





























マンリョウ




















セキコク










及氏憲邸址石碑



























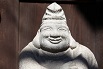






















*** 2016年1月25日 報国寺/瑞泉寺の冬 ***
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.報国寺山門 | 2.観音像1 | 3.観音像2 | 4.苔庭1 | 5.苔庭2 | 6.苔庭3 | 7.赤のツバキ1 | 8.赤のツバキ2 | 9.竹林1 | 10.竹林2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11.防災工事中の崖1 | 12.防災工事中の崖2 | 13.やぐら群 | 14.中庭 | 15.白いツバキ | 16.赤いツバキ3 | 17.マンリョウ1 | 18.中庭の石仏群1 | 19.中庭の石仏群2 | 20.中庭の石仏群3 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21.苔庭4 | 22.苔庭5 | 23.苔庭6 | 24.マンリョウ2 | 25.マンリョウ3 | 26.マンリョウ4 | 27.センリョウと マンリョウ |
28.紅白のマンリョウ | 29.マンリョウ5 | 30.ピンクのツバキ1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 31.報国寺庭園1 | 32.報国寺庭園2 | 33.マンリョウ6 | 34.マンリョウ7 | 35.白梅 | 36.赤いツバキ4 | 37.赤いツバキ5 | 38.報国寺本堂1 | 39.鐘楼1 | 40.報国寺本堂2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 41.鐘楼2 | 42.鐘楼3 | 43.茅葺屋根の セキコク |
44.竹林3 | 45.竹林4 | 46.竹林5 | 47.龍の木彫1 | 48.龍の木彫2 | 49.獅子の木彫1 | 50.獅子の木彫2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 51.凍った金魚鉢 | 52.金魚 | 53.上杉朝宗 及氏憲邸址石碑 |
54.ピンクのツバキ2 | 55.ピンクのツバキ3 | 56.衣張山への道1 | 57.衣張山への道2 | 58.道祖神1 | 59.道祖神2 | 60.衣張山への道3 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 61.富士山1 | 62.富士山2 | 63.富士山3 | 64.丹沢の山並み | 65.箱根連山 | 66.稲村ケ崎 | 67.マユミ1 | 68.マユミ2 | 69.アオキ1 | 70.アオキ2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 71.瑞泉寺参道1 | 72.瑞泉寺山門 | 73.瑞泉寺本堂1 | 74.瑞泉寺本堂2 | 75.霜柱 | 76.スイセン1 | 77.スイセン2 | 78.スイセン3 | 79.紅梅1 | 80.紅梅2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
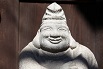 |
 |
 |
| 81.石庭1 | 82.石庭2 | 83.本堂裏側 | 84.地蔵群1 | 85.地蔵群2 | 86.どこもく地蔵 | 87.大黒像 | 88.恵比寿像 | 89.ミツマタ1 | 90.ミツマタ2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 91.ミツマタ3 | 92.ロウバイ1 | 93.ロウバイ2 | 94.ロウバイ3 | 95.ロウバイ4 | 96.ロウバイ5 | 97.ロウバイ6 | 98.ロウバイ7 | 99.地蔵堂1 | 100.地蔵堂2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 101.紅葉ヶ谷 | 102.境内の風景1 | 103.境内の風景2 | 104.瑞泉寺本堂2 | 105.ツバキの落花 | 106.濃赤色のツバキ1 | 107.濃赤色のツバキ2 | 108.赤いツバキ6 | 109.瑞泉寺竹林1 | 110.瑞泉寺参道2 |
| 1月25日(月)、本日は晴天、東鎌倉の"衣張山(標高121m)"からは、富士の雄姿が望めそうでる。またこの時期、瑞泉寺の"ロウバイ"も丁度見頃を迎えていると思われる。そこで、港南台の病院での診察の序に、東鎌倉まで足を延ばすことにする。だが今回は、受診を優先して、登山時の如くレンズ一式を持参せず、標準ズームのみの撮影に留め置くことにする。 10:54、"報国寺"に到着する。幸運にも、駐車場には1台分の空きスペースは有ったが、その大半を工事用の車が占めている。斜面を見上げると、草木が無残にも伐採されてしまっている。HPによると、"『緊急防災工事のお知らせ』度重なる豪雨の為、緊急防災工事を予定しております。・・・"とあるので、今後何らかの防災処置が施されるのであろう。山門を潜ると、左手に白亜の観音座像が望める。実に慈悲深い顔立ちであり、名だたる彫刻家の作と思われるが、NET上で検索しても、その名前は特定できない。本堂手前の石段下には、小さな苔庭があり、光に映える緑が何とも艶やかである。受付で200円の拝観料を払い、竹林手前まで来ると、艶やかな赤色の"ツバキ"が目に留まる。花の少ない時期にあって、実に目立つ存在である。ここで改めて、花言葉をチェックしてみると、日本では、以外にも"控えめな素晴らしさ","気取らない優美さ"とあるのに対し、欧米では、"You're a flame(炎) in my heart."と記されている。だが、私自身は、バラにも似た色合いから考えても、寧ろ英語表現の方が相応しいように思える。竹林を抜け中庭まで来ると、"やぐら"の岩盤上でも、防災工事が行われている。改めて画像をチェックすると、梯子を掛けられた巨木の根が剥き出しになり、崖下に転落しそうな状態になっている。HPの説明にあった通り、正に緊急事態というところか。ふと、庭園に目を遣ると、赤色の"ツバキ"の落花や"マンリョウ"の実が、緑色の苔の絨毯と、見事なコントラストを見せている。その奥には、一重の"ピンクのツバキ"も確認できるが、普段よく見かける八重咲きのものより、気品があるように思える。バラ同様、様々な種類に、改良された模様である。石庭を撮り終え、本堂正面まで戻ってくると、一人の参拝客が熱心にお祷りしている。ふと向拝に目を遣ると、見事な龍の木彫りの扁額が 掲げられている。その両側の組物の下には、龍を守るかのように、木彫り獅子も備え付けられている。何れも、木目を生かした見事な彫刻であり、名工が制作したものに間違いなかろう。写真を撮り終え、報国寺を後にしようとしたところ、受付辺りから、女性の奇声が聞こえてきる。近づいてみると、水瓶の表面が凍りつき、中の金魚が透けて見える。水温が低いせいか、金魚はじっと動かないままだが、生きている模様である。ここから、"田楽辻子の道"を通って、"衣張山"を目指す。"上杉朝宗及氏憲邸址"の石碑が立つ十字路を左折し、緩やかな坂道を数分登ると民家が途絶え、以降薄暗い杉林の中を進む。更に小さな石段を、一歩一歩踏みしめるように登って行くと、急に視界が開け、山頂に躍り出る。 11:48、"衣張山"山頂に到達する。ベンチでは、一組の御夫婦が、カップラーメンを啜っていたので、軽い挨拶を交わしたのち、そのまま展望台へと向かう。期待通り、"富士山"は惜しげもなく雄姿を見せている。2週間前に、機内から眺めた時に比べて積雪量も増え、"富士山"本来の美しさを取り戻したように見える。唯一残念なのは、この絶景を超望遠で収められなかったことだが、やはり、あらゆる被写体に対して万全の準備を尽くすのが、写真マニアたるものの心得というところか。一方、雪を被った"丹沢"を眺めていると、急に登山意欲を駆り立てられるが、冬山の危険性や私自身の体力を考慮すると、この時期は避けたほうが賢明であろう。ここから、"マユミ"や"アオキ"を撮りつつ、一旦"報国寺"まで戻り、車で"瑞泉寺"に向かう。 12:10、"瑞泉寺"に到着する。境内の一角に駐車し、受付にて200円の拝観料を払い参道を進むと、鬱蒼とした木々の中に、二手に分かれた石段が現れる。今回は、階段の上り歩数をカウントできる"活動量計"を胸ポケットに忍ばせているため、左の急階段を登ることにする。なお、この"活動量計"は、万歩計としての"3軸加速度センサー"と、高度計としての"気圧センサー"を併用して、段数を算出していることになる。それにしても、鎌倉石は摩耗が進み、すこぶる歩き難い。今後、怪我人を出さないためにも、そろそろ補修か規制が必要であろう。山門を潜り、本堂前に来ると、多くの梅の木が見られるが、未だ蕾のままである。"地蔵堂"近くまで進むと、早咲きと思しき"紅梅"が、ひっそりと咲いている。"石庭"を撮り終え、庭内を巡っていると、一人の男性が、不思議そうに"ミツマタ"の蕾を見つめている。"蜂の巣"のような実に奇妙な形をしているが、改めてオリジナル画像を拡大してみると、花芽を寒さから守るかの如く、綿毛が覆っているのが確認できる。これらの写真を撮影していると、背後から、濃厚な香りが漂ってくる。振り向くと、"ロウバイ"が太陽を背にして黄金色に輝いている。花の色形は、嘗てウイーンで見かけた"レンギョウ(2007年3月9日,11日参照)"に類似しているものの、こちらの開花時期の方が遅く、早春にずれ込むようである。そう言えば、オーストリアの地方都市Steyrの知り合いから、"春の訪れを告げる花"と聞いた覚えがある。最後に、寺の宗務所近くまで来ると、濃赤色の"ツバキ"が目に留まる。バラに勝るとも劣らぬ、実に深い色合いであり、日本原産の"ツバキ"も、様々な色合いに、品種改良されているのが実感できる。ここから、休日は大渋滞する21号線を通って、自宅に戻る。 ★活動量計データ(上り階段数:460,早歩き歩数:2503,総歩数:6635,歩行距離:5.2km,活動カロリー:872kcal,一日総消費カロリー:2595kcal,脂肪燃焼量:37.2g) |