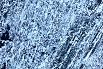11月6日(水)、谷川岳登山の朝を迎える。少しでも、登山の時間を確保するため、チェックアウトは昨晩済ませ、今朝も朝食前に荷物を車に積み込む。所で、今回初めKKR水明荘を選んだ理由だが、先ず有名な水上温泉より土合口駅に近いこと、次にOB会員用の優待プランが設定されていたためである。なお、KKRとは国家公務員共済組合連合会の略で、年金/医療施設/ホテル等を運営する巨大組織である。ただ、医療施設とホテルに関しては、一般にも開放されており、その場合1割程度高目になる。
7:50、早々に朝食を取り、水明荘を後にする。本来なら、ここからロープウエイの土合口駅に直行する所だが、途中にオープンしている店が無いため、一度水上温泉付近のコンビニまで戻ることにする。ここに到着すると、出勤時間帯とあってか、工事関係者が入れ代り立ち替わり訪れている。その間に、我々も素早く買い物を済ませ、土合口駅に向かう。到着すると、駐車場はがら空きで、まだ観光客が動き出した気配は無い。このロープウエイは、土合口駅(標高746m)から天神平駅(標高1319m)迄を約7分で結んでおり、高度が上がるにつれ、"ダケカンバ"と思しき大群落が確認できる。昨日の谷川岳山麓では、"ブナ"が大半を占め、"ダケカンバ"は確認できなかったので、やはり高度によって、縄張りが違うのであろう。そうこうするうちに、天神平駅に到着する。天神尾根ルートは、ここからスタートするが、更にペア−リフトを乗り継いで天神峠駅(標高1510m)まで登り、高度を稼ぐことにする。
9:10、リフトを降りると、眼前に雄大な谷川岳が広がっている。本日も快晴、真青をバックに、谷川岳が惜しげもなく雄姿を見せている。ただ、天神尾根ルートを目で追って行くと、昨日の"西黒尾根"程ではないものの、思いの他急峻であることが分かる。山頂部分には、"トマの耳(標高1963m)"と"オキの耳(標高1977m)"の双耳峰が確認できるが、距離の関係で、手前の"トマの耳"の方が高く見える。ガイドブックによると、"オキノ耳"まで往復6.6km、所要時間は休憩を入れないで4時間10分とある。従って、事が順調に運べば、"オキの耳"登頂も十分可能と考えられる。ここから、霜柱が溶けて少しぬかるんだ尾根道を、用心して下っていく。遥か東南の空には、優美な山容の"武尊山(ほたかやま、標高2158m))"が浮かんで見える。稜線上では、真っ赤な"ナナカマド"の実が彩りを添えている。更に下っていくと、日蔭では泥道になっていたので、ここでスパッツを装着する。行きかう人から、「これは有効ですね!」と声がかかる。暫くすると、天神平駅からの本道と合流する。この辺りが、このルートの最低点で、"ヤマケイ"によると標高1393mとか。従って、"トマの耳"までの標高差は、丁度570mということになる。この先の木製の階段から、緩やかな登りが始まる。見上げると、"ナナカマド"の実や"ダケカンバ"が多く見られるので、我々が福島を訪問した10月中旬は、極彩色の絨毯に覆われていたと考えられる。ふと足元を見ると、濃紫色の葉が目に留まる。これは、道南のオロフレ山(2009年6月28日参照)で見かけた"イワカガミ"であろうか。最初の鎖場を通過していると、土合口駅方向から、ヘリコプターが上昇してくる。暫く眺めていると、我々の上空を通過し、西尾根へと消えていく。ただ、救難信号を発していなかったので、多分定期的なパトロールであろう。
10:21、熊穴沢避難小屋(標高1460m)に到着する。中は意外と広いが、炊事や宿泊施設は無く、最少の機能しか有していない。小屋内のベンチに座って小休止したのち、登山道に戻る。この先の"熊穴沢の頭"から、愈々急登が始まる。最初のロープ場を何とか登り切ると、10分程で第二のロープ場が現れる。この辺りから、極端にスピードが落ち、後から鈴を鳴らしながら近づいてきた"山ガール"(年恰好から言うと"山レディー")に、道を譲ることになる。それでも、岩場に生える"スノキ"や"イワカガミ"の紅葉を撮りつつ、スローペースで一歩一歩登っていく。その先の西尾根の稜線は、南側が大きく切れ落ち、"川棚の頭"へと続いている。実に迫力満点で、急に近場から撮影したくなる衝動に駆られるが、このペースだと、とても西尾根まで回る余裕はなかろう。一方、天神尾根の先には、"天狗のトマリ場(標高1660m)"の岩場が確認できる。
ただ、"天狗"と言うよりは、"モアイ"にそっくりである。
11:27、やっと"天狗のトマリ場"に到着する。早速、絶景を撮影しようと岩場に足を掛けた途端、腰から転倒し、命の次に大切なカメラを、岩にぶつけてしまう。遂に愛機をオシャカにしてしまったかと、恐る恐るチェックしたところ、どうやらボディーは無傷のようである。また、マウント部の変形もなさそうで、試撮りの結果でも、異常は確認できない。してみると、フードが先に当ったことで、ボディーへの衝撃が和らげられ、本体には深刻なダメッジを与えなかった模様である。正に命拾いした格好だが、今後は岩場を歩く際は、慎重の上にも慎重を期したい。ここから、更に"天神ザンゲ岩(標高1750m)"を目指す。遥か南方には、噴煙を上げているような山が望める。
大山さんによると"浅間山"とのことだが、何度か撮影しているうちに、噴煙ではなく雲と分かる。後日ネット上で調べた所では、どうやら秩父の名峰"武甲山(標高1304m)"のようである。ふと、若かりし頃、大山さんと共に訪れた"秩父夜祭"の記憶が甦る。帰宅後、改めて古いアルバムを捲ってみると、山頂近くの神社が写っており、その山門には"三峯山"とある。従って、当時は"武甲山"には行かなかったことになるが、何れも秩父の霊山であるのは言うまでもない。機会が有れば、共に"武甲山"も訪れてみたいものである。我に返ると、南西の方角に、台形状の山が望める。山頂は、まるで鉋で削ぎ落とされたような形をしているが、これは"吾妻耶山(標高1341m)"のようである。この辺りも、急登が続き、写真を撮りつつ小休止する。別途撮影画像から逆算すると、なんと斜度23°もあることが分かる。
12:34、"天神ザンゲ岩"に到着する。時間が時間なので、ここで昼食にする。ただ、これまで休憩を取り過ぎたので、食事を早目に切り上げ、最後の急登に取り掛かる。斜度は、やや上がって24°となり、木が埋め込まれた山道を、踏みしめる様に登っていく。"肩ノ小屋"の手前まで来ると、何と先程の"山レディー"が、鈴音を立てながら下山してくる。以外の早さに驚いていたところ、大山さんと何か立話をしている。聞けば、彼女は"トマの耳"で引き返したとか。何とか"肩の小屋"まで登りきると、西尾根が上越国境沿いに延々と続いている。ふと、川端康成(2011年9月10日参照)の"雪国"の冒頭部分が思い浮かぶ。即ち、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。・・・」であるが、ここで、"長いトンネル"は谷川岳の真下を通る"清水トンネル"を、"停留所"とは同トンネルを抜けた最初の駅である"土樽"を指す。また、今朝傍を通ってきた"土合駅"は、同トンネル内の中間駅と言うことになる。私が、後期の授業(機械技術英語演習特論)のオリエンテーションで、"雪国"を取り上げたのも、何かの御縁であろうか。我に返ると、小屋の営業は終了しており、登山客もその横のベンチで食事をしている。ただ、周辺のマンホールから"芳香"が漂ってきたので、早々に撮影を切り上げ、直ぐ先の"トマノ耳"へと急ぐ。
13:15、遂に双耳峰の一つ"トマの耳"に到達する。正に絶景、ここからは、360°の大パノラマが広がっている。北方には、もう一つの双耳峰"オキの耳"が望めるが、往復30分以上も掛るため、大山さんと相談の結果、撮影後はここから引き返すことにする。南方の"西黒尾根"を辿っていくと、通称"ザンゲ岩"の先が、急激に落ち込んでいるのが確認出来る。改めて、画像から角度を逆算してみると、斜度50°を優に上回る。一方、山頂からは、垂直の壁がマチガ沢まで1000m近くも切れ落ちており、正に目が眩む光景である。ただ、万一転落して、救難ヘリの御厄介になると拙いので、撮影は差し控えることにする。眼下には、昨日訪れた"マチガ沢出合"も確認できる。ここで、撮影に熱中している間に、あっという間に30分が経過する。スケジュール表を作成した大山さんから、下山の催促が有ったので、そろそろ腰を上げることにする。
今回は、11月5日/6日の両日、大山さんと共に名峰・谷川岳に初挑戦した。2日目も絶好の登山日和に恵まれ、勇んで出発したものの、途中で失速し、大山さんに御迷惑をかける結果となったが、迫力満点の大自然に出会え、谷川岳の秋を十二分に堪能することが出来た。次回は、大山さんの"記念日"に、共に新たな山に挑戦したい。
"
総歩数:約15,807歩
登りの厳しさ:▲▲〜▲▲▲(熊穴沢ノ頭からの登り)
|