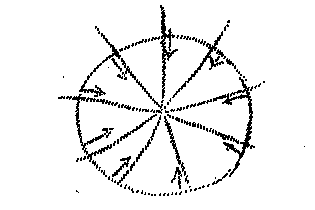
ここから第二講に入ることになります。第一講ではこの講義の前提となる姿勢と視点が語られていましたが、その全体からさらに進んで、まずは「人間の本質において支配的なある種の二元性」に着目しながら、人間の本質へとアプローチしていくことになります。
第一講では、動物とは違って、人間では、負荷のかかっている力に、さらに垂直方向の力と結びついて平行四辺形の力が働いていて、それは骨組織だけではなく、筋肉組織についても、重要な視点が提供できるということが述べられていましたが、ここではその視点がさらに、心臓学へと向けられていきます。
昨日選択しましたような出発点から先に進んで、人間の本質において支配的なある種の二元性に着目することにより、さらに人間の本質へと徐々に迫って行きたいと思います。
すでに昨日気づかれたように、私たちは、動物においては未だ負荷のかかっている力を、ある種の垂直方向の力と結びつけて平行四辺形を成す必要があり、筋肉の反応においてもそれに相応した類似が見られます。この人間の骨組織と筋肉組織の研究における考えかたをさらに追究すると、その追究の際に今日経験がすでに与えることのできること全てを助けにすると、おそらくは骨学、筋肉学からすぐさま、医学にとって従来なされていたよりも意味のあることを為すことが可能でしょう。
けれどもとりわけ困難なのは、人間の認識を、今日心臓学から出発する時に医学が必要としているものと結びつけることです。私が申し上げたいのは、骨学、筋肉学において初めてその構想を示すものは、心臓学に関して培われてきた見解において根本的に生じてきたということです。
通常、心臓は血液を送り出すポンプであるととらえられています。そのポンプであるということを説明するために、その力学的構造が問題にされているのです。しかし、その観点を疑ってみることが必要です。心臓の活動というのは、「原因」ではなく、「結果」だといえるのです。つまり、心臓はポンプとして血液を送り出しているのではないのです。
と言いますのも、そもそも一般に人間の心臓についてーーまずはこれに限定しようと思いますーーどのような見解が持たれているのでしょうか。心臓は血液をさまざまな器官に送り出す一種のポンプである、というふうに見られています。そしてこの「心臓」というポンプ機構を説明すべく、あらゆる興味深い力学的な構造が考案されているのです。さてこの力学的な構造は、胎生学に全く矛盾しているのですが、この力学的心臓論を実際に疑ってみること、少なくとも通常の科学においては制御しないにしても、この心臓論をもう一度制御することに留意されてはおりません。
心臓観においてとりわけ考慮せねばならないことはーーまずは概略を述べましょう、後日お話することは、最初に観点として示す必要があったことを、少しずつ裏書きしていくかたちになると思いますのでーー、この心臓というものは全くもって、一種の活動している生体組織と呼ばれうるようなものではないということです。なぜなら、心臓の活動は原因ではなく、結果だからです。
この、心臓はポンプではないということを理解するために、人間の生体組織での活動において生じる二元性に着目しなければなりません。二元性というのは、呼吸プロセスと消化プロセスとの間の対立であるといえます。栄養分の摂取、消化、血液中の移動ということを見ていくならば、栄養分を取り入れる血液の活動と空気を取り入れる呼吸の活動の間の相互作用にまで、栄養の消化ということを追求することができるのです。
呼吸プロセスと消化プロセスの対立においては、何かが均衡しようとします。液体状になった栄養素と呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間に生じる相互作用がありますが、この相互作用は、お互いに働きかけあう力のなかで生じ、その互いに働きかけ合うものが、心臓において、互いの働きかけを妨げあうのです。
この原則が理解できるのは、皆さんが人間の生体組織におけるあらゆる活動の間に生ずる二元性に着目する時のみでしょう。すなわち、栄養分の摂取に関係する活動、さらに栄養分の消化に関わる活動と、直接かあるいは血管を通じての、栄養分の血液中への移動に関わる活動、これらの活動間に生じる二元性です。いわば生体組織内で下から上へと、栄養分を取り入れる血液と空気を取り入れる呼吸との間にまず生じる相互作用まで栄養分消化を追求できるからです。その際観察される経過を正確に見るなら−−実際正確に見さえすればよいのですが−−、呼吸プロセスに中にある全てのものと、最大範囲の消化プロセスの中にあるものとの間に、ある種の対立があることがおわかりになるでしょう。
ここでは何かが互いに均衡をとろうとします。いわば、お互いに渇望し合うものが、お互いに満たし合おうとするわけです。もちろんもっと他の表現を選ぶこともできるでしょうが、先に進むにつれて、もっと良く理解できると思います。液体状になった栄養素と、呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間にまず生じる相互作用があります。この相互作用が厳密に研究されねばなりません。この相互作用は、お互いに働きかけ合う力の中に生じます。そしてこの互いに働きかけ合うもの、これがいわば、心臓においてその互いの働きかけを妨げ合うのです。
心臓は、生体組織の下部の活動である栄養分の摂取、消化と生体組織の上部の活動である呼吸という、上下の活動の滞留器官として存在しているのです。(「滞留器官」というのは、原文ではStauorganとなっていて、Stauはせき止めるもの、澱み、渋滞、それを動詞化したstauenはせき止めるということorganは器官という意味です。)
心臓の活動は、液体養分と外部から取り入れられた空気との間の相互作用の「結果」だということなのです。血液をポンプのように送り出す「原因」ではなく、「結果」として考察していく必要があるわけです。
ここで少しシュタイナーの論とは別に少し付け加えておきますが、東洋医学などでいわれる「心経」「肝経」というのが「心臓」や「肝臓」などの臓器そのものを指しているのではないといわれるのと関連するのではないかと思われます。これについては、今後少し勉強してみながら、その関係を見ていければと思ってます。
心臓はひとつの滞留器官(Stauorgan)、つまり、私がさらに生体組織の下部の活動と呼びたい栄養分の摂取、消化と、呼吸をその最下部の活動に組み入れたい生体組織の上部の活動、この上下の活動の滞留器官として存在しているのです。
ひとつの滞留器官が組み込まれているわけで、その際本質的なことは、心臓の活動は、液体状になった栄養素、すなわち液体養分と、外部から取り入れられた空気との間の相互作用の結果であるということです。心臓に表現されている全て、心臓において観察されうる全ては、まずは力学的な意味で、ひとつの結果として考察されねばならないのです。
この観点において、心臓の活動の力学的な基礎について、オーストリアの医師、カール・シュミット博士は1892年の「心臓の動悸と脈拍の曲線」という論文で、心臓をポンプ的なものであるとはとらえているものの、心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を水流によって動かされるひとつの流れの結果としてとらえています。
唯一有望な発端は、少なくともこの心臓の活動の力学的な基礎に一度注目する−−もちろんそれ以上ではありませんーーことで、この口火を切ったのは、オーストリアの医師、カール・シュミット博士でした。
彼は北部のシュタイアマルクの医師で、”ウィーン医学週報”の1892年15号から17号に彼の「心臓の動悸と脈拍の曲線」が掲載されたのです。この論文にはまだそれほど多くのことが含まれてはいませんが、少なくともここにひとり、扱うべきは通常のポンプとしての心臓ではなく、ひとつの滞留装置としての心臓なのだと、自らの医療実践から気づいた人がいたことは言っておかなくてはなりません。
シュミットは心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を、水流によって動かされる水撃ポンプとして想定しています。カール・シュミット博士の論述に内在する真理はまさにこの点なのです。心臓の活動であるもの全てを、液体の流れと気体の流れーーここでは象徴的にこれらを流れと呼ぶことができますーー、これらの互いに入り込んでいく流れの結果として把握する時初めて、力学的なものに近づくのです。
心臓はつまり、ひとつの感覚器官なのだといえます。心臓は、人間の上部の活動が下部の活動を知覚、感受することを可能にするための感覚器官なのです。眼は外界の色彩現象を知覚するように、心臓は、下半身で起きていることを知覚しているのだといえます。
結局心臓とはいったい何なのでしょうか。つまるところ、心臓とはひとつの感覚器官なのです。たとえ私たちが心臓の感覚活動であるものを直接は意識しないとしても、つまり心臓で起きていることが、識閾下の感覚活動に属するものであるとしても、やはり心臓は、いわば人間の上部の活動が、人間の下部の活動を知覚し、感受することを可能にするために存在しているのです。
ちょうど皆さんが眼によって外的な色彩現象を知覚するように、皆さんは、もちろん暗い下意識においてではありますが、皆さんの下半身で起きていることを心臓を通じて知覚しているのです。結局のところ心臓とは内的知覚のための感覚器官なのです。心臓はそういうものとみなされねばなりません。
人間における「二元性」を理解するためには、心臓は、人間の上部の活動が下部の活動を知覚、感受することを可能にするための感覚器官であり、下半身で起きていることを知覚しているというように、人間は、上部から下部を知覚する二重構造である存在だ、ということを知らなければなりません。
しかし、さらにつけ加えなければならないのは、心臓は、上部と下部の均衡を表現している下意識的な知覚器官であり、人間の生体構造の二極間を中継しているということです。生体構造の一方の極は、呼吸活動、感覚−神経活動という関連している全てでありもう一方の極は、栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連している全てです。
この原理によって、初めて人間の生体構造を理解することが可能になります。解剖学、生理学、生物学をこの原理で探究していくことができるのです。心臓に中継されている上部と下部を区別しない限り、人間を真に理解することはできないといわなければなりません。
人間における二元性そのものを理解できるのは、人間は本来、このように上部から下部を知覚する二重構造の存在であるということを知る時のみなのです。
しかしここで次のようなことを付け加えておかねばなりません。より広い意味での栄養分の摂取、栄養分の消化を呼吸との同化に至るまで研究する時に、下位部分の活動、つまり人間の本性全体の一方の極が与えられました。呼吸との同化はその時律動的活動と共に行われます。私たちの律動的活動の意味についてはさらにお話すべきことがあるでしょう。しかし呼吸活動と組み合わさり、呼吸活動に所属していると見なければならないものは、感覚−神経活動、すなわち外的な知覚とこの知覚の継続に関わる全てのもの、神経活動による知覚の加工に関わる全てのものです。
つまり皆さんが、一面において、呼吸活動、感覚−神経活動という関連している全てのものを思いうかべてくださるなら、いわば人間の生体構造の一方の極が得られるのです。
他面において、栄養分の摂取、栄養分の消化、言葉の通常の意味での新陳代謝である全てのものを総合的に見れば、人間の生体構造におけるプロセスのもう一方の極が得られます。
心臓は本質的に、その観察できる動きにおいてこの上部と下部の均衡を表現している器官であり、心意的あるいはもっと良い言い方をするなら下意識的な知覚器官であって、人間の生体構造の二極間を中継しているのです。解剖学、生理学、生物学が提供してくれる全てのものを、皆さんはこの原理に向かって研究することができます。そうすれば、この原理によって初めて人間の生体構造の中に光が差し込むことがおわかりになるでしょう。心臓によって中継されているこの上部と下部を区別しない限り、皆さんは人間を理解することはできないでしょう。なぜならこれは、人間の下部の生体活動において起こっている全てのものと、上部の生体活動において起こっているものとの間の根本的な差異だからです。
人間の下部の生体活動と上部の生体活動との差異を下部で起こっていることはすべて上部に反対の対応物としてのネガを持っているということによって表現できます。上部に関連するものはすべて、下部に対応物を見出すことはできるのです。ネガとポジの関係にあるということができます。
ここで重要なのは、上部と下部は物質的に中継されているのではなく、「対応」しているということです。ですから、中継するものとしての物質的な仲介物、つまりコードや導線のような管がそこにあると考えてはなりません。
たとえば、上部に関係しているものとして「咳」をとりあげてみるとすると、それに対応する下部のものは「下痢」のなかに見出すことができます。こうした対応関係を正しく見ていくことで、真の人間理解が可能になるのです。
この差異を単純に表現しようとすれば、下部で起こっていることはすべて、上部にそのネガ、つまり反対の対応物を有している、と言うことができるでしょう。上部に関連するものはすべて、常に下部においてその対応物を見出すことができるというわけです。るわけではなく、対応しているということなのです。下部におけるあるものを、常に正しく上部における別のものと関連づけるということを理解しなくてはなりませんが、物質的な仲介物を見出すことを目指す必要はありません。
単純な例として、私たちの咳、これは上部と関係しているという意味で上部に属しているわけですが、下部において咳に対応するものは下痢のなかに見出せます。上部に対応するするものが常に下部において見出せるのです。こういう対応関係に正しく着目することによってのみ−−同様のものは観察していくうちにしばしば登場してくるでしょう−−、真の人間理解に到達できるのです。
しかし、このことを抽象的な対応関係としてとらえてはいけません。健康な生体組織では、上部と下部に緊密な補完関係があるのです。上部と活動と下部の活動は、常に相互に対応し、制御し、お互いを方向づけていくようなものでなければなりません。特に重要なのは、下部のプロセスに対する上部のプロセスの方向付けです。
しかしながら単にこのような抽象的な対応関係があるだけではなく、健康な生体組織においては同時に上部と下部との緊密な補完関係が成立しているのです。
健康な生体組織において成立している補完関係とは、上部のもの、つまり呼吸と関係する活動であれ、神経−感覚機構に関係する活動であれ、何らかの上部の活動は、下部のものに何らかのかたちで抑制せねばならず、下部と完全に調和しなければならない、ということです。
何らかのかたちで下部が優勢になったり、支配的になったりすると、つまり下部がそれに対応する上部の活動にとって強くなりすぎると、あるいは逆に、上部がそれに対応する下部の活動に対して強くなりすぎると、すぐさま−−これは後ほど病気のプロセスを正しく理解することにつながっていくでしょう−−生体組織に変則が生じます。
上部の活動と下部の活動の関係は常に、両者が何らかのしかたで相互に対応し、互いに制御し、両者がいわばお互いに方向づけられながら経過していくようなものでなければなりません。ここに確固たる方向づけが存在します。この方向づけは人によって異なりますが、下部のプロセス全体に対する上部のプロセスの確固たる方向づけが存在するのです。
「健康な生体組織」では、上部と下部に緊密な補完関係があり、特に、下部のプロセスに対する上部のプロセスの方向付けが重要なわけですが、そうした「健康な生体組織」から「病気の生体組織」へと至るにはさまざまな推移があります。ちなみに、上部は、呼吸活動、感覚−神経活動という関連し、下部は、栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連しています。
さて、病気の徴候を見ていく場合、機能的な在り方、つまりエーテル体(パラケルススにおいてはアルケウス)において見ていくならば、その上部と下部の二元性について語ることができます。しかし、その二元性に関しては、必ずしも両者が対応関係にあるとは限らず、その関係が変則的になっているということに注目する必要があります。
さて、この上部が下部に対応して健全な作用をする生体組織から病気の生体組織まで至る推移が見出せます。
パラケルススがアルケウスと呼び、私たちがエーテル体と呼ぶものにおける病気のかすかな兆候を出発点とすると、あるいは、皆さんが外部から、つまりこういう事柄については何も知ろうとしない人々に悪く思われないように取り繕うとすると、やはり皆さんは、機能的なもの、動的なもののなかの病気の徴候、いわば病気の最初のかすかな兆しについてまずは語ろうとするでしょう。
私たちがこれらを出発点とし、まずエーテル体あるいは機能的なもののなかに最初に予告されるものについて語るなら、二元性についても語ることがでます。ただこの二元性はすでに自らのうちに、対応しないもの、変則的なものを有しているのです。これは次のようにして生じます。
健康な生体組織では、食物において作用している力は、すべて上部によって克服されているのですが、下部を完全に制御する(エーテル化しつくす)ほどには、上部が強くないという場合も生じます。その場合、下部における栄養分の化学的、有機的な力が優勢になります。
下部において、つまり栄養分摂取とより広い意味での消化機構において、摂取された栄養分の内的、化学的な、あるいは有機的な力が優勢であると考えてみてください。
健康な生体組織においては、私たちが実験室で食物を分析して得られる、食物そのものの中で作用している力、食物に内在している力はすべて、上部によって克服されており、生体組織内部の効力にとっては全く問題にならず、外的な化学、外的な動力学その他のいかなるものも行われず、あらゆるものが完全に克服されています。
けれども、下部を実際完全に掌握し、いわば完全に料理しつくし、こういう言い方が可能ならエーテル化しつくす−−こう言えばいくらか厳密に語ったことになります−−ためには、それに対応する上部が十分強くない、という事態も起こりうるのです。その場合、人間の生体組織においては、通常は外界で起こっていて人間の生体組織のなかでは起こるべくもない、本来人間の生体組織には属さない優勢な経過が現れます。
物質的な身体はこうした変則的な在り方を完全にとらえることができないので、そのプロセスは、エーテル体、アルケウスという機能的なもののなかにまずは現れてくることになります。そうした新陳代謝プロセスが独立的な傾向を強める在り方を「ヒステリー」と呼ぶことができます。
本来のヒステリー現象というのは、そのような不規則な新陳代謝が頂点にまで達した状態なのです。そのヒステリーのプロセスにおいては、人間の生体組織のなかにあってはならない不規則な新陳代謝が生じているのだといえます。
これが、一方の極です。
物質的身体は、このような変則性に完全には捉えられないので、こういう経過は、まさに機能的なものと呼ばれうる、エーテル体、アルケウスのなかにまず現れてくるのです。
この変則性の特定の形式から取られたと思われる慣用表現を選択するとすれば、ヒステリーという表現を選ばなければなりません。新陳代謝プロセスが多大な独立性を持つようになることを表す用語として、ヒステリーを選択しようと思います−−後ほどこの表現が悪くない選択であったことがおわかりになると思います−−。
狭い意味での本来のヒステリー現象は、実際この不規則な新陳代謝が頂点にまで達した状態にほかならないのです。事実、性的な症候にまでいたるヒステリーのプロセスにおいて本質的に存在しているのは、の人間の生体組織なかにあるべきではない、その本質において外的なプロセスであるような不規則な新陳代謝にほかなりません。こういうプロセスに対して上部は、それを克服するにはあまりに弱すぎることがわかります。これが一方の極です。
一方の極は「ヒステリー」ですが、もう一方の極は「神経衰弱」です。
それは、先ほどとは逆に、上部のプロセスが、上部の組織を酷使しすぎ、そのプロセスが正常に経過しないということによって起こります。そのプロセスはあまりに霊的であり、器官的に知性的すぎるのだといえます。心臓により下部の組織に中継される前に終わってしまうのです。つまり、心臓での滞留を通じて、上部でのプロセスが下部に流れ込むことができなくなっている状態なのです。それは、先の「ヒステリー」の場合の反対、下部のプロセスのネガだといえます。
ヒステリーの特徴とともにそのような現象が現れてくるときは、人間の生体組織の下位部分において、人間の外部にある活動が強くなりすぎた状態なのです。
しかし、上部のプロセスが正しく経過しないこと、つまり上部のプロセスが上部の組織を酷使しすぎることによっても、同様の不規則な相互作用が起こります。それは反対のプロセス、いわば下部のプロセスのネガであって、上部のプロセスをあまりに激しく使いすぎるのです。
このプロセスはいわば、心臓によって下部の組織に中継される前に終わってしまいます。つまりこのプロセスは、あまりに強く霊的であり、あまりに−−こう表現してよければ−−器官的に知性的すぎるのです。こうして変則性のもう一方の極、神経衰弱が現れてきます。
このように、人間の生体構造の機能的なもの、エーテル体における「ヒステリー」「神経衰弱」という二つの変則性に注目する必要があります。それは、上部で表現され、下部で表現される欠陥であるといえるからです。
病気によって欠陥が生じた器官そのものを実際に見て診断することは、単に結果としての現象に過ぎません。それよりも重要なのは、病気の全体像、形状に注目することです。つまり、病気の実像そのものをトータルに見るということなのです。参考までにいうと、こうしたことはシュタイナーがよく言う「ゲーテ的世界観」につながる観察法に結びつくものだといえます。こうした視点を拡大していく必要があるのです。
まだ人間の生体構造の機能的なものに潜んでいるこれら二つの変則性に、何にも増して注目せねばならないと申し上げたいのです。それらはいわば上部で表現され、下部で表現される欠陥だからです。そして人間の生体構造におけるこの二元性が何らかの欠陥のもとになっているということが、次第に理解されるようにならなければなりません。
つまり、神経衰弱は、上部があまりに激しく上部の器官を使って機能することであり、その結果、本来は上から心臓で中継されて下部で起こるべきことがすでに上部で起こり、上部で行われてしまうので、その活動が、心臓での滞留を通じて下部の流れに入り込むということがなくなってしまうのです。
おわかりでしょうか、欠陥を生じた器官の実見よりもはるかに重要であると申し上げたいのは、病気の実像の外的形状(Physiognomie:骨相、人相、形状、外観、外面的特徴)を観察することです。なぜなら欠陥を生じた器官が示すものは単に結果としての現象にすぎないからです。重要なことは、病気の全体像、形状に注目することなのです。この病気の形状は常にある種の仕方で皆さんに、一方かあるいはもう一方への傾向を持つ、つまり神経衰弱的なものか、ヒステリー的なものへの傾向を持つ実像を提示してくれるでしょう。もちろん、こういう表現を通常の言語使用に向けて拡大しなければなりません。
人間の生体組織における、呼吸活動、感覚−神経活動に関連した「上部」と栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連した「下部」の相互作用について、新陳代謝プロセスが独立的な傾向を強める在り方が「ヒステリー」であり、それとは逆に、上部のプロセスが、上部の組織を酷使しすぎ、そのプロセスが正常に経過しないということによって起こるのが「神経衰弱」ですがそうした実像から認識されるのは、最初は単に機能的、エーテル的に存在しているものがその力を凝集することで、物質的現象が刻印されるということです。
たとえば、最初はヒステリーの徴候としてだけ存在しているものが、下半身の疾患という形で物質的に現れたり、神経衰弱の場合も、喉の病気、頭部の病気として現れたりしますが、そのようにひとつの組織で起こることは、組織全体にも作用を及ぼすことになります。そうしたことを研究することこそが、医学の未来のために重要になります。
さて、この上部と下部の相互作用について満足のいく実像が得られたなら、そこから出発して徐々に次のようなことが認識されるでしょう。すなわち、最初は単に機能的に存在しているもの、つまり私たちが言うところのエーテル的なもののなかで起こっているものが、いわばその力を凝集することで、器官的ー物質的なものをとらえていくこと、そして最初はヒステリーの徴候としてのみ存在しているものが、さまざまな下半身の疾患のなかにいわばその物質的な形態を取り得ること、他面において神経衰弱は、喉の病気、頭部の病気のなかに器質的な形態を取り得ることについて語ることができるのです。
神経衰弱的なものとヒステリー的なものに、当初は機能的なものだったこれらの物質的現象が刻印されるということ、これを研究することこそ未来の医学にとってはなはだ重要なことでしょう。器質的となったヒステリーの結果として、消化過程全体、下半身のあらゆる経過に不規則が生ずるでしょう。けれども、このようにひとつの組織で起こることは、さらに組織全体にも作用を及ぼします。不規則として生じていることが、さらに組織全体にも作用を及ぼすということを見過ごしてはなりません。
たとえばヒステリー現象が、機能的、エーテル的にはまったく現れず、エーテル体が即座に物質体に押しつける場合がありますが、この場合、下半身の器官には疾患として現れてはきません。つまり物質的な病気にまでは到らないのです。しかしそれは、器官の疾患としてはあらわれてはこないものの、内部には存在していて、生体組織全体に働きかけています。
そういう状態は病気と健康の間を漂っている状態だといえますが、その場合、下部から上部へと作用し、上部に反作用を与え、上部のネガのなかに、それが現れてくるという特殊な現象が起こります。そうした現象が、結核の素質をもたらすのだといえます。ふつうは神経衰弱を引き起こす領域に、ヒステリーの最初の物質的な結果である状態が作用して、結核の素質が現れるというのです。
さて、その初期に機能的のもののなかに観察できるとしたら端的なヒステリー現象であるようなものが、そもそも機能的には全く現れてこないという場合を考えてみてください。確かにこういうことが起こりうるのです。機能的に表面に現れてくることなく、エーテル体が即座にそれを物質体に押しつけるのです。それは下半身の器官においてどんなかたちであれ明らかな疾患としては現れてきませんが、内部には存在しています。
つまり下半身の器官には、いわばヒステリーの刻印を押されたものがあるのです。これは物質的なものに自らを押しつけたことにより、ヒステリー現象として心的に前面に現れてくることはないのですが、かと言って、やっかいな病気、物質的な病気であるにはまだ十分強くないのです。
けれどもこれは、生体組織全体に働きかけるには十分な強さを持っています。その時、病気と健康の間を漂っていると申しましょうか、そういうものが、下から上へと作用を及ぼし、上部に反作用し、上部にいわば伝染してそのネガのなかに現れる、こういう特殊な現象が起こります。そこが一面的になったり、不規則になったりするとふつうは神経衰弱を引き起こすもとになる領域に、ヒステリーのいわば最初の物質的な結果である状態が作用してそこに現れる、こういう現象が結核への素質をもたらすのです。
結核になりやすい素質は、下部の活動の上部への反作用です。こうした生体組織の持つ原−素質、つまり結核になりやすい素質に遡ることで、結核の本質を見出すことができます。
細菌に感染するのは、そうした結核になりやすい素質の結果生じます。もちろん、結核菌に感染することで結核になるのですが、細菌による伝染は必要条件のひとつであるということであって、それだけで結核という病気が真に理解されるのではありません。
ちなみに、「恐るべき範囲に広がっている」といっているように、シュタイナーがこの講義をした当時は、結核に罹る方が多かったようです。結核菌の発見から、結核の流行、死亡率の現象までに関しては、訳注を参照してください。
これは興味深い関係です。結核になりやすい素質は、皆さんにただ今お話した、下部の活動の上部への反作用なのです。このように完全に終わりきらないプロセスが上部に反作用することによって生じる、この全く独特な相互作用が結核への素質をもたらすのです。
この人間の生体組織の原−素質(Ur-Anlage)とも言うべきものにさかのぼらないと、合理的に結核を扱う方法を見出すことはできないでしょう。と申しますのも、寄生生物(訳注)が人間の生体組織にはびこるということは、たった今皆さんにお話しました原ー素質の結果生じる現象にすぎないからです。
このことは、必要な条件がそろえば結核のような病気は伝染する、という事実に矛盾するものではありません。もちろんそのために必要な条件が整わなければなりません。しかし、この下部の器官活動の優勢は、残念ながら今日の人類の極めて大多数に現れておりますので、結核になりやすい素質は、今日実際恐るべき範囲に広がっているのです。
必要条件のひとつとはいえ、細菌に感染するという観点は有効なもので、結核に罹っている方はやはり、その周囲に作用を及ぼしていきます。そういう意味で、最初の原因である第一次発生と伝染という概念は、ともに特にこの結核においては正当なものです。しかし、伝染という現象に関しては、必ずしも細菌の存在を原因としなくても説明は可能であって、伝染という現象から結核の本質がわかるのではないのです。
とはいえ、伝染というのはこの領域においてやはり有効な概念です。かなりな程度に結核を病んでいる人は、周囲の人々に作用を及ぼすからです。内部で結核患者が生活しているものにさらされていると、通常は単なる作用にすぎないものが、今度は原因になりうる、ということがまさに起こってくるのです。
私はいつも、ひとつのたとえ、アナロジーによって、この、病気の第一次発生と伝染との間の関係を明確に説明しようとしているのですが、たとえば次のように言えるのです。
私が道で、ふだんそれほど親しくつきあっていない友人と出会ったと考えてください。彼は悲しそうにやってきます。彼の悲しみには理由があります。彼の友人が死んでしまったのです。私が彼に出会い、彼が自分の悲しみを私に告げることにより、私も彼と一緒に悲しくなります。彼は直接の原因によって、私は伝染によって悲しくなるわけです。この場合確かなことは、この伝染の条件は彼と私とのお互いの関係のみである、ということです。
従って、第一次発生と伝染、という概念はどちらもまったく正当であり、とりわけ結核においては極めて正当なものなのです。ただ、合理的な意味においてこれらを真に用いなければなりません。
結核療養施設がほかならぬ人工結核孵化場となっていることは少なくありません。結核患者を結核療養施設に詰めこむと、この施設をできる限り何度も繰り返し取り壊して、別の施設に作り替えねばならないでしょう。一定期間ののちには、結核療養施設は結局さらに遠ざけられねばならないでしょう。なぜなら奇妙なことに、結核患者自身がきわめて感染させられやすい素質を有していて、彼らはもっと重い結核患者の近くにいると、そうでなければもっと良くなっているかもしれない病気がおそらくいっそう悪くなってしまうからです。
こうした結核の本質に関する事例から、人間の生体組織のさまざまなプロセスについて理解できるようになります。つまり、人間の生体組織における、呼吸活動、感覚−神経活動に関連した「上部」と栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連した「下部」とが密接な関連しあっているという事実から、病気の本質を探究することができるようになるのです。
さて、まずはとりあえず、結核の本質を指摘しておくだけのつもりでした。私たちはこの結核を一つの例として、人間の生体組織におけるさまざまなプロセスが、いかにお互い密接に関連し合っていなければならないかを理解します。これらのプロセスは、皆さんにもご想像いただけると思いますが、お互いにポジの像とネガの像が相対しているように対応している、上部組織と下部組織があるのだという事実に常に影響を受けざるをえないのです。ご説明しましたような生体組織の構造が存在することによって結核が準備されるという、いわば極めて特異な現象を手がかりにして、その経過のなかでさらに、そもそも病気の本質をどのように見るべきかを研究することができるのです。
<訳注>
* 寄生生物:原文ではDie Parasiten(Der Parasit:寄生動物、寄生植物の総称)の複数形で、ここでは広い意味での「細菌」の意味あいも含まれていると思われます。
ちなみに、ローベルト・コッホによる結核菌の発見は1882年で、同時に発表された論文により、この菌が結核の第一次的要因になるという説が認められました。
20世紀になると、ストレプトマイシンの効果が1944年に発表され、同時期にパラアミノサリチル酸、その後イソニアジドの抗結核性も実証されるなど、新薬の発見が相次ぎました。なお、肺結核の死亡率は17世紀半ばに非常に高くなり、その後徐々に低下し、再びピークを迎えたのは、18世紀の終わりから19世紀前半ということで、この講演の時期(1920年)と一致しています。シュタイナーは1925年に亡くなっているので、ストレプトマイシンのことは知る由もないのですが。興味深いことに、イギリス、フランス、ドイツなどでは、すでにストレプトマイシンの投与が始まる以前から死亡率が下がり始めていたそうです。けれども、日本で肺結核による死亡率が激減した1950年代は、ちょうどストレプトマイシンと新しい肺外科の技術が導入された時期と一致しているそうです。(訳者)
参考:山崎幹夫 「薬の話」中公新書
結核患者には、咳、喉や胸、四肢の痛み、疲労状態、特に寝汗などが徴候として現れてきますが、これらは上部と下部の不規則な相互作用の結果として生じているものです。しかし、これは同時に病気に対する生体組織の戦いでもあります。
たとえば、咳の場合、下部組織が上部組織によって制御されないで起こるのですがこれは、侵入してくるものを防ぐための生体組織の健康な反応です。ですから、咳を止めてしまうということが、害になることもあります。咳を止めることで、肉体が有害なものを受けいれてしまうからです。
咳をするというのは、そうした有害なものに耐えられないがゆえに起こるのであって生体内に侵入してくるものを侵入させないために必要なことなのです。
結核患者になりかかっている、つまり将来結核が現れてくる兆しがある人にきわめてしばしば見られる徴候を取りあげてみましょう。おそらく彼が咳をするのに気づかれると思います。また、彼が喉や胸の痛み、あるいは四肢の痛みも感じていることに気づかれるでしょう。さらに、ある種の疲労状態、そしてとりわけ盗汗(寝汗)に気づかれるでしょう。これらは何なのでしょうか。これらの徴候を目の前にするとき、これらすべてはいったい何なのでしょうか。私が今挙げたものはすべて、何よりもまず、先ほどお話しました内部の不規則な相互作用の結果として生じているものなのです。けれどもこれは同時に、もっと深い根拠として存在しているものに対する、生体組織の戦いでもあります。
おわかりでしょうか、咳を−−まずはこのような単純な事柄を観察し、それからもっと複雑な事柄に移っていきます−−咳を、いかなる場合でも常に克服することは、全く良くないことなのです。生体組織にとっては咳をわざと引き起こすことが必要な場合さえあるのです。人間の下部組織が上部組織によって制御され得ない場合に咳の刺激として現れるものは、さもなければ侵入してくるものを侵入させないための、人間の生体組織の健康な反応なのです。
したがって、いかなる場合にも咳を直接止めてしまうことは、場合によっては害になることもあり得るのです。肉体が有害なものを受け入れてしまうからです。その人のその時点での素質ではこうした有害なものに耐えられず、それを取り除こうとするために、彼は咳をするのです。咳の刺激は、生体組織に何らかのものが欠けていて、そのために生体内に侵入してくる可能性のある侵入者を侵入させない必要性がある、ということを示すものにほかなりません。
咳の場合と同じように、喉や四肢の痛みといったものも、下部が上部によって制御されないで起こるプロセスが起こらないように結核の素質があるために近づいてくる有害なものに対して、生体組織が戦っているのだといえます。
ですから、結核の素質があるとわかったならば、適度に咳を引き起こすようにしたり、食餌療法によって病気の徴候を引き起こすことで、生体組織を支えることが有効な場合もあります。
たとえば、痩せるということもひとつの防御手段です。ですから、ある人が痩せていくからといって、すぐに太らせるための食餌療法をとるのが有効だとは限りません。そうしたことについて、個別的に研究していくことが重要なのです。
私たちが挙げた別の徴候もまた、結核の素質があると近づいてくるものに対する、生体組織の防御、戦いなのです。喉の痛み、四肢の痛みはまさしく、生体組織が、上部のプロセスに制御できないような下部のプロセスが起こらないようにしていることを示しているのです。
例えば逆に、早めに結核の素質に気づいたら、適度に咳の刺激を引き起こしたり、とりわけ−−どういうふうにこれをすることができるかは、明日以降の講演で見ていきます−−、ある種の食餌療法によって疲労の徴候を引き起こすことさえして、生体組織を支えるのが良いこともあるのです。
さらに、例えば痩せるということも、ひとつの防御手段にすぎないのです。なぜなら、痩せない場合におこってくるプロセスは、下部における、上部に制御され得ないものに他ならないかもしれず、その場合生体組織は、制御され得ないものが一時的に存在しないように、痩せることによって自らを守るからなのです。
ですから、例えばある人が痩せていく場合、すぐさま太らせるための食餌療法をほどこすのではなく、こういう事柄を個別的に研究することが非常に重要です。痩せるということが、まさにその時点で生体組織に現れてきていることにとって、たいへん良い意味を持っている可能性もあるからです。
また、結核に対する生体の防御反応としてとりわけ重要なのは盗汗(寝汗)です。
そして、まだ結核患者ではないけれども、結核にかかる見込みのある人の場合、とりわけ有益なのは盗汗です。なぜなら、盗汗は、睡眠中に実行される生体組織の活動に他ならず、これは本来ならば目覚めている時に、完全な霊的−心的活動のもとに行われるはずのものであるからです。本来ならば昼間に完全に目覚めた状態で行われるべきことが行われず、夜になって現れてきているのです。これは結果の現象であると同時に防御手段でもあります。生体組織が霊的な活動から解放される一方で、生体組織は盗汗に表される活動を行うのです。
発汗などのあらゆる分泌現象は、目覚めた意識的活動に対応するものであり、魂的、霊的活動に密接に関係しているのですが、それに対して、生命的な構築プロセスは無意識的なものです。肉体をもっとも活発に形成する必要のある乳児がほとんど眠っているというのはこのことと深く関係しているのだといえます。
もっともこうした事実を完全に評価することができるためには、あらゆる分泌現象は、汗の形成も含めて、普通は魂的、霊的活動がその中に含んでいるものと密接に関係しているということについて、少しばかり知っておかなくてはなりません。
構築するプロセス、本来の生命的な構築プロセスというものは、すなわち無意識的な基盤をなすものにすぎません。目覚めた、意識的な魂的−組織的活動に対応するもの、これはいたるところにおいて、分泌プロセスなのです。私たちの思考というものも、脳の構成的プロセスには対応しておらず、脳の分泌プロセス、分解プロセスに対応しています。盗汗という現象は、通常の生活において本来は霊的−魂的活動と平行して進行していなければならないはずの分泌プロセスなのです。上部と下部が正しい相関関係にないので、そういう分泌プロセスは、生体組織が霊的−魂的活動から解放される夜まで持ち越されることになるのです。
病気の諸症状の間には相互作用が生じています。痩せるという症状は、諸々の症状の間の相互作用のなかのひとつなのだといえます。ですから、そうした症状をひとつひとつばらばらに見るのではなく、一連の連関のなかでそれを見ることが大切なのです。
結核の場合にも、生体組織自体にそうした反応を引き起こす力(防御反応のひとつ)がない場合には、それを助けて反応を起こすようにすることは、合理的なことなのです。
健全に病んでいる人間の生体組織の成長と生成全体と関係している、あらゆる出来事を注意深く研究すれば、病気の諸症状の間にも相互作用が生じていると言えるところまで導かれることがおわかりになると思います。痩せることはまずもってひとつの症状です。しかしながら、結核の素質との関係において、つまりいくらか活動し始めている結核との関係において、この痩せるということは、諸々の症状の間の相互作用の一部なのです。すなわち、ひとつの組織体、諸々の症状の観念上の組織体とでも言うべきものが成立しているのです。ひとつの症状はある意味でほかの症状に属しているのです。
従って、生体組織の他の条件によって何か反応のようなものが起こるとき−−結核の例にとどまりますが−−、生体組織自体にこの反応を引き起こす力がない場合は、これを助けて反応を起こしてやること、まさにひとつの病気に別の病気が続くようにしてやることは、全く理にかなったことになるのです。
古代の医師たちは、霊視力を持ってそうした諸連関を見ていたがゆえに、別の症状との正しい関係をもたらすために、ある症状をも引き起こすことができなければならないことを知っていました。病気を癒すことができると同時に病気を引き起こすこともできなければならないわけです。
古代の医師たちはこのことを、医師のためのいわば意味深い教育法則として語ってきました。医師であることによって危険なのは、単に病気を取り除くことができねばならないというだけではなく、病気を引き起こすこともできなければならない、ということだ、と古代の医師たちは語りました。−−つまり医師は病気を癒すことができるのと全く同じ程度に、病気を引き起こすことができる、というわけです。
隔世遺伝的な霊視力によってこういう関連についてもっと多くのことを知っていた古代人たちは、医師のなかに、彼が悪意を持てば、人々を健康にするばかりでなく病気にすることもできる人物を同時に見ていたのです。けれどもこのことは、他の発病状態との正しい関係をもたらすために、何らかの発病状態を引き起こさなければならない必然性と関連しています。とはいえ、これらは病気の状態であることは確かです。咳、喉の痛み、胸の痛み、痩せる徴候、疲労の徴候、盗汗、これらはすべて、病気の症状には違いないのですから。これらの症状は引き起こされねばならないとはいえ、やはり病気の症状であることは間違いないのです。
防御反応として起こしたことであっても、一度そういう症状を起こした場合には、適当な時期が訪れたときに、それを治療してその症状をなくさなければなりません。
結核の場合、防御反応として咳のや喉の痛みが引き起こされた場合には、通常、下部においては便秘状態になっているのですが、それを改善するために、下痢の状態へと導かねばならないのです。
このことから、半分治療した時すなわちこれらの症状を引き起こした時点で、病人をその運命に委ねてしまうことはできず、この時こそ治療プロセスの第二の部分が現れてこなければならない、ということがおのずと容易にご理解いただけると思います。
その時は、単にこれらの反応、つまり病気を防ぐために引き起こしたものが存在するように配慮されねばならないだけではなく、今度はこの反応を癒し、生体組織全体を再び正しい道に導くものが生じてこなければならないのです。
したがって例えば、結核の素質に対しての自然なあるいは場合によっては人為的に引き起こされた防御として、咳の刺激が引き起こされたとき、また喉の痛みが起こったりあるいは引き起こされたときには、その際常にいくぶん詰まった状態つまり便秘状態を呈しているであろう消化プロセスが秩序正しいものになるように配慮されねばなりません。
何らかの方法で気づかれることでしょうが、ひとつの防御プロセス、一種の下痢に移行させられねばならないのです。常に、咳の徴候や喉の痛みその他に続いてこのような下痢が起こることが必要なのです。まさにこのことが、上部に現れていることをそれ自体として観察してはならず、たとえ物質的な媒介物はなく、対応関係があるだけだとしても、上部に現れていることの治療を、下部における経過を通じて探究せねばならないことが多々あるということを示唆しているのです。このことは何にもまして考慮されてしかるべきなのです。
防御反応の症状は、適当な時期に、それを克服しなければなりません。新陳代謝が優勢であって、それが上部によって制御されないときには疲労の徴候が現れますが、その場合には、消化活動を活発にさせる必要があります。痩せるという症状に対しては、脂肪を形成させるような食餌療法が必要ですし、寝汗という症状も、汗を出させるための活動が必要になるのです。
疲労の徴候−−私はこれを単に主観的な疲労徴候と呼ばずに、本来常に新陳代謝の優勢に基づいている、全く組織的に引き起こされた疲労徴候と呼びたいのですが−−、新陳代謝が上部によって制御されない時に強く現れるような疲労徴候は、結核の場合これが実際に引き起こされねばならないので、その後必要な時点で克服されねばなりません。
つまり、それに応じた食餌療法によって−−こうした食餌療法の詳細についてはさらにお話すべきことがあるでしょうが−−、消化が優勢になるように、すなわちその人の通常の状態よりも消化活動が活発になるように、いわばもっと簡単に消費されてしまうものが、消化プロセスを通じて消費されるように配慮することで、こういう疲労徴候は克服されねばならないのです。
痩せることも、今度は一種の脂肪形成,つまり器官や器官組織のなかへの蓄積を起こさせるような食餌療法によって、後から克服すべきでしょう。盗汗もまず最初に引き起こされた後に、きわめて知的な活動、つまり努めて熟考するなどして実際に汗を出すような活動を指示することを試みることによって、後から克服されねばなりません。そうして再び健康な発汗が促されるのです。
病気の諸関連を見ていくならば、病状を強めたり弱めたりすることで病気の経過を必要な方向に導き、やがて生体組織のプロセス全体を健康にしていくことができるようになります。
まず最初に心臓の活動を正しく把握することにより、人間において上部と下部がいかに対応しているかを理解するなら、さらに、神経衰弱やヒステリーのような、機能的なもの、エーテル的なもののなかに病気の最初の発生、いわばかすかな兆しが見られることを理解するなら、器官的なもの、物質的なものにそのとき刻印されているものを理解することへも進んで行けるのだということがおわかりになると思います。こうして相関しあっている病気の像の外観を研究することにより、−−最初に引き起こすものも含めて−−いわば病気の経過を、場合によって病状を強めたり弱めたりさえしてある方向に導き、時期が到来すれば、プロセス全体を再び健康にすることができるでしょう。
こうした医学的処置をするにあたって、最大の障害となるのは、社会的状況であり、また患者自身であるといえます。患者は、まず症状そのものを取り除くように求めるからです。しかし、そういう処置をしてしまうと、病状をもっと悪くしてしまうこともあるのです。
言うまでもなく、こうして少しばかり特徴をお話しました処置にとって、最大の障壁はまず第一に状況、社会的な事情です。従って医学とはまったくもって社会的な問題でもあるのです。
他面において、最も強力な障壁を築いているのは患者自身であるともいえます。患者は当然のことながら、何はさておき、何かを、彼らが言うように「取り除いて」ほしいと要求するからです。しかしながら、彼らが持ってい るものをそんなに直接取り除いてしまうと、すでにそうなっているよりももっと病気を悪くしてしまうという事態が容易に起こりうるのです。患者を今の状態よりももっと悪くしてしまうことも考慮しておかなくてはなりませんが、彼らを再び健康にすることができる状態になるまでは待たなくてはならないのです。けれども、大多数の皆さんにご同意いただけるでしょうが、その時にはたいてい患者さんは逃げ出してしまっているわけです。
治療を正しく方向づけるためには、医師は病気の後のケアも完全にしなければならないのですが、症状を取り除いたことで満足してしまいがちです。障害は、医師にもあるのです。
そもそも治療というもの全体に正しい価値を与えようとすれば、医師は後療法をも完全に掌握していなければならないのですが、これこそ、健康な人間及び病気の人間の正しい観察の結果帰着することなのです。こういうことこそ、まさに公然と目指されねばならないのです。現代のような権威信仰の時代にあっては、このような動きがが導入されさえすれば、その必要性を指摘することが困難であったりしてはならないはずです。
しかしながら、言うまでもなくーー皆さんの前でこのようなことを申しあげるのをお許しいただきたいのですがーー、病気をほんとうにその支脈の末端まで追求することを適切であるとみなさず、単に何かを取り除いたことで多かれ少なかれ満足しているのは、いつも患者や社会状況であるのみならず、医師のかたがたであることもしばしばあるのです。
治療にあたっては、上部と下部の二元性を正しく把握しなければなりません。それは唯物論的な見方に基づいた言葉によっては、非常に説明しにくいのですが、シュタイナーはそれを、アナロジーによって説明しようとしています。
とはいえ、このように人間の生体組織のなかでの心臓の位置づけを正しく追求することが、私たちを病気の本質へと徐々に導いていくということはご理解いただけると思います。
ただ、皆さんに注目していただかねばならないのは、下部の諸々の組織的活動は単に外的な化学的活動であるものをなるほどある意味で克服してはいるけれども、それと全く反対の上部の活動にやはり何らかのしかたで類似しているというとき、これら(上下)の間に成立している徹底的な差異なのです。
人間の生体組織におけるこの二元性[Dualismus]に満足に足る定義を与えることは非常に困難です。私たちの言語は、物質的、器官的なものに対立するものを暗示すための手段をほとんど有していないからです。けれども、まず次のようなアナロジーによってーーこういう事柄について語るべきことはもっとたくさんあるでしょうけれどーー、本来この下部プロセスと上部プロセスの間の二元性がどんなものなのかを明確にするなら、もしかすると良くご理解いただけるかもしれませんーーもしかすると皆さんのどなたかの何らかの先入見にぶつかるかもしれませんが、私はあえてそういたします。
シュタイナーは、上部と下部の二元性をホメオパシー(同種療法)で説明しています。物質の特性は、一律にどこまでも分割可能なものではなくて、ある限界を超えると反対のものに転化する可能性すらもっています。自然にはそうしたリズミカルな過程があるのです。
皆さんが何らかの物質の特性を考えるとき、つまりどういうかたちであれ私たちの前にある物質が効力を生じる際の特性を考えるとき、まず第一に、消化の際に起こっているように生体組織によって克服されて人間の下部の活動に取り入れられるものが考えられます。
さて、こう言ってよろしければ、ここでホメオパシー(同種療法)(**)を行うことができます。その物質の集合性、連関性を止揚することができるのです。このことは、その物質を何らかのやりかたで希釈するとき、いわゆるホメオパシー的極小量を用いるときに生じます。よろしいでしょうか、このとき、現代の私たちの自然科学全般においてまともに観察されていないことが明らかになるのですが、人々はすべてを抽象的に観察することに慣れっこになってしまっています。ですから、ここにひとつの光源があるとすると、彼らは、光はあらゆる方面へ広がっていく、と言い、これがあらゆる方面へ広がっていって無限のかなたで消滅する、と考えるのですーー彼らは太陽についてもそう考えます。けれどもこれは正しくありません。このような活動はいかなる無限のかなたでも消え去ることはなく、ある範囲の限界まで達するのみで、その後弾力性をもっているようにはね返ってきます。たとえその性質はしばしば往路の性質とは異なっているにしても、はね返ってくるのです(図)。自然のなかにはリズミカルな経過があるのみであって、無限のかなたに通じる経過は存在しないのです。リズミカルに再びそれ自身にはね返ってくるもののみが存在しているのです。
これは単に量的な拡散にのみあてはまることではなく、質的な拡散にもあてはまることなのです。皆さんがある物質を分割し始めるとき、その物質は最初の出発点において特性を持っています。これらの特性は、無限に減っていくのではなく、ある点にいたると、はね返ってきて、それとは反対の特性になるのです。
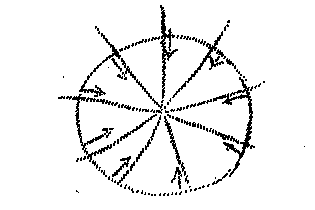
上部と下部の対立性もそういうふうにイメージすることが可能です。生体の上部組織と下部組織の間にもこうした内的なリズムがあります。上部組織はホメオパシー的なもので、下部組織は特性がある時点で逆転したものであるといえますから、その特性を利用して、薬剤師は希釈を行うことで、下部組織に関係した諸特性を上部組織に関係した諸特性に導くことができるのです。
私たちの生体の上部組織と下部組織の間の対比もこの内的なリズムに基づいています。私たちの上部組織はホメオパシー的なものです。それはある意味で通常の消化プロセスの正反対のもので、その反対物、ネガを形成するものです。したがって、ホメオパシーの薬剤師は希釈をおこなうことで、普通は人間の下部の生体組織に関係していてこれと関係のある諸特性を、今度は人間の上部の組織に関係のある特性へと、実際に導いているのだ、と言うことができるでしょう。
これはたいへん興味深い内的な連関です。この連関については明日以降さらにお話していきましょう。
<訳注>
**ホメオパシー[Homoeopathie] 同種(類似)療法。健康体に与えるとその病気に似た症状を起こす物質を、ごく低濃度に希釈し、それを薬品としてその病気にかかった患者に投与して治療する方法。アロパシー[Allopathie](逆症療法)はちょうどこれとは逆のやりかた。シュタイナーはホメオパシーとアロパシーをどう捉えるべきかさらに第五講で述べています。
<第2講・終了>