
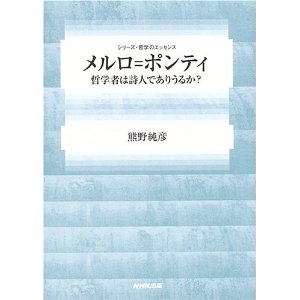
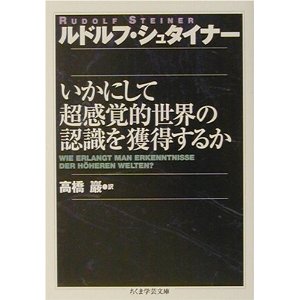
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.3.12
◎esquisse5
奥行きを見ること
存在者との呼吸
世界との呼吸
記憶の向こう側の奥行きを見ること
世界表象
 |
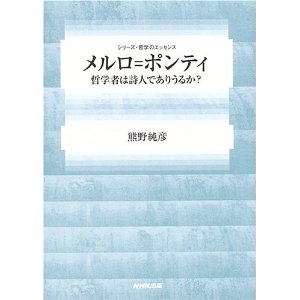 |
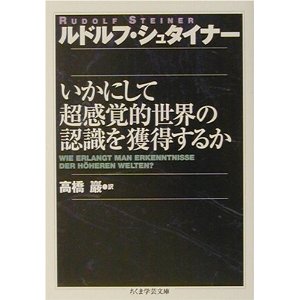 |
|---|
◇引用テキスト
(テクスト:熊野純彦『メルロ=ポンティ 哲学者は詩人でありうるか』NHK出版)
岩は、ただそのかたちと色合いについてだけ「見られている」のではない。岩は、ざらざら
したその手ざわりにおいて見られ、動かしがたいその重量感においても見られている。質感と
量感がともに見られていることで、見られた岩には厚みと嵩とが与えられ、たしかに存在する。
あるいはそこに「ある il y a」ものとして見られることになる。画家が描く岩肌は、二次元の画
布のうえに色とかたちだけを用いて、岩の重量感と手ざわりとを描きとっている。ひとの視覚
は見えない(はずの)ものを見ている。画家の筆は、視覚をとらえかえすことで、見えないも
のを見えさせているのである。
たとえばセザンヌの「サント・ヴィクトワール山」のことを考えてみよう。それが教えている
のは、そもそも、かたちとは、色とはなにかである。(…)セザンヌの絵筆が、かたちをあえて
デフォルメすることで示しているものは、「生まれ出ようとする秩序」であり、生まれようとす
る自然自体にほかならない。(『意味と無意味』)
見ること、視覚に固有の次元については、もうひとつの問題がある。ひとは空間の深さを、つ
まり「奥行きprofondeur」を見ているということだ。私が奥行きを見ているとは、しかし、どの
ようなことなのだろう。
ある種の考え方によれば、そもそも奥行きは見えるはずがない。じっさいに見えるものは、網
膜上に映った二次元の像である(はずである)からである。奥行きはその場合、すこしずつずれ
た両眼が収斂するなかで与えられると考えられるか、あるいは、見かけの大きさの縮小や、対象
像の鮮明さの低減を手がかりに構成されるものと考えられる。そのように考えられるとき、奥行き
は「横から見られた幅」とおなじものととらえられている。だが、私が見ているのは、まさしく奥
行き、空間の深さであって、「幅」、ひろがりではない。深さがひろがりに置き換えられたとたん、
「奥行きは見えなくなる」のである。(…)
奥行きは、見られた世界そのもの、世界にぞくする事物から引き出されることはできない。それ
は意識によって、事物や世界に付与されたものであると語ることもできない。奥行きは、それは、
なにから生まれるのだろうか。メルロ=ポンティの答えは、こうである、「奥行きは私の視線のも
とで生まれる。私の視線はなにか或るものを見ようとこころみるからである」。私の視線がなにか
に向かっていることこそが、奥行きの知覚を生むのだ。
(・・・)
奥行きの知覚とは、単純にいえば、ものがそこに見えるという経験である。あるいは、より正確
に語るとするならば、ものがそこにあることをめぐる経験のことである。奥行きとは世界の厚みの、
「嵩voluminosite」の経験である。世界が世界として存在し、しかも私に対してひろがっていること
の経験なのである。
(・・・)
見えないはずの木肌のざらつきを見、目でその木肌に触れているとき、木々のおもてをたどる私の
眼は、また幹の表面によって触れられている。見えないはずの奥行きのなかで、木の幹と厚みを見て
いるとき、奥行きの深部から私もまた視線を向けられている。しっとりと湿気を帯びた森の気配、強
く、けれども秘めやかに立ちこめている生命の薫り、微妙な陰影を示す緑、木漏れ日、葉が擦れあっ
て立てるかすかな音、達ならぶ樹木、敷き詰められた落ち葉、そうした空間の深さ(profondeur)のな
かで、つまり経験の奥行きのうちで、木々もまた、私をまなざしているのではないだろうか。じっさい
ひとは、かなたにうす暗闇をつくっている森の奥底から、なにかが視線を向けているのを、感じること
があるのではないか。ーー「ひとがインスピレーションと呼ぶものは、文字どおり受けとめられるべき
である。ほんとうに、<存在>の吸気(inspiration)と呼気(expiration)があり、<存在>における呼吸
(respiration dans Etre)がある」。
(P.87-93)
◇note5
◎私たちが見ているのは、実際に見ているのは、「網膜上に映った二次元の像」でしかない。
テレビもコンピューターのディスプレイのしても、それがたとえ3D的な見せ方をするシステムがあったとしても、
そこに私たちが見ているのは平面の像である。
しかし、私たちは多くの場合、そこに「奥行き」を見ている。その「奥行き」というのはいったい何だろう。
私たちはそこに何を見ているのだろう。
◎メルロ=ポンティは、私たちが見る「奥行き」を、世界の厚み、「嵩」の体験であると示唆している。
世界が世界として存在している。そして私に対して広がっているという経験そのものである。
そしてさらに、前回のnote4にもあったように、見るということは単なる光の遊戯ではなく、
眼でふれる、眼でつかむという体験であり、さらにいえば、まなざしをする、眼でふれる、
眼でつかむということは、逆にものにまなざしされていること、ふれられていること、つかまれているということでもある。
◎つまり、わたしたちが奥行きを見るということは、見ているものとのあいだで「呼吸」しているということだ。
岩を見るということは、岩という存在者に対して、「呼」びかけ、「吸」い込むということを繰り返しているということ。
そうすることで、岩という存在者は、逆に、私たちに「呼」びかけ、「吸」い込んでいる。
◎従って、世界が世界として存在している。そして私に対して広がっているという経験というのは、
そのように世界を呼吸している、世界に呼吸されているということでもある。
◎上記引用部分の射程はここまでであるが、重要なのはある意味ここからである。
私たちは目の前にあるものだけを「見ている」のではない。
少し前に、あるいは昨日、昨年、数十年前に見た岩や樹木をも「見ている」。
それは、記憶でもあるが、さらにいえば記憶をも超えている向こう側の「奥行き」をも「見ている。
その向こう側の奥行きというのはいったい何だろうか。
◎シュタイナーは、植物の生成と衰退や植物の種の中に潜在している生成力、
結晶の形態などについての内的な像を形成する沈潜の時間を持つ瞑想法を
『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』で示唆している。
◎たとえば、目の前に「種」を置く。この種から芽がでて根を張り、双葉が出、茎が伸び、
さらに葉を次々に広げ、花を咲かせ、実を付け、やがて枯れていくことを内的に表象する。
見えている「種」のなかにあるであろう潜在力を内的なイメージの力で顕在化させ展開させていく。
もちろん、イマジネーションの世界のなかで。
◎そのとき私たちはいったい何を見ているのだろうか。
実際に見ているのではない「見ること」。その「奥行き」。
そしてそのとき、私たちは何と呼吸しているのだろうか。
そしてそこに広がっている「世界」とはいったいどのような「世界」なのだろうか。
◎そして、私たちが普通「見ている」と思っている対象世界の表象と記憶のなかでの世界表象、
そして対象を持たない純粋なイメージのなかでの表象とはどのような関係にあるのだろうか。