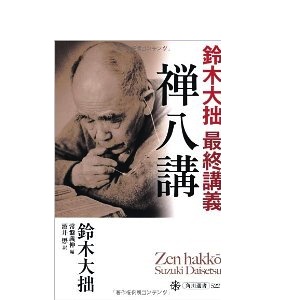
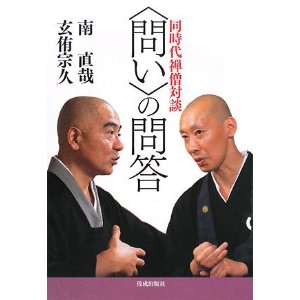
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.6.10
◎esquisse22
《大疑・疑問符そのものとなること》
・子どもの「なぜ」という問いとそれに答えるということ
・権威としての「答え」に自足してしまう大人
・逆に権威に対するアンチを「答え」の反対のものとしてしまう大人
・仏教の「四法印」
・「涅槃寂静」のイメージのもつパラドックス
・「私」がいないことで成立する「涅槃寂静」
・「答え」を求めるための問い
・「出来レース」としての問題と解答
・大疑・疑問符そのものとなること
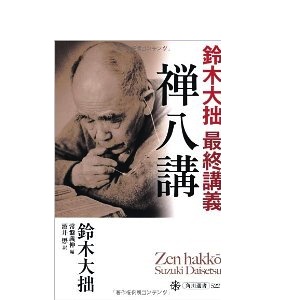 |
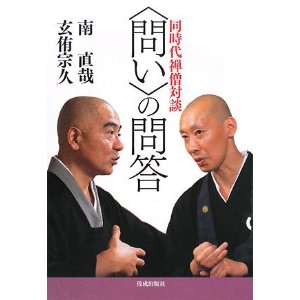 |
|---|
《note22》
◎子どもは「なぜ」をつぎつぎに繰り出して大人を困らせてしまうことがある。子どもは適当な答えでそれなりに納得することもあるし、ファンタジーを喚起するようなかたちで、「なぜ」を繰り出した子どもも、答えた大人もそれなりに満足することもあるかもしれない。それはそれで幸せでクリエイティブな体験となるかもしれない。
◎しかし、子どもは成長していくにつれ、つまりはみずからが「大人」になるとともに「なぜ」を失っていき、自分の世界を「答え」で埋めそれなりの世界のイメージをつくりあげるか、自分の外に権威をつくって自分は理解できないまでも、権威からの言葉を「答え」として受けとめて自足したりする。あるいは、自分の外に敵、つまりは権威の反対のものをつくりあげて、それにアンチや批判をぶつけて、自分の世界をネガティブに守ろうとする。
◎私たちはさまざまな疑問をもち、その答えを見つけようとする。そして、そのときどきにでてくる疑問にそれなりの答えを見つけてその都度、それなりに納得する。納得しようとする。しかし、「なぜ」をどんどん突き詰めていっても、「ほんとうの答え」というのはおそらくはどこにも見つけることができないことに気づくはずなのだが、多くの場合はそうはならないように思える。それなりの答えで自足しておくことで自分を守ろうとするのかもしれない。つまり、自分を守るための「答え」で囲い込んでそれで世界を構築し、それに反するものはそれを拒否し、ときにはそれを否定・攻撃することで自分の世界を守ろうとする。
◎仏教に根本原理とされている「諸行無常」「諸法無我」「一切皆苦」「涅槃寂静」という「四法印」というのがある。一切のものは無常、変化しないものはなく、因縁生起(縁起)によって生滅変化を繰り返していている。また、すべての存在は実体としての我(自性)がなく、「相互依存的相関関係、相依性《そうえしょう》として関係性のもとに存在している。私たちは、さまざまなものを実体的にあると錯覚してそれにとらわれて苦しんでいる。そうした無常、無我、一切皆苦を去るために、八正道を実践することで、迷い・苦しみのない静かで安らかなる清浄な心を保てるようになる・・・といったことなのだけれど、それを安易に物語的にとらえると、その「涅槃寂静」という絶対的な答えがあるというふうに錯誤してしまうのではないかと思う。この生きている地上は無常だけれど、悟りを得たら絶対的な「常」なる世界がそこにある、と。
◎そこにパラドックスがあることに気づくのはそんなにむずかしくない。迷い、苦しみのない静かで安らかなる清浄な心をもっている状態というのは、すでに「私」はそこにいないのである。極論をいえば、「一切皆苦」だというのは「私」がそこにいるということである。だから、「苦」を去るということは、「私」をなくすということである。「私」をこの身体を持って生きている私だとすれば、単純に死ねば解決するということになってしまう。肉体そのものを私としなくても、苦しまないためには、その肉体のない私も滅さなければならなくなる。肉体上の自殺、魂上の自殺である。それは「私」ではなく、自己、高次の私、ハイアーセルフだとしても、すでに「私」はそこにはいないはずである。「私」がそこに存在していないからこそ、そこには苦しみはない。だから、悟る私もすでにそこにはいない。そうなると、浄土だとか死後の世界だというのも意味がなくなる。いったいだれがそんなところにいるというのだろうか。すでに私はどこにもいないというのに。
◎このように、「答え」を求めるための問いというのは、すぐにパラドックスに陥ってしまうか、そうでなければ、ある種の絶対的権威を持ち出して、そこからでてくる「答え」を盲信するための問いしかもちえないということになってしまう。「奥行き」や「永遠の今」へのアプローチも同様である。最初から見えている答えに向かって「出来レース」を走ってみても意味がない。
◎鈴木大拙は、6年に及ぶ思索と瞑想と苦行の末に仏陀が直面した状態を禅家では「大疑」といっているという。「仏陀は疑問符そのものと完全に一体化」したのだという。それこそが「永遠の今」。そこにあるのは、「涅槃寂静」という言葉からイメージされてしまう変わらない永遠ではなく、「大疑問符」そのものだというのである。その「大疑問符」には「答え」がない。もしあるとすれば、「大疑問符」そのものであるというパラドックスがそこにあるのだといえる。論理化できない論理とでもいおうか。論理そのものが成立しえない論理とでもいおうか。従って、言語でそれを表現しようとすれば、それはパラドックスそのものでしかなくなるはずである。
◎仏陀や禅家の至るそうした「大疑問符」とまではいかないまでも、「問う」ということそのものについて、そのことは意識されている必要があるのではないかと思っている。少なくとも最初から「答え」の用意されているような問いは問いとして成立しえないということである。その意味で、この「エスキス」で記そうとしていることは、受験用問題集のような正解の用意されているような問いとはまったく性質を異にしている。さまざまな引用や参考テキストなどにしても、それらは「権威」として引っ張ってきているわけではない。「問い」を引き出すということがその主題となっている。
◎しかし、世の中にはなんとたくさんの「答え」とそれを導き出すための「問題」があり、それを教えようとする「権威」ある教師がいることだろうか。おそらくは、「奥行き」への旅を難しくしているものがあるとすれば、「答え」を求めようとすることそのものなのではないだろうかと思う。必要なのは、みずからが「疑問符」そのものになることなのだろう。「疑問符」そのものになるということは、みずからが「!」になるということであり、そこからさまざまに「方便」として導き出されるものを絶対化したふりをしないということだろう。ニーチェではないが、それらを「真理」としたとたんに、その「真理」はそれ以外のものを「虚偽」としてしまうことになる。そしてそこにはすでに「!」は消え失せている。
◎ついでに、下に、南直哉・玄侑宗久の「問いの問答」から少し引いている。問うことそのものの重要性に関するところである。興味深い問答ではあるが、そこには「仏教」「禅」という「権威」が、それを絶対的なものとしてはいないまでも、その対話を囲い込むものとして確固として置かれている。南直哉の道元的なラディカルさも、その中でのラディカルさとなっている。釈迦は仏教を起こしたが、おそらくは仏教を超えていたはずである。重要なのはおそらくそのことだ。「!」は「仏教」とされている宗教に閉じ込められないで発せられることでさらにその喝!度を高めることができる。もちろん、僧侶であることそのものが囲いとなっているというのではなく、多かれ少なかれひとはそれなりの囲いのなかでしか生きられない。そうではなく、そのうちにあってそれにとらわれないで発することのできる「!」もまたあるのではないかと思うのである。
◇参考テキストからの引用
A)鈴木大拙『鈴木大拙 最終講義 禅八講』(角川選書522/平成25年4月25日)
6年に及ぶ思索と瞑想と苦行は、仏陀の「聖求」にはすべて無益と知れたのだが、その後、仏陀が絶望的な探求でもつかめなかったあるもの、未知のあるもの、すなわち大いなる疑問符号〝?〟を追求する探求心を支えたものは何か。
仏陀はこの大いなる疑問符号〝?〟の追求のために、自らの手中にあるあらゆる手段を使い尽くした。それでもなお彼に残っていたのは何か。未知の、底無しの深淵に飛び込む際に使って効果のある何かが仏陀には残っていたのだろうか。(・・・)
今や仏陀の状況は、通常瞑想とか安定法とか意識を消して真っ直ぐに無(…)に人を飛び込ませる術とかして普通に知られているようなものではなかった。六年に及ぶ、無駄ではあったが激しい努力の末に仏陀が直面した状態は、禅家では「大疑」といわれているものである。
その時、仏陀は大いなる疑問符そのものであった。仏陀がその「聖求」を始めて以来、立ちはだかってきた疑問符はもはやなかった。仏陀は疑問符そのものと完全に一体化し、前に掴むべき対象としてはなにもなく、後にまだ何か欠けているとして自分の背を押すものもなく、仏陀には過去も未来もなく、仏陀は過去や未来と関係ない、現在そのものであった。仏陀が「時間」で、つまり永遠なのだから、仏陀には「時間」がなかった。仏陀即大疑問符は最高のもので、その中にすべてがこめられていて、疑問符の奥底で区別も分化もなだないままの、あらゆる可能性の源であった。この疑問符こそは、実に絶対の自己である。なんとなれば、その中にはこれだのあれだのの二元がなく、主客の分離もなく、自我と非我の区別もないからである。
(P.185-186)
B)南直哉・玄侑宗久『同時代禅僧対談 “問い”の問答』(佼成出版社 2008/01)
南 (…)仏教あるいは道元禅師や親鸞聖人、弘法大師もそうなのかもしれませんが、僕がとくに禅の言葉にシンパシーを感じるのは、そこに<絶対に閉じさせまい>という覚悟を感じるからなのです。(…)<閉じる>というのは、ある問いに対して「答えはこれだ」と一つの答えをポンと出して、問いを塞いでしまうことです。それは、玄侑さんの言葉で言えば<異界を異界でなくしてしまうこと>であり、<わかったことにしてしまうこと>です。
玄侑 ええ、そうなると、もう運動は停止します。たとえば『臨済録』では「釈迦に会ったら釈迦を殺せ」というのがそれですね。権威として奉るようなものを作ってしまった時点で、おしまいです。
(P.83-84)
南 僕はですね、徹底的に相対化を止めない、裏切り続けるーーつまり、「無常である」という言説を教えとして実現するには、一定の立場を常に自分で破壊していくことがぜったいに必要なんだろうと思うのです。あくまでも相対化を止めてはいけない。安住したところでは、すべてが終わります。無常というもののリアリティが落ちてしまって、仏教ではなくなるということがあると思います。
(P.95)
南 答えの出る「問題」というのは、どうでもいいことがほとんどですね。答えが簡単に出る問題は、すでに答えを前提に問題をつくっているのですから、これは大したことはないんです。
厳密に言えば、<問い>と問題は違います。問題として構成される以前の<問い>というのは、これは致し方なくそこにあるもの、始末に負えないものです。それを誰かが適当に問題として構成して、答えの出るものにしてしまう。「問題を作る」ということは、言語のなかに<問い>を取り込み、解体する作業です。つまり、ただ単に「えーっ!」と絶句するしかできないこと、「それは何か」とか「それはどういうものか」みたいな問題として言語化し、構成していく。それは、「答え」を前提につくるのですから、手持ちの答えがすでにあるとうことです。(…)しかしほんとうに決定的なものは、問題として構成されえないのです。
(P.213-214)