

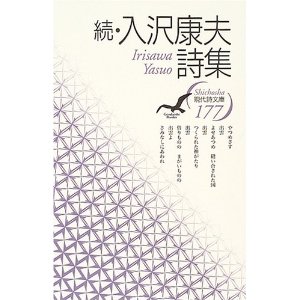
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.6.5
◎esquisse21
《私という現象》の多重構造〜《テクスト》のアナロジーとして〜
・「詩作品」としての「私」
・「私という現象」を重層的に意識する
・テキスト内的意識主体の多重構造
・地上における「私という現象」の多重構造
・私というペルソナの背後の高次世界にある「自己」の多重構造
・地上における多重構造と高次世界における多重構造の結び
・「私という詩作品」の「根源」にあるもの
・傀儡でありながら使い手でもある「私」の自覚と習熟
 |
 |
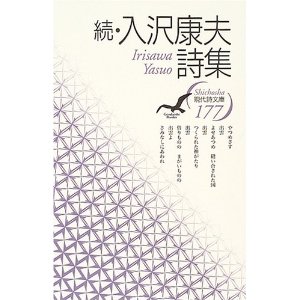 |
|---|
《note21》
◎「私」をひとつの「詩作品」としてとらえてみる。この地上世界において書かれていくきわめて創造的で詩的なポエジーとして。
◎それでは、その「私」を書くのは誰で書かれるのは誰なのだろうか。そのことを観ていくためには、「私という現象」を重層的に意識してみる必要がある。
◎「私」をこの肉体のなかで「脳」がつくりだした意識であるとする唯物論的科学主義的な見方もあるが、それではなにも観えてこない。おそらく「脳」はコンピューターのハードウェアであって、それはソフトウェアとしての魂がなければ機能しないただの箱でしかないし、そのソフトウェアはそれを使ってなにがしかの操作をしているオペレーターが存在している。キーボードの前にいる「私」である。
◎そうした「私という現象」をどのように理解するかで、「私」そのものの多重的なあり方を垣間見ることができるだろうし、「私という現象」を映し出すもしくはそれが演技されている時間と空間といった「奥行き」の観え方は大きく異なってくるはずである。
◎さて、詩作品には「書く人」と「読む人」がいて、「書く人」は同時にまたは書かれたあとで「読む人」でもある。そうした「読む」ことについて考え始めてからもう40年近く経っている。そして、大学での卒論は、「文学テクストの受容」をめぐるものだった。そこには、作品(テクスト)の内的構造と作品(テクスト)が生きて働いているコミュニケーション構造が関わっている。
◎作品(テクスト)の内的構造についていえば、そこには一人称ないしは三人称の背後にいる語り手がいる。そしてその語られている語りのなかに、さまざまな主体による語りが展開されていく。しかも、語り手のメタレベルには、作品(テクスト)の内的な作者が控えている。これは、実際の肉体をもった作者ではなく、機能的に、作品(テクスト)を働かせている作品(テクスト)内的な作者のことである。そのように、作品(テクスト)は三重の内的構造をもって機能している。
◎この(詩)作品における主体の問題についてはさまざまな研究家からの示唆を受けたが、もっとも深く影響しているのは詩人の入沢康夫の『詩の構造についての覚書』『詩的関係についての覚書』だろうと思っている。たとえばそれをこのように表現することもできるだろう。「私は <私は 「私は書く」 と書く> と書く」。この構造は何重もの形でマトリョーシカ風に表現できる。
◎以上のことをまとめると以下のような《テキスト内的意識主体の多重構造》になる。
・テキストの主体としての「私」
・語り主としての「私」
・登場人物(たち)の語りとしての「私」
◎テキスト内的意識主体の多重構造は、おそらくこの地上における「私という現象」においても、以下のようにアナロジックに観ることができる。
・「私」というペルソナの主体としての「私」
・「私」の表現主体として働く「私」
・「私」が表現されている(具体的に表出している)ものとしての「私」
◎ふつう「私は私だ」と思っている「主体」は、一枚岩ではないし、「私は私だ」という「私」も「ペルソナ」(仮面/人格)として地上的に顕現しているだけであるといえる。ユングは「自我」の深みにある「自己」を想定しているが、いってみればその「自己」がペルソナとして顕現しているのが、「私は私だ」という「私」であるといえる。
◎しかし、話はここで終わりではない。その「自己」と想定されているものもおそらくは多重構造的に働いているのではないかと思われる。この多重構造をテキスト内的意識主体における多重構造としてアナロジックに観てみるとこのようになるだろうか。
・「自己」の主体
・「自己」の語り手
・自我主体を語っている「私」である「自己」
◎こうみていくと、「自我」としての「私」の多重構造と「自己」としての「私」の多重構造があって、その中心が重なっていると観ることができる。自我主体を語っている「私」である「自己」=「私」というペルソナの主体としての「私」を中心にした多重構造である。「私」というペルソナ主体を中心とすれば5重構造。もしくは、肉体をともなって顕現している「私」という「自我」を中心点とすれば、3+3+1の7重構造。
◎パソコンの前に座ってキーボード入力またはマウス等で操作している「私」をイメージしてこのことを描いてみるとこうなるだろうか。
◎私が入力しているテキストは「私」ではないが、そのテキストにはそのエクリチュールの主体がいる。そして、そのテキストには「語り手」が(第三者的な位置を占めている場合もあるが)存在している。そしてその語り手が、そこに登場する人物や描写をそれらを主体とした語りとして語る。
◎パソコンの前に座ってキーボード入力またはマウス等で操作している「私」がいる。ペルソナとしての「私」である。そしてそこには、ペルソナ(仮面)を送り出している「自己」がいる。そしてその自己をいわば「語っている」語り手がいる。そしてその語り手の物語る高次のテキストである「自己」のエクリチュールの主体がいる、という多重構造の「自己」。
◎「私という詩作品」は、このように、地上に身体をもち、そのなかに自我をもった「私」を中心として、地上における多重構造と高次世界における多重構造を結び、重なりながら、メビウスの輪のようにつながっていると考えることができるのではないか。
◎ここで重要だと思われるのは、そうした「私という詩作品」の「根源」にあるものは、入沢康夫がいうように、まさに「歌うよりほか仕方ない」ように思える。どのような表現、説明も「便宜的な比喩」としてしか可能ではない。それは「外部」(これも「便宜的な比喩」でしかないのだが)にあって「私という詩作品」を照らし出している。しかし、その《詩のオリジン》であり《中心の炉》、《聖なるもの》にどこまで近づけるか。それをどれだけ「たしかに「在る」」として感得できるか。それが重要課題だといえる。もちろんそれは、おそらくどこまでいっても「幻想」でしかないのだけれど、それでも、「私」を語り出している、語り出そうとしているものに接近すべく、「私」を重層化してとらえようとすることは、そのままで「私」の「奥行き」を観るということでもあるだろうと思う。少なくとも、「私」を重層化してとらえようとする意識なしでは、「私」はだだの傀儡でいるしかないだろう。その傀儡がどんなに素晴らしい傀儡でも、それがどんなに素晴らしい使い手に使われているとしても、「自由」であることはできない。重要なのは、みずからが傀儡でありながら使い手でもあることを「自覚」のもとでおこなうことだろう。そしてできれば、それに習熟していくこと。
◇参考テキストからの引用
A)宮沢賢治『春と修羅』「序」より
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
B)入沢康夫「作品の廃墟へ/幻想的な作品についての妄想的な断想」(1970)(『続・入沢康夫詩集/現代詩文庫177』(思潮社)より)
詩作品の根源にあるもののことについては、それは語ることはできず、歌うよりほか仕方ない。あれについて、人々に倣って《彼方のもの》と呼び、《詩のオリジン》と呼び、《中心の炉》と呼び、《煮えたぎる坩堝》と呼び、《聖なるもの》と呼んでみても、それらはすべて便宜的な比喩であり、形容(それぞれに感覚的には適切だが)に過ぎない。
しかも、ここですでにひとつの疑念が浮かぶ。「あれ」は、ほんとうに、詩の根源にあるのだろうか。「詩」という語を「詩作品」の意味に解するとき、むしろ「あれ」は、その外部にあって、それを照らし、それに熱を与えているのではないか。もっとも、「根源的」と言い、「外部」と言っても、それもまた比喩に過ぎないのだが。
そして問題は次のごとくに設定される。
「あれ」が、なぜ、「言葉で書かれたもの」に関するのだろうか。どうやって、「あれ」が、「言葉で書かれたもの」の「根源」に座を占め、もしくはそれを「外部」から照らすのであろうか。いや、それよりも先ず、「あれ」はたしかに「在る」のか。
「在る」と思うこと自体、すでに一つの幻想の開幕であるかも知れない。だが、それがかりに幻想であるとしても、とりあえず維持せねばならぬ幻想である。しょせんは論証の次元の話ではなく、感覚あるいは信憑の次元の話なのだ。
(P.116)
C)同上
それにしても、一つの作品が未完に終わり、そして、しかもそれがわれわれをそのことゆえに魅するためには、そこに、「作者がそれを完結させようと最後まで欲したにもかかわらず」という信頼あるいは神話が、十全にうちたてられていなければならないだろう。そのとき、そこにはドラマが、いま一つの幻の物語が成立する。一作品の完結が作者の死によってはばまれる場合もあろうが、ここではそれをも含めて、作品の徹底的な追いつめが、おそらくは必然的に生んだ作品の破壊、完結性の喪失が問題なのである。
(・・・)
幻想作品における語りの変質については、語り手のうしろにいま一人の語り手がいることが、時として膜がうすくなって、はっきりと透けて見え、さらには、これら二人の語り手の関係がいつとはなしに逆転するといった場合も考えられる。
幻想的散文詩の、と言うか、ここではもはや「幻想的」という形容詞をはずしてもよいという気もするのだが、そのあり得べき一つの特質は、それが一つの宇宙論、一つの神話体系(と言っても既成のものではなく)を暗示(あるいは明示)しており、そのことから、その作品が自らのうちに閉鎖されておらず、世界全体とアナロジックな交感状態にあるのを、陰に陽に感じさせることであろう。一作品が作品として閉じているかどうかということと、今のことは、おそらく密接な関係にあると思われるが、しかも別のことである。
そして作品としての価値ということになれば、話はいちばんはじめに戻って、例の「中心の炉」からの照度、あるいは、同じことだが、「中心の炉」への接近度というとになるだろう。
(P.121−122)