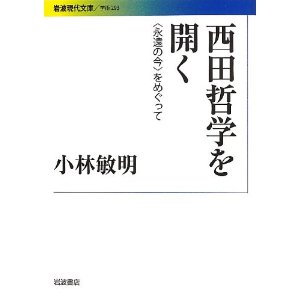

視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.5.28
◎esquisse20
《「今ここ」にいるということはどういうことなのか》
・「永遠の今」
・「今」を永遠にする
・「ここ」を「無限」にする
・「自己」および「他己」の「心身脱落」
・「永遠の今」へ、プレからポストへのプロセス
・「自由の哲学」と「永遠の今」へのプロセス
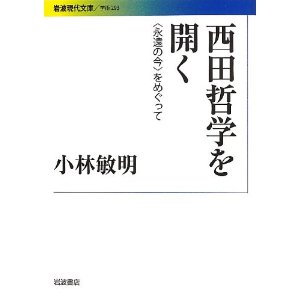 |
 |
|---|
《note20》
◎エスキス16で《永遠の今と世界劇場》についてノートしてみたが、ちょうど西田幾多郎の「永遠の今」のテーマについて、小林敏明『西田哲学を開く/<永遠の今>をめぐって』(岩波現代文庫)がでたので、そのテーマに関連してあらためて敷衍を試みたい。
◎「永遠の今」という言葉は、永く遠いという「永遠」という言葉に「今」という言葉を「の」でつなげているけれど、あらためて考えてみると、永遠は遙か彼方にあるようなイメージで、今というイメージはまさに今ここ、で矛盾している。重要なのは「今ここ」であって、「今ここ」に遙か彼方の永遠がなければならないということになる。
◎その遙か彼方の「永遠」を「奥行き」に重ねて考えてみると、「今ここ」にその「奥行き」が見出されないと「永遠の今」とはいえない。私たちが通常見出している世界(時空)の「今ここ」というと、身体をもった自分が「今この瞬間」に「ここ」にいるということでしかない。そこに永遠としての奥行きを観るためには、「今」を「永遠」に、「ここ」を「無限」にする必要がある。
◎「今」を永遠にするということはどういうことだろうか。そのときの「時間」は、時計が進んでいるような過去と未来に連続しているような「クロノス」的な時間ではなく、非連続の「カイロス」的な時間、つまり時計的な時間とは切りはなされた「神の時」とか「重大な転機」といったときにもつかわれる時間でなければならないだろう。クロノスの時間をいくら分割して短くしても「今」はでてこない。クロノスは数直線的にイメージできるが、そういう連続した時間ではないところに時間を見出さなければそこに「奥行き」は見えてこない。いってみれば、その水平的な数直線の時間に対して、垂直の時間。永遠=無の時間である。そしてその無の時間は、なにもないというのではなく、むしろ充溢した時間としてとらえなければならない。その充溢した無の時間からの射影として、「今」という連続してとらえられる時間が展開してくる(ようにみえる)ということでなければならない。
◎「ここ」を「無限」にするということはどういうことだろうか。そのとき、「ここ」から見える無限遠点が「ここ」ということでなければならない。宇宙の彼方まで進んだいちばん遠くにあるところが「ここ」でなければならない。光=私の視線がずっと進んで、宇宙の彼方に消え、それが私の背後から還ってくるということ。自分の頭の後ろを見ているというイメージ。それが可能になるためには、球面をイメージすればいいだろうか。今自分の位置しているところから球の表面をたどって、北極から南極を通って今の自分の地点までぐるりとまわって還ってくるということ。それを空間的な座標軸として理解してみる。つまり、そのとき「ここ」は三次元空間的な「ここ」ではない。「ここ」のすべてが「点」として虚空間へと反転しているのでなければならない。そうであってはじめて、あらゆる「ここ」は無限となることができる。
◎「今ここ」にいるということはどういうことだろうか。そこにいる「私」とはいったいだれだろうか。そのことについて、ヘルメス・J・シャンブ『“それ”は在る』という興味深い本がでている。いってみれば「悟り」をめぐる対話を模したものだが、「悟り」というよりも、まさに「永遠の今」、「今ここ」にいることについての体験について書かれてあるということがいえる。(とても読みやすく書かれているものの、その内容を理解しやすいというわけでは必ずしもないけれど、問題の要点を観るには格好のテキストとなっている)。
◎ちなみに、「永遠の今」、「今ここ」にいるということは、いってみればそれは道元のいう「自己」および「他己」の「心身脱落」ということでもあるように思う。そのときの体験の主客はすでに問題ではなくなっている。西田幾多郎のいう主客以前の(そして以後でもある)「純粋経験」的な意識だといえるだろうか。西田幾多郎はそれを言葉で哲学的に表現しようと生涯をかけて苦闘したということなのかもしれないとも思う。「私」も「あなた」も、「心」も「身体」も離れたところで、それを観ている意識だけがある。しかし、「心」も「身体」がなくなってしまっているというのではなく、同時に「心」も「身体」もまた存在している。「世界劇場」を観ながら、同時に「世界劇場」そのものが自分でもあるということだ。自分が「世界劇場」なのだから、それを観ている意識があるとしても、「世界劇場」が消えてしまうわけではない。
◎そして、「永遠の今」に至るまでにはさまざまなプロセスが存在していることは、可能な限り意識しておく必要がある。プレからポストへのプロセス。「子ども」から「子どものような」へ。禅の十牛図をイメージしてもいいだろうか。「心身脱落」するまえに、まず幻想として「心身」をもたなければならない。私は身体であるという幻想。私は心であるという幻想。思考というツールへの自己同一化などなど。そのために私たちはまず「私」というペルソナを身につけれてそれらとともに苦しみ、喜んだりを果てしなく繰り返す。そして、やがてなにがしかの機と気づきによってその自己同一化を離れ、「心身脱落」する。しかも、そのときには「自己」だけではなく「他己」もそうなっている。主と客は別のものではないからだ。私たちは、「無」から「有」へ、そして「無」の充溢へと反転ー反転する。永遠の今である非連続と刹那の今である連続との往還。それをひとことでいえば、やはり「遊」だろうか。「世界(劇場)」は「世界(劇場)」そのものを/で、遊び戯れている。
◎こうしたプロセスをシュタイナーの「自由の哲学」との関係で観てみるのもいいかもしれない。「自由の哲学」では、「思考」による一元論を示唆しているが、ここでいわれている「思考」は、たんなる「想念」や「考え」というのではなく、いってみれば「純粋思考」である。一元論であるということは、主客を超えたところで「思考」をとらえているということであり、その意味で、「純粋経験」的でもあり「直観」的でもある。その「思考/純粋思考」によって、認識の限界を超える可能性が検討されているが、そこで問題にされている「思考/純粋思考」についても、おそらくそこには実際的にいってその「思考/純粋思考」的なものが働く何段階かのプロセスを想定しておいたほうがいいかもしれない(「自由の哲学」にはそういうことは書かれていないけれど)。主客かそれとも主客を超えているかという二つの様態しかないということではないからだ。認識の限界を超えるためのペルソナは段階的であってそれぞれに応じた主客の様態や「思考/純粋思考」の様態があるというふうに考えてもいいかもしれない。「奥行き」についても、それに応じた姿で現れてくる。「劇場」はその様態に応じたかたちで「劇場」として顕現するわけである。
◎「自由の哲学」の最終章・第14章「個と類」のなかでシュタイナーは「類的なものから自分を自由にする程度如何が、共同体の内部にいる人間が自由な精神でいられるかどうかを決定する」と述べているが、その「自分を自由にする程度如何」というのが、その「劇場」を決め、「永遠の今」への道のなにがしかの(遙かな)道程を決めているということになるだろうか。もちろん、数限りないペルソナがそこで幻のように戯れているとしても、ほんらいは、すべては永遠であり無限である。ただ、それに気づいていないだけ。
◇参考テキストからの引用
《疑問符となること》
A)小林敏明『西田哲学を開く/<永遠の今>をめぐって』(岩波現代文庫/2013.5.16)
「永遠」はカイロスという「非連続」の瞬間において、文字どおり一瞬だけ顕現する。だからその「永遠」はアイオーンのような「永続」のことではない。それはいわゆるクロノス的時間を「切断」する。つまり西田の言い方でいえば「時を超越し時を否定」することにおいて初めて顔を見せるものなのだ。過去・現在・未来を内容としてもつクロノスとは、ある意味で連続する時間である。しかし、その合意承認された連続性はいつでも時間の惰性化をもたらしうる。ちょうどハイデッガーのとどまりweilenが立ちとどまりverweilenとなって、継ぎ目Fugeが愚行Unfugへと固定することがありうるように、ベルクソンや初期の西田はこうした惰性化した時間概念に「純粋持続」を対置させたが、後期の西田はその立場を放棄して、かわりにカイロス的瞬間による非連続を対置させたといってよいだろう。より正確にいうなら、アプリオリにそういう非連続をはらんだ連続としての時間概念である。非連続を欠く連続だけの時間が生きた時間でないように、連続なき非連続もまた、もはや時間ということができない。いずれにせよ、いわゆる「時間」はカイロスという「時」によって切断されるとき、「充実」にもたらされる。西田がエックハルトに読み取ったのも、そういうことであった。
(P.246-247)
B)道元『正法眼蔵』ー「現成公案」巻より
仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の心身および他己の心身をして脱落せしむるなり。
C)井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』(岩波書店/1989.7.25) *道元『正法眼蔵』の読解に関した箇所
「尽時」。刻々の時が、刻々に全時を尽くす(「十世隔法異成」)。時時無礙的に重々無尽の多層構造をうちに秘めた「現在」(「而今」)が、一瞬一瞬の有為転変を刻みながら遷流して、その度ごとに時の全体を包んで「永遠の今」(nunc aeternum)である。
D)ヘルメス・J・シャンブ『“それ”は在る』(ナチュラルスピリット/2013.5.17)
完全に<今ここ>に生きる時、そこにはいかなるものも存在し得ない。
なぜなら、完全なる<今ここ>には時間も空間も存在しないからである。
(・・・)
ただ、無限と永遠の<今>だけがあるのである。
そしてまた、<今ここ>においてのみ、
時間と空間の幻想が存在できる。
(・・・)
時間と空間は<在る>の中に、
すなわちあなたの中にあるのである。
あなたは無限であり、永遠である。
(・・・)
完全なる<今ここ>とは永久不滅であり、
その完全さの中においてのみ、全ての変化がまた可能なのだ。
(P.167-168)
E)ルドルフ・シュタイナー「自由の哲学」(イザラ書房)第14章「個と類」より。
以上に述べたような仕方で、類的なものから自分を自由にする程度如何が、共同体の内部にいる人間が自由な精神でいられるかどうかを決定する。どんな人も完全に類でもなければ、完全に個でもない。しかしどんな人も、多かれ少なかれ、動物的生活の類的なものからも、自分の上に君臨する権威の命令からも、自分の本質部分を自由にしていく。
しかしこのような仕方で自由を獲得することができない人は、自然有機体か精神有機体の一分肢になる。そして他の何かを模倣したり、他の誰かから命令 されたりして生きる。自分の直観に由来する行為だけが、真の意味で倫理的な価値を有している。遺伝的に社会道徳の本能を所持している人は、その本能を自分の直観の中に取り込むことによってそれを倫理的なものに変える。人間の一切の道徳的活動は個的な倫理的直観と、社会におけるその活用とから生じる。このことを次のように言い換えることもできよう。ーー人類の道徳生活は自由な人間個性の道徳的想像力が産み出したものの総計である、と。これが一元論の帰結である。
(P270)