

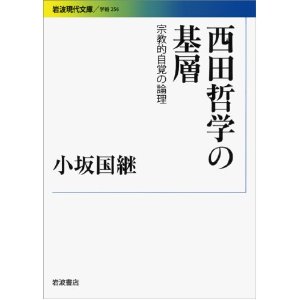

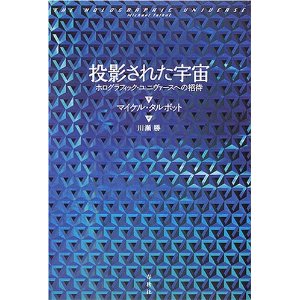

視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.25
◎esquisse16
《永遠の今と世界劇場》
・「今」について考える
・なぜ、今ここに私がいて、世界があるのか
・絶対の無なるが故に絶対の有である
・「今」という「点」において、「無」が「逆対応」的に展開している
・永遠の今
・「永遠」と重なる時間性を潜在的に含み込んでいる
「永劫回帰」=「絶対的な差異」の「反復」である「円環」の時間としての「第三の時間」
・デヴィッド・ボームは、目に見える「明在系」に対し、その背後に「暗在系」があることを示唆
・世界劇場論
舞台の<内>である「この世」にいるが同時に<外>にいる
 |
 |
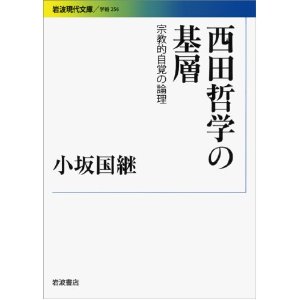 |
|---|---|---|
 |
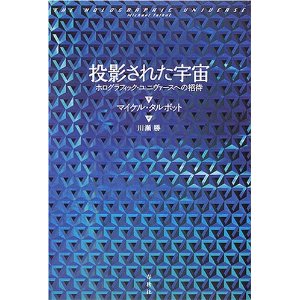 |
 |
《note16》
◎時間について考えていくと、かならずのように、「今しかない」という考えにいたる。「今しかない」のだから「過去」や「未来」にとらわれて生きるのはやめて今をポジティヴに生きよう、といったような人生論風の結論になることもあるだろうし、逆に「今しかない」のだから刹那的に生きるしかないと短絡的な発想になることもあるかもしれない。
◎そして、続いて考えつくのは、「今」というのはどんな「瞬間」なのだろうかということではないだろうか。ごくごく短い時間としての「瞬間」をイメージしたりもするが、その「刹那」を数直線上のような時間で理解しようとするのはすぐに限界になる。アキレスの亀のようなパラドックスに陥ることにもなる。
◎「今」について考えるということは、「ある」、「世界がある」、「自分がいる」ということについて考えるということもである。「今しかない」という考えの背景には、今自分がここにいるということや、今自分がここにいる世界があるということがあるからだ。ヴィトゲンシュタインも「世界がどのようになっているか、でなく、世界があるということ、これが謎である」と『論理哲学論考』のなかで述べている。「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか?」「なぜ「無」ではなく、「何かが存在する」のか」というのは、哲学の形而上学や神学や宗教哲学、また宇宙論などの領域でしばしば議論されていることである。「ある」ということ、つまり「存在」は限りなく神秘的なのだ。それをクローズアップさせたのはハイデッガーの「存在論」である。
◎西洋においては、ほとんどの場合「無」ということは避けられるが、東洋においては「無」という概念が多用される。東洋的世界観を背景に哲学的にそれを構築しようとしたのが西田幾多郎であるといえる。「絶対の無なるが故に絶対の有である」というのである。これはたんに言葉の遊びではない。「無」というのは「有」の根拠なのである。この世界が「ある」、この「私」が「いる」という「有」は、「無」故なのである。神は「絶対無」であり、その「絶対無」が「絶対の自己否定」を行い、「逆対応」的に自己自身に対するからこそ、この世界が「ある」、この「私」が「いる」ということになる。「絶対無」の「自覚的自己展開」としての「絶対矛盾的自己同一」である。従って、「私」もまた「神」のように、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」ということが自覚の基本として示唆される。
◎なぜ「無」である必要があるのかといえば、私はそのままでは私ではないからだ。そのままの私がそのままの汝という他者と対するというのでもない。世界の謎がそれでは解消されない。世界がなぜあるのかに対する答えは世界があるからだというトートロジーにしかならないし、時間の謎も迷宮入りになるしかない。アキレスの亀のようなパラドックスがでてきてしまうのも、この世界を「有」だけでとらえてしまっているからだといえる。世界は、無と有がその接点において裏返っている、または反転しているがゆえに存在しているといえる、というのがここでの基本的な視点である。「絶対無」としての「神」は、自己認識を行うために、自らの内に自らを照らし出そうとして、「絶対の自己否定」を行なった。その「逆対応」によって、この世界が存在することになった、というわけである。神も「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見」ているということになる。「絶対の他」であるから、「無」はその絶対の他としての「有」と「逆対応」的な関係をもつ。
◎時間についても、「今しかない」というのをその点から考えてみると、「今」という「点」において、「無」が「逆対応」的に展開しているとして理解することができる。仏教で言う「刹那滅」という概念もそのように理解することが可能である。「今」という「点」に、「無」の世界が反転して展開している。その「今」というのは、物理的にいう短い時間、一瞬というのではなく、「永遠の今」である。「非連続の連続」であるということもできる。「過去」と「未来」も、その「永遠の今」「非連続の連続」のなかに収斂するものとして理解することができる。前回、「時が自己の底に自己を抜けていく」ことが「円環」になることであり、「周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定としては、之に於て無数の自己自身を限定する円が限定せられると考えることができる」という西田幾多郎の論をご紹介したように、「周辺なくして至る所が中心となる円」である「絶対無」は、その自己を限定することによって「永遠の今」という「円」を描いているということができる。これは、すでに時間というよりは時空論としてイメージしたほうがいいかもしれない。
◎そのような「永遠の今」とでもいる「瞬間」と「永遠」についてのドゥルーズの観点を檜垣立哉『瞬間と永遠/ジル・ドゥルーズの時間論』が紹介し、論じているのが興味深い。ドゥルーズは、とくに『意味の論理学』のなかで、「クロノス」(現在的な時間)と「アイオーン」(永遠の時間)をめぐって、時間が「現実化」することに対抗する「反ー実現」の働き(永遠という不在の時間の働き)が、「潜在性」という存在領域の問題とともに描かれていくとともに、けっして円環を形成しない「永劫回帰」=「絶対的な差異」の「反復」である「円環」である時間としての「第三の時間」について示唆している。そのことで、「瞬間」を、直線的に伸びていく時間のイメージのなかでの時間性ではなく、垂直的な方向において、「永遠」と重なる時間性を潜在的に含み込んでいるとしてとらえることができる。その「瞬間」は、「卵」であり、「胚」であり、ドゥルーズ後期の用語でいえば「平滑空間」とむすびついた世界の力動性の「場所」なのである。「瞬間」という「永遠の今」は、「絶対無」という潜在性の「周辺なくして至る所が中心となる円」が自己限定することで「現実化(原働化)」されることでこの世界があり、そしてこの私がいる。
◎ちょっとニューエージっぽくなるが、量子力学のデヴィッド・ボームは「ホログラフィー宇宙理論」で、目に見える宇宙である「明在系」は、その背後にもうひとつ別の宇宙である「暗在系」があると論じている。そして、「暗在系」にはすべての物質、精神、時間、空間などが全体としてたたきこまれており、「精神もエネルギーである」としている。そして、神経心理学のカール・プリブラムは、「私たちの世界はすべて、時空を超越したレベルからの投影である」といっている。そのホログラフィック宇宙をまとまって紹介している、マイケル・タルボットの『投影された宇宙―ホログラフィック・ユニヴァースへの招待』(春秋社)があるが、こうした宇宙観も先の議論と近いところがあるのではないかと思われる。
◎さて、「世界は劇場である」という考え方がある。「Totus mundus agit histrionem.(世界中の人々は役者として生きている)」という古代ローマの詩人ペトロニウスの詩句から発想されてたものだが、セルバンテスの『ドン・キホーテ』、カルデロンの『人生は夢』、シェイクスピアの作品などででてきた考え方である。シェイクスピアの『お気に召すまま』には、「この世は舞台、男も女もみな役者だ(All the world's a stage/And all the men and women merely players)という一節がある。
◎この「世界劇場」の考え方をペシミスティックにとらえれば、世界は空しいという考え方や彼岸を求めるような宗教的発想にもなるけれど、それを積極的にとらえればこういうことになるだろうか。私は役者として、舞台の「内」である「この世」にいるが、同時に<外>にいる。舞台の「内」は、ほんらいの「私」の「外」である。しかし、私はみずからをこの舞台の「内」でしか顕現できない。私は、舞台の袖で、「アイオーン」(永遠の時間)から「クロノス」(現在的な時間)へと反転する。そしてまた、舞台から去るときは「クロノス」(現在的な時間)から「アイオーン」(永遠の時間)へと反転する。その「永劫回帰」=「絶対的な差異」の「反復」である「円環」のなかに、私でない私が「ある」。
◇参考テキストからの引用
A)西田幾多郎「場所的論理と宗教的世界観」(『自覚について』(岩波文庫)より)
神は絶対の自己否定として、逆対応的に自己自身に対し、自己自身の中に絶対的自己否定を含むものなるが故に、自己自身によってあるものであるのであり、絶対の無なるが故に絶対の有であるのである。(P.328)
B)小坂国継『西田哲学の基層』(岩波現代文庫)
現在においては過去と未来は同時存在的であり、また現在の一瞬のなかに無限の過去と無限の未来が収斂している。そして、かような現在が現在自身を限定するところに時間が生じ、過去と未来が生ずる。それだから、時間は過去・現在・未来を包容する「絶対現在」ないし、「永遠の今」の自己限定として考えられるのである。こうして時間は、その直線的限定に即して見れば「非連続の連続」であり、その円環的限定に即して見れば「永遠の今」である。(P.166)
C)檜垣立哉『瞬間と永遠/ジル・ドゥルーズの時間論』(岩波書店/2010.12.14)
こうした「時間」に対する「空間」の契機は、(…)もちろんたんなる幾何学的な均質性として捉えられるようなものではない。それは、むしろ「空間」のあり方を多次元的な構造へと変容させ、時間論のなかに織り込んでいくように描かれなければならない。
ドゥルーズ自身がこのことをはっきりと述べるのは、「クロノス」(現在的な時間)と「アイオーン」(永遠の時間)をめぐるさまざまな議論、あるいは後期の『シネマ』における「時間イマージュ」を中心とする映像の議論においてである。クロノスとアイオーンを論じ『意味の論理学』では、時間が「現実化」することに対抗する「反ー実現」の働きが、つまり「現在」が完全には実現することのない(永遠という不在の)時間でもあることが、「潜在性」という存在領域の問題とともに描かれていく。『シネマ』の文脈になると、こうした瞬間と永遠の交錯は、「結晶」や「層」のイマージュとして、「現在」のなかにみいだされる「鏡」の無限反射のようにとりだされる。それは「今」に「永遠」という契機が織り込まれたものなのである。そこでは、時間がたんに永遠というかたちで空間化されるのではない。むしろ、現在という生ける時間において、それを支える永遠の自然の時間が、現在とは異なる次元で含み込まれるものとして示されるのである。「瞬間」と「永遠」が、そこでは齟齬をきたしながら絡み合っている。
この二つの時間のあり方は、時間的というよりも、時空間的だというべきだろう。(P.4)
「瞬間」とは、それ自身としても、空間的な「点」である。それはまさに、流れていく持続が連続体であることにとって、その極限的な一契機を示すものである。そして、「永遠」とは、点が極端に狭まった時空の一面であることの、まったく逆面であるともいえる。「永遠」には流れの極限としての無限という事態が関与するからである。こうした流れの無限について、ドゥルーズは「第三の時間」の議論では「直線」という表現を利用するし、それは無限に伸びる線として、けっして円環を形成しない「永劫回帰」=「絶対的な差異」の「反復」のことであるとも述べられる。「円環」である時間は、「瞬間」である現在につねに回帰するだけのものである(ドゥルーズによれば、それは「同一性」を確保するものでしかない)。しかし、直線の「永劫回帰」は、無限の永遠として「絶対的な差異」を導き、つねに新しく繰り返される現在を再開させる。
こうした空間としての時間を想定したときに、瞬間がもつ多重的なイマージュが全面に現れてくる。瞬間は、それ自身が垂直的な方向において、永遠と重なる時間の果てを潜在的に含み込んでいる。あるいは、それを瞬間である自らの反復のなかにあわせもっている。無限の事象を含んでいるがゆえに、瞬間が獲得する深さとは、それ自身、現実化されることを拒絶する次元として示される。それは卵であり、胚であり、あるいはさらにドゥルーズ後期の用語である「平滑空間」とも結びついた世界の力動性の「場所」なのである。
そうした時間のあり方をもっともよく示すのは、バロック的な時間意識であるとおもわれる。同種の議論をドゥルーズに近い時代に探ってみても、西田幾多郎が述べた「永遠の今」、あるいはヴァルター・ベンヤミンが論じた「静止状態の弁証法」や歴史の「収縮」などがただちにおもい浮かぶ。それらは、ドゥルーズが論じている議論と深く結びついているようにおもわれる。(P.5)
D)『〈在る〉ことの不思議』勁草書房 (1992/10)
変哲もなくみえるどの瞬間もが、無窮で充溢した瞬間場の生起。ロゴス(奇蹟の巡り逢い)・カイロス(創造・破壊)・アイオーン(無窮の時)なる<今ここ>が刻一刻、寄せ来る波のように回帰しつづけるという、眩暈するような位相が開けてこないだろうか。だから、「存在:無:同一」といういわば黒いネガフィルムを現像してみると、「永遠の瞬間」という明るいポジが映しだされてくるのではないか。言わぬというしかたでハイデッガーが言おうとしたことは、そのことではなかったろうか、もしそうであれば、そんな存在の風光やプロブレマティークをひとことで、存在神秘と概括してもゆるされよう。(P.183)
まず指摘できることは、世界劇場論は裏をかえせば、自己の正体(identity)を語っているということである。だから世界劇場論は、世界虚仮的ペシミズムのすすめでも、この世の悲喜劇から自分だけは免責されようとする自己逃亡論でも、あるいは、厭離穢土欣求浄土式の説教方便(悔い改めと天上への招待)でもなく(…)、積極的な自己究明論として解読されなければならないということである。
舞台の外部や背後世界に実体的に分離して別在しているのではない。自己抹消と引き換えに役柄をえがきだす当体(Sujet)として、現にまぎれもなく舞台の<内>にいあわせている。役柄を体現する声や身振りや表情の裏づけとなって、つねに舞台にあがっている。ただ、その登場のしかたのあまりの透明さ(直接性)のために、ソレとして距離をとって表象することも限定することもできないだけである。舞台に内在しているのに、舞台の露頭面からは永遠に脱漏すること。それが、自己(無人・実存)の存立形式である。自己は、この世(世界劇場)の<内>にいながら同時に<外>にいる。<内にいるのに外にいる>という、自己のこの奇妙な存立形式を、フッサールにならって「内在の超越」とよぼう。むろん、「隠れるというしかたでしか現れない」という、存在一般の定式のヴァリエーション。新奇なことではない。(P.251-258)