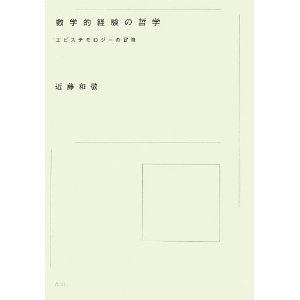
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.17
◎esquisse12
《概念創造・変革としての数学的経験/解と問題との往還・プロセス》
・「奥行き」を経験するための対象のない思考としての純粋な「概念」の創造世界としての数学
・「概念」を立てることは世界創造であり世界変革である
・新たな「概念」が導入されると、その分節化、差異化によって「世界」は新たな位相(フェーズ)に入る
・「概念」はモナドのように世界全体を相照らす関係性のなかに置かれ、そこで遊戯する
・生きた概念は私たちの経験の縮約である
・真理は過程としての真理であり、その過程を経験するのが数学的経験である
・解と問題(問い)との往還・プロセスを促進する懐疑と自然
・「奥行き」という神秘文字を読み取るために
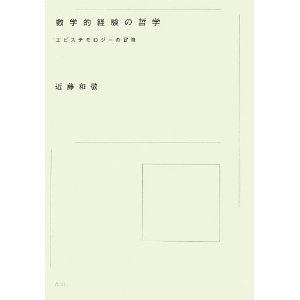 |
|---|
◇note12
◎数学はいってみれば、純粋な「概念」の創造世界である。概念は表象の一種であって、表象の領域で生きている。そして表象世界に差異をもたらす。数学における概念は、明確な形式と内容をもった表象であり、その意味で「純粋」といえる。しかも、視覚的な表象を必要としない「対象のない思考」による純粋経験である。
◎対象がないということは、「視覚の奥行きへ向かう」ときに、わたしたちの五感である視覚にとらわれてはいないということでもある。逆に言えば、「奥行き」に行く経験は、通常の視覚を超えた経験でもあるということになる。
◎概念を立てるということは、「世界」を創造するということである。または「世界」を変化させること。ことばをかえていえば、混沌の世界を分節化するということ。それまでは「天」も「地」もなかった混沌が分節化され「天」と「地」の世界が現れる。「1」という「世界」があり、そこに「2」が加わったとき、「1」だけの世界は明らかに大きく変化する。または「1」でさえなかった世界に「1」が導入されるとそこに「1」という世界が現出する。自然数だけの世界と整数の世界を比べると、そこには明確な「差異」が生まれてくる。「複素数」という概念が創造されることで、数学的世界は飛躍的に虚の世界にまで広がる。
◎概念は、単に言葉で名づけることではなく、その概念を必要とした「生きられた生存の過程を綜合することで、その過程に差異をもたらすものである」。もちろん、恣意的な概念を立てることは可能だけれど、少なくとも数学的な形式・体系における概念はそういうわけにはいかない。そこで生み出された概念は、その世界を創造・変革しながら確かな位置を獲得することになる。ある意味で、その概念はまるでモナドのようにその世界全体を相照らし出しあう関係性を持つことになる。その関係性のなかの「規則」に従ってさまざまな「振る舞い」が生まれる。ある意味で、ルールに基づいてゲーム行為〔遊戯)をするような感じだろうか。
◎そのように、「概念」をつくること、その「概念」を導入することは世界創造であり世界変革でもある。だから、その「概念」を自分のなかに位置づけることができないと、その新たな世界に入っていくことはできない。そして、いちどその「概念」が導入されると、世界はそれ以前とは変化を余儀なくされる。後戻りはできない。そこに「差異」のプロセスが生まれるからだ。世界はそこで分節しなおされ、概念同士の新たな関係性の照らしあいのなかで、新たな位相(フェーズ)に入ることになる。
◎もちろん、数学的な概念でなくとも、生きた概念というのは、私たちがここにいる経験を「縮約」したものだといえる。そして、その概念が立てられることになるにあたっては、それを必要とするプロセスがある。ある意味で、立てられた概念は「解」だということもできるが、重要なのはその「解」を要求することになった「問い」である。「問題」のない「解」は存在しない。「問題」を立てるのはその経験の「主体」である。「解」はそこに「ある」のではなく、「問い」が立てられそれが解かれる過程を通じて、「解」に「なる」のだということができる。その意味でも、「真理」というのは「過程としての真理」としてとらえていく必要があるだろう。それを「数学的経験」であるということもできる。この「経験」は、数学だけではなく、「対象のない思考」による純粋経験の領域におけるものでもある。
◎そのように「解」と「問題(問い)」は「差異」を含みながら往還していきながら(ある意味で、「解」と「問題(問い)」の対話ということでもある)、世界を創造・構築・変革していくのだが、その往還(螺旋運動もしくは捻れの運動のような)にエネルギーを供給し続けるのは、「解」に対する「懐疑」であり(「懐疑」によって新たな「問い」が生まれる)、さらにいえば、生命や物質やあえていえば魂の領域をも含んだ「自然」なのだといえる。その「自然」が、狭義の形式や体系(システム)からさまざまな偏差、さまざまな文脈を供給し続けるわけである。
◎私たちが今ここに生きているという経験を「縮約」することで「概念」が生まれ、その「概念」を使って「世界」が創造・変革されていくが、そのためには、絶えず「奥行き」へ向かう過程に身をおくことが必要となる。しかし、その「奥行き」なるものが「解」に規定されてしまいスタティックなものになってしまうと、「奥行き」は「奥行き」であることを止めてしまう。つまりは、対象のないはずのものが具体的な表象を伴った対象に固定されてしまうことになる。記号は記号の「奥行き」を失って単なる図になってしまう。まるで、四大が単なる物質になってしまって解放されない状態になるようなものだ。「見」と「観」との違いもそこにあるといえるのかもしれない。ある意味で「観」というのは、神秘学的にいえば「神秘文字の解読」のようなものかもしれない。たとえそこに書かれてあるとしても、それを読めなければそこに「奥行き」である意味を理解することはできないわけである。
◇参考テキストからの引用
近藤和敬『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』青土社 (2013/3/23)
A)概念をたてることは、それがなんであれ、世界を生み出すことであり、世界を作りかえることである。概念はたんなる言葉ではない。なぜなら概念は、生きられた経験を綜合するものだからである。概念はかならず生存の過程のなかにその意味の充足をみる。概念がたてられるというのは、その概念をたてることを要求した生きられた生存の過程を綜合することで、その過程に差異をもたらすものである。概念がたてられることによって、生存の過程はあらたなフェーズに入り込むのであり、それはほとんど不可逆な過程である。(P.26)
B)むしろ過程としての真理という主題において探求されるべきなのは、「解」としての真理を逃れる残りの部分、すなわち「問題」としての真理なのではないか。この理解は同時に、「解」としてとらえられた真理の不充分さを批判する可能性を開く。たんに「真である」という述語として理解された真理は、この「解」としての真理に属することになるだろう。「解」としての真理が、「ある」ものではなく、過程をとおして「なる」ものであるならば、そして真理の「なる」の過程全体をよりよく理解することが、真理のよりよい理解に結びつくのであるならば、「解」としての真理は、その過程全体のなかの最後のごく一部に場所を保持するにすぎないものとして理解されなければならないのではないか。
それでもやはりこの「概念」という音調においては、「解」に到る真理しか思考を開始することしかできない。(…)それゆえこの音調においては、過程としての真理の第一のものとして、「解」に到る真理の過程が議論される。そこにおいて議論されるのが、すなわち「数学的経験」であり、「概念」と「振る舞い」の二重構造であった。「経験の縮約」として「概念」が措定され、その「概念」の自由な結合が、その「概念」の意味を本来的に規定していた「振る舞い」から独立に「問題」を形成する。(P.398-399)
C)ベルクソンが指摘するように、過程として事象を理解するためには、「問題」の次元が非常に重要な意味を持つことになる。というのも、結果としての「解」が現実として成立し続ける背後には、「問題」が過程として成立し続けることが不可欠だからである。この「問題」の次元において「主体」概念を理解するためには、「自同性」の中心としての自己意識から出発するべきではない。なぜなら、「問題」は問答、つまり問いかけとその応答の狭間において成立するものだからである。問答において開かれた「主体」は、「解」としての「主体」、すなわち自己意識的な閉じた「主体」がもつさまざまな特徴を反転させたままに保持する。すなわち、「自同性」による充分な規定の反転としての「未規定性」。そして「自同性」による自己との「一致」の反転としての「不一致」あるいは「齟齬」。最後に、「自同性」による自己の中心性の反転としての「不一致」による「偏心性」。すなわち、「未規定性」と「不一致」によって無意識的に駆動される受動性である。これら三つの特徴が、過程としての「問題ー主体」を記述するための理念的なかたちをあたえてくれることになる。(P.401-402)
D)「懐疑の脈」は、「問題ー主体」を動機づける。「問題ー主体」は、「懐疑の脈」に由来する根本的な「未規定性」を解消させるために、「解」を生みだそうとする過程を駆動する。つまり、「懐疑の脈」は、「問題ー主体」にとって忘却すべき過去、外傷体験のようなものであり、それを完全に忘却するという目標が、まさに「問題ー主体」のエロス的欲望を引き起こしている。そして、」それが擬似的に完成するとき、最終的に「問題ー主体」さえもが忘却され、「解ー主体」のみが、つまり誤謬意識のみが全体を覆い尽くすかのようになる。しかし、実際にはそのような完成は擬似的なものにすぎない。(…)
「懐疑の脈」は、たしかに「問題ー主体」および「解ー主体」の生成を駆動しはするが、いかなる「問題ー主体」と「解ー主体」のカップリングによっても汲み尽くされえないどろこか、むしろ無傷のままに、無垢のままに、無学者となるものによってふたたび反駁される。「失礼ですが、ところで、結局のところ・・・」
したがって、「懐疑の脈」という変奏のためには、この「主体」という「地」の音調を捨て、さらに別の音調を求めなければならない。この「懐疑の脈」が走り抜ける此岸と彼岸の両方を浮かびあがらせることのできるあたらしい「地」となる概念が必要である。
それが「自然」であった。ここでの「自然」には、「有魂の自然」すなわち「生命」も「無魂の自然」すなわち「物質過程」も等しく含まれる。「懐疑の脈を充分に展開するためには、この概念を「地」とすることで、まったく異なる音調のもとで真理という主題を変奏しなければならない。(P.403-405)
G)真理という主題のすべての変奏を巻き込むことで、真理という過程のエロス的欲望の速度を遅らせ、反転逆流させ、その過程を駆動している忘却された「懐疑」を掘り起こしながら、それが「問題ー過程」として実現されるとともに覆い隠された「非の潜勢力」を想起させること。それが「解」となることでむしろ深められた「懐疑の脈」を注意深く、「無学者」らしく拾い上げることで、そこに「自然」のエレメントを回帰させること。「非の潜勢力」へと向かうことで、増大、蓄積、優越を最上とする大陸的記述を失調させながら、多島的な記述の展開を用意すること、あらゆる学知のなかに偏在し、あらゆる大陸的な記述において共立しているはずの「マイナーな学知」を励起しながら、みずからも「マイナーな学知」へと「なる」こと。こういった可能性こそが、「概念の哲学」において探求されなければならない。(P.407)
C)真理の生成という主題によって、真理の次元は解から問題へと移行した。すなわち、客体のセリーから極限における主体への漸近。そして主体のセリーからの再始動。すなわち、問題ー解の過程にあらわれる問題ー主体の記述という主題。客体とは概念であり、主体とは問いであり、そして自然とは不定さであるという帰結に向けて。(P.142)
E)真理の次元は、解から問題へと移行し、さらに問題から懐疑の脈へと移行した。すなわち主体のセリーから、記号系を介した宇宙のセリーへの越境的接続。自然という不定さを介した多島的な<再ー開>に向けて。(P.266)