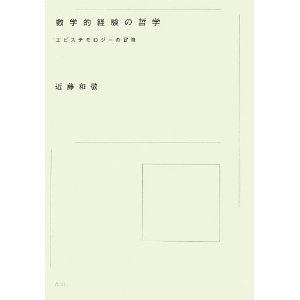
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.5
◎esquisse10
《私たちがどのような世界観のもとに生きているのかを意識し検討すること》
・自らの世界観を意識すること
・「神なしの知性」から
・認識論
・科学認識論としてのエピステモロジーにドゥルーズの「内在の哲学」を接続する
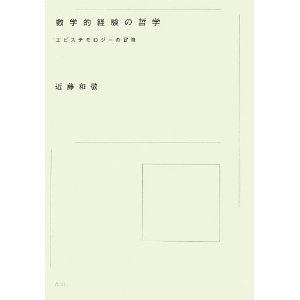 |
|---|
《note10》
◎私たちは何を見ているのか、また何を見ていないのか。それが今回のエスキスの問いかけである。なぜ前回ホワイトヘッドをとりあげてみたかというと、現代的な数学ー物理学的な視点を背景にした世界観を構築するとすれば、どのような世界観が可能かということを詳細に検討した哲学だからである。私たちはどのような世界に存在しているのか、またそう考えているのか、感じているのか。その問いかけがあってはじめて、そこからさまざまな問いかけを行うことができる。
◎マークシート方式の正しい答えを得るようなかたちでの世界観をもっているとすれば、その問いかけは意味をもたない。その場合、なんらかの自明の世界観を背景に「正しい答え」がそこには最初から準備されているからだ。そのプロセスは問題とされないし、問題とされるとしても、正しいプロセスなるものふがそこには設定されているといえる。しかし、重要なのは、問いを持つことなのではないだろうか。「正しい答え」なるものを前提としない問題を設定すること。たとえ山の頂上はひとつだったとしても、山頂に至るコースはたくさんあるのかもしれないし、新たな道をつくりだす可能性だってある。あるいは、空から舞い降りる方法だってあるかもしれないし、トンネルを掘ることもできるかもしれないのだから。その意味でも、「正しい答え」がどの文脈で、なにを背景にして「正しい」とされているのかということを検討することが必要だろう。
◎「奥行き」を問題にするというのも、今自分が見ているもの、見ていると思っているものだけの世界観の持っている文脈や背景を検討することでもある。世界観そのものに懐疑の視線を向けることで、今見ているもの、見ていると思っているものそのものの文脈や背景は変化する。いままで正しい、あたりまえだと思っていたことも、必ずしもそうではなくなる。マークシートにこれまで正しいと思っていた答えを記入して安心していることはできない。解答するというシステムが変わってマークシート方式そのものの採用が取り消されるかもしれないし、そこに載せられていた問題ー答えの対応そのものが根本的に変わってくるかもしれない。ひょっとしたら今まである色のついた、または特殊な見え方をさせてしまうメガネをかけていることに気づかないままでいる世界観のもとにみんなが生きていて、そのメガネが取り外されることでまったく別の世界が見えてくることだってあるかもしれない。
◎しかし、なにもかもかわってしまうから何も根拠にすることができない・・・ということではない。絶対確実な客観的視点というような「神の視線」を求めることはできないにしても(ある意味で、これまで「信仰」がそれを担ってきたりもしたが、現代においては少なくとも宗教・宗派的な意味での「神」の存在を外して問うことは少なくとも必要なことだろう)、そこにはみずからの世界観がどのようなもので、そこにはどんな文脈や背景が前提にされているかを問うプロセスにみずからを置くことはできるのではないかと思う。
◎そういう意味で、今回は、「認識論」についてのエスキスとしてみたい。「認識論」というと、むずかしく感じてしまうかもしれないが、その問いはほんとうはだれもが避けることのできない問いにかかわる。要はこういう問いだ。どうしたら物事を正しく知ることができるのか、また間違った考え方をするのはなぜか。正しいかどうか、また間違っているかどうかを確かめるにはどうしたらいいか。絶対に知ることのできないことはあるのかどうか。またそれがあるとしたら、それはどのような領域のことか。
◎「奥行き」を認識するということは、「奥行き」をどのようにすれば「正しく」認識できるのか、また間違った「奥行き」の認識はどういうありようなのか。またほんとうに「奥行き」を認識できるのだろうか。認識するためにはどのような方法やプロセスが必要なのか。そうした視点が不可欠である。
◎認識論のことを、ドイツ語では「Erkenntnistheorie」、英語では「Epistemology」、フランス語では「Épistémologie」といい(英語とフランス語はそのギリシア語が語源で epistēmē + logos) 、存在論や形而上学と並ぶ哲学の最重な領域のひとつであるが、国によってその射程はかなり異なっているところがある。ちなみに、日本語の「認識論」はドイツ語からきていて、今回問題にしたいフランスでのエピステモロジーのことを、日本では「科学認識論」と訳したりもしている。
◎今回のエスキスは、近藤和敬の『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』から示唆を受けている。近藤和敬はフランス現代哲学及びジャン・カヴァイエスの研究を行っている。カヴァイエスはフランス・エピステモロジーの礎を築き、ナチス占領期にレジスタンスの闘士として銃殺された数理哲学者である。
◎エピステモロジーは「科学認識論」ということで、その基礎には数学的経験があるといえるが、近藤和敬はそれにドゥルーズの「内在の哲学」を接続し、人間の知性の根源をめぐる世界観を切り開こうとしている。
◎本書の最初にはこんな問いというか問題意識が置かれている。「わたしが知りたいのは、わたしたちはここに生きていったいなにをやっているのか、ということだ」。私たちの生きる理由や目的を宗教的な意味での「神」の存在を外して問うこと。「神なしの知性」。
◎しかし、かつてなんらかの形で平安を与えてくれていたはずの「神」なしの知性ゆえに、不安感や恐怖感に満たされてしかるべきであるにもかかわらず、多くの場合、私たちはみずからの知性の根拠を問うことなく日常生活を送っている。いわゆる「そういうものだ」ということで、みずからの依って立つ根拠のようなものを問わないことで生きている。ある人は、外的な権威によって、またある人はその外的な権威を内化することでみずからを権威として、あるいは自らの知性を鈍化させることで。そうでいないとしたら、やはり不安や恐怖からみずからを遠ざけるべく絶対的な拠り所を求める信仰によって。
◎認識論が必要とされるのは、たとえそこに絶対的な根拠を最終的に求めることができないとしても、まずはみずからの知性によって「正しく知ること」「間違っていることを知ること」「知り得ないことを知ること」といったことから出発することが現代人にはどうしても必要だからだ。
◎近藤和敬の問題意識は、現代数学の核心に見出される生命の創造的な力を通じて、生命だけではなく非生命までも包含する自然・宇宙の次元へと射程を向けている。まるで、前回ご紹介したホワイトヘッドのような問題意識のようだ。今回このテーマをとりあげたてみることにしらは、その流れからでもある。そこで、次回からその『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』をガイドとしながら「奥行き」をどのようにとらえるか、理解していくかということもふくめた、新たな世界観の可能性を探ってみたい。少なくともそのために必要な認識的態度がどのようなものであるのかを考えてみたいと思っている。
◇参考テキストからの引用
《近藤和敬『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』青土社 (2013/3/23) 》
A)わたしが知りたいのは、わたしたちはここに生きていったいなにをやっているのか、ということだ。(…)
神が存在すると安易に言えたならまだよかったのかもしれない。わたしたちが生きる理由もその目的もすべて神に帰することだできたからだ。そうすることができたなら、わたしたちがそうであるのはそうであるらだ、というトートロジーを受け入れることができたかもしれない。しかし、すくなくともわたしはそれでは納得できない。それならば問わなければならないだろう。わたしたちはなんの目的もなんの根拠もあたえられないま、この世界でなにをしているのか。わたしたちがなしてきたことは、いったいどのようなものとして理解することができるのか。(…)
「神なしの知性」というのは、一見すると当然というか、むしろ「知性」に「神」を結びつけるほうが時代錯誤的な印象を与えるかもしれない。しかし、本当にそうなのかはもうすこし考えてみてもよいのではないか。(…)「神ー知性」の体制において重要なのは、「神」そのものの存在云々ではなく、わたしたちの不安感、わたしたちが無底の深淵のうえをなんの支えもなしに歩いているという恐怖感を解消するという機能のほうだということになる。
そう考えてみると、わたしたちはこのような不安感や恐怖感といったものを、。真の意味では日常として生きていない。(…)「神なしの知性」といったものが違和感なく受け入れられている現代において、「神」がいないはずなのに、なぜわたしたちはそういったものを生み出してきたみずからの知性になんの不安も恐怖も感じていないのか。(P.11-15)
B) わたしたちがこれまでに知り馴染んできた「知性」が、「神ー知性」か「人間ー知性」でしかないのだとしたら、「神なしの知性」を理解するためには、あらたに用語の設定から始める必要があるだろう。なぜなら、まさに用語あるいは概念の設定こそが世界の創出であるからだが、より実際的には「神=人間=知性」の体制における「知性」という語の設定がほかのおおくの用語、たとえば「経験」、「客観」、「真理」、「本質」、「形式」、「主観」、「歴史」、「記憶」、「自然」などの用語の設定と結びつけられているがゆえに、この語ひとつを根本的に再規定するということは、ほかの用語もすべて最初から設定しなおすことを要求するからである。(…)しかし、それは既知の概念の根拠をあとづけによって明らかにすることが目的なのではなく、その根拠自体を問いにふし、それによってその概念の意味内容を振動させ、同じ名前の双子的概念を既知のものと共立させることにある。そこで実現される概念の関係は既知の概念の否定ではなく、共立あるいは深化であるほうがなお望ましい。なぜ共立が望ましいのか。それは共立へとなることは、生成あるいは変化という語のある別の可能性、すなわち否定なき生成というものを示唆するように思われるからである。共立へとなることは、既存のものと争い、打ち負かし、完全に否定したうえで、それにとってかわることではなく、既存のものと無関係な仕方でその傍らにあることでそれの安定性を浸食し、その意味作用を修正し、かつてあったのと同じようにもはやそれを受けとめることを不可能にしてしまうことである。(P.16-18)
C)わたしのここでの試みが、哲学史的にどう位置づけられるかということにかんしては、まずジル・ドゥルーズの名を呼び出すのが適切だと思う。わたしがここで「神なしの」と言うとき、フーコーとともに想起しているのはフリードリッヒ・ニーチェであり、「神なしの知性」が共立させられるべき「神=人間=知性」という設定に関して想起しているのは、イマヌエル・カントの超越論的観念論である。そして、ニーチェとは別に、そのようなカント的設定の傍らで、無目的なあるいは自律的な世界の創造的生成を最初に主張した一人がベルクソンだった。そして、このニーチェとベルクソンという対がもっともよく似合うのは、両者についてのモノグラフィーの著者としても高く評価されているドゥルーズである。このドゥルーズは、「人間知性」を擁護するいわゆる超越論的哲学全般を批判し、それに対して内在の哲学を確立することを目指したとされる。「神なしの知性」を実現可能にする諸々の用語の再設定とは、その意味で、この内在の哲学をドゥルーズとは異なる経路で検討しなおすものだということになるかもしれない。(P.18)