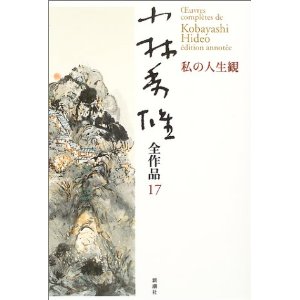

視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.8
◎esquisse-interlude2
《観ることと見ること》
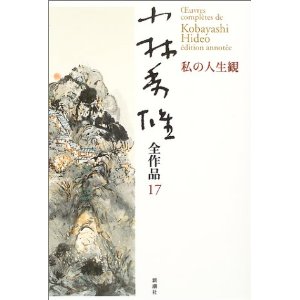 |
 |
|---|
◇interlude2-note
◎ちょっと閑話休題・・・というよりも最初の問いかけのポイントの再確認として少し軽めの間奏。
◎私たちはいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)をもっているといわれている。なかには共感覚といわれるような、感覚のあいだの敷居が低くなっているような人たちもいるようだし、実際のところ、5つの感覚はそれなりにだれでもある程度は浸透し合っているようにも思うが、一般にはそれぞれの感覚はかなり独立しているものとして理解されている。そして、それらの感覚はその有り様は別として、能力差のようなものはあるにしても、ある種の特別な状態にないかぎり、ある程度だれでも持っているものとして理解されている。そしてそれらの標準能力とされている基準に基づいて、さまざまな機械など(電気製品など)も製作されている。
◎しかし、それらの五感があるということは、それぞれの五感という、いってみれば「窓」の奥に到ることができるかどうかとは、そのままでは無関係なところがある。むしろ、なまじそれらの「窓」があることに安心して、その「窓」が鉄格子になって、私たちを檻のなかに閉じ込めているというとらえ方も可能である。つまり、私たちに自由であるというふうに思い込ませて、その窓の向こう側の存在を忘れさせてしまうということである。
◎五感の例ではないが、別の例でいうながら、私たちは自由にものごとを考えていると思っていても、ただ心に浮かぶあれこれを感情処理しているだけであることは思いのほか多い。最近、「考えないこと」の重要性が示唆された本などもでているのは、別に、ほんとうの意味で考えないでいいといっているわけではもちろんないと思う。ちゃんと思考を働かせることができないで、考えることと妄想することを取り違えているくらいならば、そういう勘違いした人には「妄想しないように!」という意味で「考えない練習」をオススメしているのだろう。
◎そういう意味で、なまじ自分がちゃんと観ているか聴くことができていると思い込んでしまっているくらいならば、「みざる・いわざる・きかざる」を内化した自覚的ありようとして、今の自分の五感に大きな疑いをもつ機会はもっておいたほうがいいのではないかという気がする。そうすることで、今の自分の五感を「まるで子どものような仕方」で学び直すこともできるのだろうと思う。
◎さて、現代はかつての時代のような修業が成立し難くなっているのはたしかで、シュタイナーもそういう意味も込めて、現代人にとって適切な修行方法を「いかにして超感覚的世界の認識を得るか」に詳述しているわけだが、どこかに隠って修行することにくらべてある意味飛躍的に自己管理(セルフ・コントロール)が重要になってくる。つまり、教師は自分の内的なセルフにもとめざるをえないわけである。その意味でも、自分の思考や感情や意志、先の五感にいかに自覚的に向かうかということが欠かせない。
◎しかし、今の私たちのふつうの五感などを超えた世界など存在しない、という視点にたってしまえばなにもはじまらない。檻の中に入れられた動物が世界は檻の中だけだと思っているようなものだ。もちろん、檻の中などという世界は存在していない。檻の中(と本人は思っていないけれど)しか存在しないとしか思っていないからそこが檻になってしまう、という矛盾のなかにみずからが身を置いているということにすぎない。
◎シュタイナーも神秘学を学ぶ際の先入見について『神秘学概論』の最初の章「神秘学の性格」で次のように述べている。「感覚とその感覚に仕える悟性とが明示しうるものだけを「学」と見なす人にとって、本書の意味での「神秘学」は当然、科学たりえないだろうが、よく考えてみれば、その立場は根拠あるものではなく、個人的な感情に発する独断に従っているにすぎないことが分かる。」「感覚的に把握されうるものだけにを考察する態度に慣れてしまうと、この感覚の開示こそが本質的なのだと考えてしまう。そして人間の魂が、その際、まさに感覚の開示だけに向けられているという事実を意識できなくなる。/しかし、そういう魂の自己規制から脱け出して、研究対象を特定の領域に限定しなくなれば、この特別な場合以外のところにも、科学研究の可能性を見出すことができるようになる。」
◎その意味で、「奥行きへ」と向かうということは、まずは「奥行き」の存在があるということに向かって魂を開く必要がある。そして、観ることと見ることとの違いを理解することが前提となる。
◎古代ギリシアのアカデメイアで、幾何学、いわば数学が入門の前提とされていたということは、現代的にいうならば、見るのではなく観ることに向かって魂が開かれているかどうかということになるだろうか。たとえば、三角形ひとつとってみてもそれを抽象空間において認識することは、単純に見ることではありえない。1+1を計算することにしても、これは目の前にある具体的な林檎2個を見てそうだというのではなく、観ることによってしか理解することは本来できない。
◎小林秀雄の『私の人生観』のなかで、「私達が生きる為に、外物に対してどういう動作をとるかに順じて知覚は現れる」といっているように、「観る」ことも、真に生きるためにわたしたちが切実な仕方で認識しようと思わなければ、見ることを超えることはできないだろう。たとえ、観えているにもかかわらず、自分はそんなものは観てなどいないというマーヤのなかに自足するしかなくなる。実際、真に思考するということは、ある意味、「観る」ということでもあることなのだから、これまでのように眼の前にある林檎は「見る」ことにおいてはそのままふつうの林檎でも、「観る」ことにおいてはただの林檎ではなくなる。だから、禅者は言ったのだ。「悟りとは何か?」「眼の前の樹だ!」と。そして、芸術家はその「観る」世界を描こうとする。
◇参考テキストからの引用/小林秀雄『私の人生観』
A)観というのは見るという意味であるが、そこいらのものが、電車だとか犬ころだとか、そんなものがやたらに見えたところで仕方がない。極楽浄土が見えて来なければならない。無量寿経という御経に、十六観というものが説かれております。それによりますと極楽浄土というものは、空想するものではない。まざまざと観えて来るものだという。観るという事には順序があり、順序を踏んで観る修行を積めば当然観えて来るものだと説くのであります。(…)
禅宗というものが宋から這入って来て拡がった後は、禅観の観の方を略して、禅という様になったが、それ以前の日本の仏教では、寧ろ禅の方を略して観と言っていた、止観と言っていた様である。止という言葉に強い意味はないそうです。観をするために、心を静かにする、観をする為の心の準備なのであって、例えば、法華経の行者が山にこもる、都にいては心が散って雑念を生じ易いから山に行く、平たく言えばそれが止であります。
B)武蔵は、見るという事について、観見二つの見様があるという事を言っている。細川忠利の為に書いた覚書のなかに、目付之事というのがあって、立会の際、相手方に目を付ける場合、観の目強く、見の目弱く見るべし、と言っております。見の目とは、彼にいわせれば常の目、普通の目の働き方である。敵の動きがあゝだとかこうだとか分析的に知的に合点する目であるが、もう一つ相手の存在を全体的に直覚する目がある。「目の玉を動かさず、うらやかに見る」目がある。そういう目は、「敵合近づくも、いか程も遠く見る目だと言うのです。「意は目に付き、心は付かざるもの也」、常の目は見ようとするが、見ようとしない心にも目はあるのである。言わば心眼です。見ようとする意が目を曇らせる。だから見の目を弱く観の目を強くせよと言う。
C)知覚の拡大など不可能である、眼には見えるものしか見えはせぬ、と人は言うかもしれぬ。どんなに注意力を働かせてみても、知覚の世界に、何か新しいものを生み出す事は出来ない。初めから在ったものを明らかにするだけだ。常識はそう言います。(…)実際には、この不可能事を可能にしたとしか考えられぬ人間がいるのである。それが優れた芸術家達だ。彼等の努力によって、私達が享受する美的経験のうちには、重要な哲学的直覚がある筈である。そういう風にベルグソンは考えるのであります。(…)
知覚は認識を構成する一定の要素でもないし、恰も写真でも撮る様に外物が知覚でとたえられるものでもない。私達が生きる為に、外物に対してどういう動作をとるかに順じて知覚は現れるのである。