■武満徹『映像から音を削る 武満徹映画エッセイ集』清流出版 (高崎俊夫・編者 2010/9/2)
■『オリジナル・サウンドトラックによる 武満徹 映画音楽』(CD 7枚組2006/2/20)
■菊地成孔『ユングのサウンドトラック 菊地成孔の映画と映画音楽の本』イースト・プレス
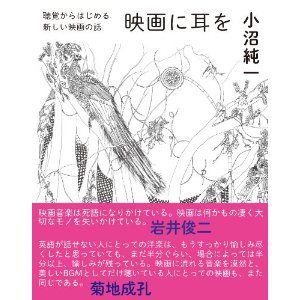 |
 |
|---|---|
 |
 |
小沼純一の『映画に耳を』というぼくがずっと読みたかったテーマの本がでていて大変面白い。もう、このテーマを聴いただけでぼくのなかにその世界がどんどん広がってくる。このなかには、約100本分の映画と音楽の話がつまっている。
映画音楽についてはじめて意識したのはいつのことだったのか。記憶に残っているのは、小学生の頃、映画音楽ではないだろうがテレビドラマのナレーションで「たけみつとおる・おんがく」という言葉と画面に入る「武満徹 音楽」という文字だったように思う。ストーリーよりもむしろ不思議な音色の音楽を「たけみつとおる」という人がつくっているのか・・・ということを思っただけで、「たけみつとおる」という人がどういう人なのかを知るのはずっと後のこと。
その後、実際に映画を観るようになり、映画音楽の作曲家のことも少しずつ知るようになったが、「映画音楽」ということについて少しなりとも考えてみるようになったのは、これも武満徹のエッセイを通じてだったと思う。ぼくは武満徹の大ファンで、その映画音楽の多くが収録されているサウンドトラックCDもぼくの宝物のひとつだ。
武満徹のつくる映画音楽は、少し前に刊行された武満徹の英学音楽エッセイ集のタイトルからもわかるように、「映像から音を削る」という考え方からつくられている。ある意味で、理想は、映画音楽とされるものがまったく入っていない映画なのである。意識してみれば、映像とかみ合おうが合うまいが挿入されている音楽が垂れ流しのように映像に浸っているような映画、映画に限らず各種映像が多いこと多いこと。これでは、耳は死んでしまうし、視覚のほうもほとんどゾンビ化してしまうのではないかという感もある。
ちなみに、小沼純一の『映画に耳を』にコメントを寄せている菊地成孔も、『ユングのサウンドトラック 菊地成孔の映画と映画音楽の本』という、ゴダールの作品を「音楽」と「恋」から読み解く酩酊しながら楽しめるような本をだしている。
さて、映画には最初から音楽がくっついていたわけではない。最初はいわゆるサイレント映画であり、それがやげて「トーキー映画」になる。1920年代のことで、一般公開されるようになったのは1927年のこと(そういえば、そのとき、シュタイナーはもう亡くなっている)。そのあたりのことについて『映画に耳を』から。
「見えるもの、と、音。
両者を切りはなし、また、くっつけること。
映画はそれをやってきら。トーキー以降である。
20世紀にほとんどなりかけている時期に、これまた映画とともに来るべき世紀に大きく貢献するレコードを使ってフィルムによる映画に音を同期させようとの試みがはじめておこなわれたという。商業的に広まるにはまだまだだった。残念ながら。当時パリでは発声映画(Chronoromegaphone)と呼んでいた。サウンドカメラなるものが発明され、短編映画でフィルムに音声がつけられるのは1920年代になって、アメリカ合衆国においてだ。そして登場人物が〝You ain't heard nothin' yet〟とセリフを発するーー「お楽しみはこれからだ」と高瀬鎮夫の字幕によって後生に残ることになるーーアラン・クロスランドの長編『ジャズ・シンガー』が一般公開されたのは1927年10月のこと。
トーキー映画は、サイレント映画に親しんできた少なからぬ人たちに、「映画は終わりだ」とため息をつかせるものだった。にもかかわらず、世界中でトーキーへの移行はごくあたりまえのことになる。撮影と録音を同時におこなうという苦労、映画と音とのシンクロの不具合がおもしろおかしく描かれているのをジーン・ケリー『雨に唄えば』(1952)に見ることができる。主人公たちのハッピーエンド、トーキー映画のストーリーの裏には、声が良くなくても、方言や訛りがあってもやっていけたサイレント時代の男優・女優の引退があったりもした。」(P.16-17)
そういえば、サイレントからトーキーへの移行期を背景にした白黒&サイレント映画の『アーティスト』が記憶に新しい。