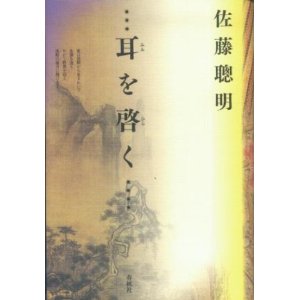
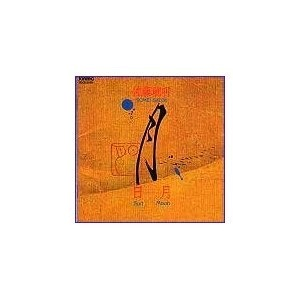



視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.5.19
◎esquisse19
《目を啓く・耳を啓く》
・みること、きくことにおいて
何重にも覆われているヴェールを剥がしていくこと
・傾聴するという行為と、微細に見つめるという行為は、同じ
・確かな一つの音の在処、確かな一つの光の在処へ
・『きく』ことは、『みる』こと以上に霊的な行為である
・耳を啓く
・西洋と東洋における対極的な音意識
・音の外化と音の内化
・この2つの方向性をむすぶこと
・新しい「聴覚的認識」へ
・荘子「地籟」「人籟」「天籟」
・形なきものにも形あるものにも、
また声なきものにも声あるものにも
その根底にある理念を見、聴くこと
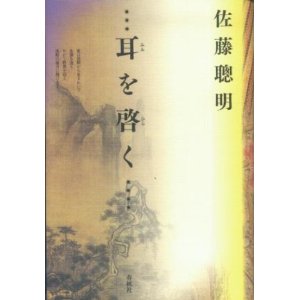 |
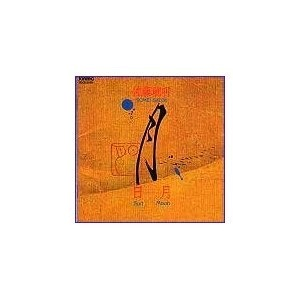 |
 |
|---|---|---|
 |
 |
《note19》
◎私たちは何を見ているのか、また聴いているのか。その問いを少し進めてみる。実際のところ、ただ見る、聞くというだけでは、たとえばそこに文字があってそれを見ることはできるが、読めない。読めたとしても意味がわからない。そういう状態とまったく変わらない。そして多くの場合、見えていない、聞こえていないということにさえ気づいていない。その状態からなんとかして脱する必要がある。ヴェールを何重にもかけられている状態から、そのヴェールを一枚一枚剥がしていく必要がある。
◎先日来、久々に佐藤聰明『耳を啓く』を読み、その音楽を聴いている。武満徹以降の日本の現代作曲家で、ぼくがもっとも敬愛しているひとの一人でもある。佐藤聰明は1981年に「沈黙の彼岸より」という武満徹についての文章がある。その最後にこんな箇所がある。「僕は、武満が、確かな一つの音の在処を求めて、遙かな旅を、ひたすら続けているのを識っている。そして、いつの日にか、生も死も、永遠も刹那も、極微も極大も、無始無終、陰陽、乾坤、その一切を呑みこんで、生り成り為りて鳴り響く、その玄の玄たる<一つの音>を、僕の眼の前に啓き示してくれるのを、待っているのだ」。「確かな一つの音の在処」、それこそが重要である。佐藤聰明は、アルバム『日・月』を出した際、杉浦康平との対話のなかで、「傾聴するという行為と、微細に見つめるという行為は、同じことではないかと僕は思います」と語っているが、その意味では、それは「確かな一つの光の在処」ということでもある。
◎聴くということはどういうことだろう。白川静は「神は『音なひ』によって『音づれ』る」といい、「『きく』ことは、『みる』こと以上に霊的な行為であった」と言っている。ものの本質を見極める力が「徳」でありそれが「みる」ことに関係し、神の声を聞くことができるということが「聖」であり「きく」ことに関係しているという。そして「聴」には、すでに「徳」が含まれている。「聴く」ためには、ものの本質を見極める力をもって神的なものをきく力を育てなければならない。その意味でも、なんでも聴けばいいということではなく、重要なのはその「質」の部分であるといえる。そして、聴くべきものを聴くためには、最初に述べたように何重にもかけられているヴェールを一枚一枚剥がしていく気の長い「行」が求められる。佐藤聰明の著書『耳を啓く』というタイトルが示しているように、「耳」を「啓く」必要があるのである。
◎「聴く」ことにおいて、音楽は重要な役割を担っているといえるのだが、西洋と東洋、とくに日本(邦楽)とではその方向性が逆転しているところがあるという。西洋音楽が楽器を「より技術的に容易に、より雑音(ノイズ)の少ない音色と安定した音程を」得るために進歩発展させてきたのに対して、邦楽器ではむしろその反対の方向に進み、一音のなかにあらゆる陰影をもたらそうとして複雑な音色と不安定な音程をだす方向に進み、「さわり」のようにむしろ積極的にノイズをつくりだしてきた。佐藤聰明は「邦楽器というものは奏する者が音と一体となり、耳を啓くためにのみ、永い年月をかけて今日の形に作りかえられた」という。
◎そのように、邦楽においては「音」を沈黙に近づけ、「その最も深いところで音楽を拒否」する方向に進んだのに対して、西洋音楽においては、ポリフォニーや対位法が発達し、アンサンブルやシンフォニックな方向性に展開してきた。ある意味で、邦楽は「音」を「内化」させたのに対して、洋楽では「音」を「外化」させる方向に進んだともいえるかもしれない。
◎それは、発声法にもあらわれていて、声明に象徴されるような発声法では声帯を狭くし喉を緊張させ臍下丹田に重心を置いて発声するのに対し、西洋音楽の歌唱法の典型でもあるベル・カント唱法では、声帯を開き上半身を共鳴させるように発声する。こうしたところにも、音の内化と音の外化という逆の方向が見られる。
◎ぼくはこの二つのまったく逆の方向性が見られるということのほうに、興味があったりする。ハズラト・イナーヤト・ハーンは「創造の本質とは一つのものを二極化すること」であるといっている。イナーヤト・ハーンの趣旨とは少し異なった視点ではあるけれど、音楽が洋の東西で二つのまったく逆の方向で展開したこともそうした「創造」なのだろうと思っている。西洋では音の純化、構造化に向かったが、東洋(邦楽)では音の複雑化、曖昧さのほうに向かった。一方では、神を外化し、一方では神を内化した。一方では、神を絶対化し、一方では神を八百万化した。おそらくその両者が「逆対応」的に「むすぶ」ことで、「創造」の「和」が可能になるのではないかと感じていたりもする。西洋においては存在論的に「有」がその根底にあり、逆に東洋においては「無」がその根底にあるが、そうした「有」と「無」もまさに「逆対応」的に「むすぶ」ということが今必要になっていることなのではないだろうか。
◎こうした音楽に関する多様性・両極性は、時間意識の多様性・両極性ということでもある。「もっとも根源的な時間意識」には、「原始共同体における反復的時間、古代ギリシャの抽象的で循環的な時間、ユダヤ=キリスト教における線分的な時間、そして最後に西洋近代文化における無限に抽象的な時間」という四種の時間意識があるという。そして、今私たちはさまざまな時間・空間意識のなかで音楽を聴取している。そうしたなかで、新しい「聴覚的認識」を獲得するために、世界と自己との間で「耳を啓く」必要があるのだといえる。
◎『荘子』の「斉物論篇」の「朝三暮四」の前に、「地籟(ちらい)」「人籟(じんらい)」「天籟(てんらい)」の話がある。「人籟」というのは「竹管」のような「人のふえ」、楽器が奏でる音楽であり、「地籟」とは「地のふえ」であり、大地が風とともに奏でる音楽であって、どちらも実際に聴くことができる。しかし、「天籟」は簡単には聴くことができないという。「夫(そ)れ万(よろず)の不同を吹きて、其れをして己(おのれ)よりせしむ。みな、其れ自ら取れるなり。」という。「全て音をたてるものはさまざまで同じではないが、それぞれに自分の音を出している。すべて自己自身の原理によって響きとなる」。つまり、「天籟」というのは、「天の音楽」とでもいえるものが実際に客観的にあるというのではなく、聴く人の「耳」が、いってみれば「啓」かれてこそはじめて鳴り響くことができる音のことだというのである。
◎「形なきものを見、声なきものの声を聴く」という。それは「形あるもののなかにその形の理念を見、声あるもののなかにその声の理念を聴く」ということでもある。一音のなかにも無限の豊かな音色を聴き出すことのできる耳、色彩豊かでダイナミックな音のなかにあもその根底にある無と無限を聴き出すことのできる耳。そんな耳を持ちたいと切に思う。
◇参考テキストからの引用
A)佐藤聰明『耳を啓く』(春秋社 2006/11/1)
邦楽器というものは奏する者が音と一体となり、耳を啓くためにのみ、永い年月をかけて今日の形に作りかえられたのである。誤解を恐れずに申せば、邦楽器とは、その最も深いところで音楽を拒否している楽器なのである。
(・・・)
西洋音楽の理念は、常に時間の流れる方向に進むものであり、総合と止揚による弁証法的展開によって表現される。この音楽には進歩発展という意識が常に影のごとくつきまとう。
しかし伝統音楽はある時代を境に時間軸上にたたずみ動かず、邦楽器においてはしばしば逆行する退化現象が見られる。
たとえば正倉院に残されている尺八は指孔が六孔ある。しかしいつの頃からか普化尺八のように演奏がより困難な五孔へと指孔の数が減少したのは何故だろうか、演奏の便利さを求めるならば、六孔より七孔、八孔へと楽器の改良を考えるのが常識であろう。
西欧の楽器の歴史は、まさにこの道を辿ってきたのであって、今日のオーケストラで使用されるほとんどの楽器に、そのような改良が絶えず加えられてきたのである。なぜならばより技術的に容易に、より雑音(ノイズ)の少ない音色と安定した音程を得んがためにである。
(・・・)
尺八であれ、異様に長い棹を持つ三絃にせよ、あるいは巨大としかいいようのない撥を用いる琵琶にしても、これらの楽器はある明確な意図のもとに演奏機能が退嬰させあっれている。
このような楽器のありようは、西欧楽器の持つ理念とは正反対の方向へと歩むものであり、楽器そのものに幽冥の蒼然が背負わされていると感じられる。
何故であろう。
ただ耳を啓くためにのみ意図されたからである。
(P.18-21)
声明を習いながらいだいた素朴な疑問がありました。
それは声明を唱するとき、なぜ喉を力ませるというか、詰めるというか、声帯を狭くして喉を緊張させて発声するのか、ということでした。
たとえば西洋音楽のよく知られた歌唱法に、イタリア・オペラなどに聴かれるベルカント唱法があります。ベルカント唱法でうたうときには、顔を上向きにし声帯を開いて上半身を共鳴させるようにうたいますが、声明を唱えるさいには顎を心持ち引き、背筋と首筋が垂直になるような姿勢で、喉を詰めて独特な発声をいたします。
喉を詰めるというのは正確な表現ではありませんが、いわば声帯を狭くして緊張させ、下腹部に、いわゆる丹田といわれる部分に重心を置いて発声するのです。
(・・・)
アジア的発声法というのには、その起源においてある 目的があったのではないかと想像します。
つまりこの発声法は幾度か申しましたように、非日常的な世界の属するものであり、人間の魂を目覚めさせ、神をわが心のうちに呼ぶためではなかったか、と思えるのです。
己の声のなかに自己を埋没させ、そして空白となり、そこに神を降ろすためのものではなかったのかと。もしくは神と合一するためのものではなかったかと、思えるのです。
(P.191-215)
B)白川静『文字逍遙』(平凡社ライブラリー 1994/04)
「みる」とは、その本質において、神の姿を見ることであり、「きく」とは、神の声を聞くことであった。そのように、ものの本質を見極める力を徳といい、また神の声を聞きうるものを聖という、徳は目に従い、聖は耳に従う字である。
(P.159)
神は直接に語ることはなく、神意は廟門の前におかれたその言に対して、夜更けたとき、ふしぎな「音なひ」として示される。闇の字形のなかに含まれる言が音に変じた形が闇である。神は姿をあらわすことはない。闇のなかにその姿はみえないが、音の気配がして、それと知られるのである。(…)神は「音なひ」によって「音づれ」るのである。音こそ、霊なるものの「訪れ」でった。しかもそれは、闇のなかでのことである。神の姿は肉眼に見えるものではない。ただその「音なひ」を聞くことだけができた。「きく」ことは「みる」こと以上に霊的な行為であった。
(P.171-172)
C)ハズラト・イナーヤト ハーン『音の神秘―生命は音楽を奏でる』(土取利行 訳/平河出版社 1998/05)
創造の本質とは一つのものを二極化することです。この二重の相は、この世のあらゆる二元論の原因になります。かたや積極的、かたや消極的。一方は表現し、他方は反応する。したがって、この二元的創造において精神と自然が相対します。まず最初の相に音があり、次の相に光がある。この自然の相、あるいはそれに反応する相においては、まず光だけが働きますが、創造の深部へと入って行くにつれ音が聴こえてきます。自然が精神と向かい合う中で最初に表現するもの、あるいは人が最初に反応するものは光です。そして次に人が反応し、より深く動かされるのが音なのです。
人間の体は精神の乗り物です。創造のありとあらゆる側面を体験する完璧な乗り物です。でもこれは、物や生き物としてこの世に形をなし、名をなす他のものが、どれも精神の表現に反応しないということではありません。実はどんな物でも、精神やその働きに反応しており、精神はあらゆる相の中で、さまざまな形や名をもつ森羅万象の中で活動しています。ルーミーの『精神のマナスウィー』を読むと、人の前では物質である地、水、火、空気が、神の前では生きたものになることが分かります。
(・・・)
つまるところ、音楽とは何なのでしょう。いわゆる音楽とは、耳に聴こえる音の調和のことですが、実は色の中にも、線の中にも、音楽はあるし、種々の草木が繁茂する森にも音楽はあります。そしてそこでは、草や木の共生の仕方にハーモニーがあります。より広く自然を観察すれば、自然はさらに人の魂に訴えかけてきます。どうしてでしょう。そこに音楽があるからです。より広い生命観をもてば、生命への理解が深まり、音楽がもっとよく聴こえるようになります。全宇宙に呼応する音楽が聴こえるようになるのです。でも心の開けた人は、森に出かけるまでもなく、雑踏の中にいても音楽をみいだせます。
(・・・)
神秘家の観点からすると、天上の音楽は、船乗りに目的地に近づいていることを教えてくれる港の燈台のようなものです。これはどんな音楽なのでしょうか。生命の本質に調和がなければ、生命は変化に富んだこの世での調和を作り出せなかったでしょう。そして人は、精神の中にないものを切望しなかったはずです。調和が欠けているように見えるこの世のすべてのものは、実は人間自身の視野の狭さのせいです。観察の地平がもっと広がれば、さらに生命のハーモニーを楽しむことができます。全宇宙の営みのハーモニーは、人間に生命の奥底で、完璧な音楽として集約されます。それゆえ天上の音楽とは、創造の根源である音楽、すべての創造の目的地に向かう旅の途上で聴こえる音楽なのです。そして、それは自分自身の生命の奥底に触れる音によって聴かれ、楽しまれるものなのです。
(P.31-32/35)
D)椎名亮輔『音楽的時間の変容』(現代思潮新社 2005/02)
さまざまな分化がある以上、音楽は唯一のものではなくそれぞれの音楽がそれぞれに固有に時間の知覚と意識をもっている。「世界を止めた」(カスタネダに基づく真木悠介の表現)後、人は新しい聴覚的認識に到達するためにこの「止まった」世界を注意深く聴く。したがってある意味で、「我聴く、ゆえに我あり」と言うこともできるだろう。しかし、この聴覚的コギト体験は、それが自律的超越性に安住せず、いやむしろそうできないがためにデカルト的なものではない。人が聴くものはつねにモナド的な「自己」の外側からやってくるものだ。しかしそれはまた同時に純粋に主観的なものでもない。すなわちこと時間と同じように、人は世界と自己との間で聴くのである。この認識は緊密に時間意識と結びついている。というよりも、少なくとも、音楽とその知覚の関係について、時間の問題圏の観点から追求してみようと思う。
音楽の多様性と同じほどに時間意識の多様性がある。もっとも根源的な時間意識を探求する中、四種の時間意識を参照することで、完全な物象化以前の時間が見出された。その四種の時間とは、原始共同体における反復的時間、古代ギリシャの抽象的で循環的な時間、ユダヤ=キリスト教における線分的な時間、そして最後に西洋近代文化における無限に抽象的な時間である。しかし、ここで見出された時間意識は、「汚染されたこと時間」の形ですでに部分的に物象化されていた。真木悠介は以上の四つの時間意識を四つの理想的なカテゴリー、すなわち実在しないものとして提示していたのだが、ことの時間、いやより正確には、こととものとの共生的時間は、定義上異種混交の混在した不純な形で現れる。この不純性がこととものとの差異を、換言すれば時間=持続と時間=空間との間の差異を知ることの可能にする。しかし、時間=持続は、それが知られるためにはあまりに純粋すぎるためにそのものとしては存在できない。つねにそれは、上述の不純性の中にのみ見出される差異の中に現出する。
木村敏によれば、こと時間には、音楽の非主観的(すなわちもちろんのことだが、非客観的でもある)聴取のなかで出会うことができるという。
(P.129-130)