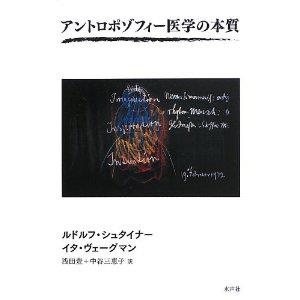
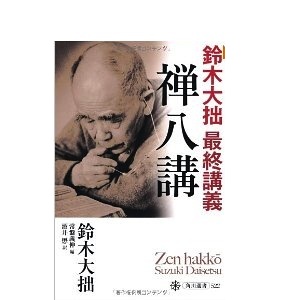
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.5.10
◎esquisse18
《自己認識からみた多次元的な奥行き認識》
・人間の基本的な構成要素「肉体」「エーテル体」「アストラル体」「自我」
・エーテル体を認識するためのイマジネーション認識
・アストラル体を認識するためのインスピレーション認識
・自我を認識するためのイントゥイション認識
・人間は動物に対しては90度、植物に対しては180度の位置関係にある
・自我と物質は逆転した360度の関係にあるのではないか
・イントゥイション認識としての自己認識
・「奥行き」の多次元的なあり方を認識すること
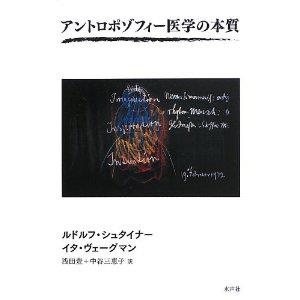 |
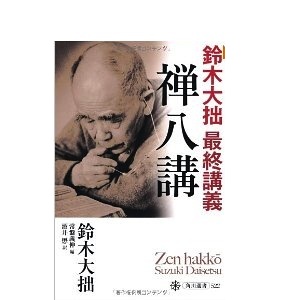 |
|---|
《note18》
◎人間の基本的な構成要素は、肉体、エーテル体、アストラル体、自我である。これらの構成要素の関係について理解することが、「自己認識」を通じた「奥行き」への視点を得るためには大変重要である。
◎現在の通常の人間の認識からいえば、肉体とされているものしか認識できない。エーテル体を認識するためには、イマジネーション認識、アストラル体を認識するためにはインスピレーション認識、自我を認識するためにはイントゥイション認識が必要となる。これらの認識を得るために必要な修行について書かれたのが、シュタイナーの『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』である。
◎図式的にいえば、この地上世界には、鉱物界、植物界、動物界、人間界が存在していて、鉱物界は物質的レベルだけがこの地上で顕現している。植物界は、物質体とエーテル体を有している。動物は、物質体、エーテル体に加えて、アストラル体を有している。そして、人間は物質体、エーテル体、アストラル体に加えて、自我を有している。
◎人間と植物、動物との関係についていえば、人間は、動物に対しては90度の位置にいて、植物に対しては180度の位置にある。植物、動物、人間はそれぞれ90度ずつ回転させたあり方となっている。
◎人間が、植物に対して180度の位置にあるというのは、植物を逆さまにしてとらえてみるとわかる。つまり、人間の上部は植物の根に相当し、人間の下部は植物の花に相当する。植物は生殖器官を花の部分に持っているが、人間は下部に持っている。
◎人間が動物に対して90度の位置にあるというのは、人間が直立しているのに対して、動物は4本の脚で水平の姿勢をとっていることからイメージできる。
◎以前、「反空間」としての「エーテル空間」についてノートを書いたことがあった。そこで示唆されていたのは、エーテル的な諸力が物質的なもののなかでどのように働いているかということだった。宇宙から地球に向かって働きかけている作用のことである。それは、人間の思考力にも関わっている。それを認識するためにイマジネーション認識が必要となる。
◎人間と動物にはその他に、アストラル体を有している。このアストラル的な作用というのは、エーテル空間のように、宇宙の周辺からの働きかけではない。アストラルが「星」を意味しているように、宇宙の周辺からではなく、その彼方に存在している「霊存在」としての「星」からの働きかけである。そして、先の植物と動物との関係からいえば、90度の関係になり、それを認識するためにはインスピレーション認識が必要となる。
◎さらにいえば、人間はそのほかに、自我を有している。人間の本来の「自我」の働きは、アストラル体のように、宇宙の彼方に存在する「霊存在」からの働きかけというのではなく、そうした霊的な働きかけを外から受けるのではなく、自身の内部において働くものとしてとらえなければならない。そして、植物との関係でいえば180度の関係、動物との関係でいえば、90度の関係となり、その認識のためにはイントゥイション認識が必要となる。
◎さて、シュタイナーの医学的な視点から、自我〔機構)に働きかける薬剤としては、鉱物的なものが用いられることが多い。あくまでもイメージでしかないのだけれど、人間と植物の関係が180度の位置にあるのに対して、人間と鉱物の関係は360度の関係、つまり逆転した360度の関係にあるのではないだろうか。そのように自我と鉱物との関係をとらえれば、なぜ人間がこの物質的な世界で自我を働かせなければならないのか、逆に言えば、自我形成のためにこの物質的な地上世界が必要なのかが垣間見える気がする。人間の構成要素からみれば、物質的なものと自我はほかのエーテル体、アストラル体にくらべて、もっとも遠い関係にあるにもかかわらず、それが逆転した関係で働いているという不思議。そして、そのためには、イントゥイション認識という、霊的合一といわれる認識が必要となる。
◎そのことから禅でいわれるような「花は紅 柳は緑」という認識様態のことが思い出された。これはある意味で、イントゥイション認識、霊的合一の境地である。その認識を「自己認識」ということもできるのだと思うのだが、その場合の「自己」はもちろん、主観ー客観の世界での「自己」ではない。その「自己」意識とは、意識の対象とは別のところに意識する主体があるようなそんな意識ではないからだ。花を前に花を見てそれを意識しているような意識ではなく、花そのものと別のものではない意識がある。しかもそれはその花と融合した未分化の意識ではなく花とは別のものではない「自己」意識として顕現している。対象知的な意識を超えた「自己」が有し得る意識にほかならないのだろう。
◎そうした意識においては、人間は宇宙の彼方の虚空間、反空間である「エーテル空間」からの反転した働きかけを180度逆転させたあり方で受けると同時に、その「彼方」に存在している「霊存在」である「星」の働きかけを90度の関係で受けながら、さらに逆転させた360度の関係にある物質世界の働きを自我に受け、それらの諸存在との霊的合一において「自己認識」を有しているといえる。「奥行き」を認識するというときには、そうした多次元的な視点をもつ必要があるのではないだろうか。
◇参考テキストからの引用
A)ルドルフ・シュタイナー+イタ・ヴェーグマン『アントロポゾフィー医学の本質』(水声社/2013.4.15)
エーテル界においては、人間の物質体の他に、エーテル体が知覚される。(・・・)
エーテル体の中で働いている諸力は、人間の地上での生涯の最初に、造形力および成長力として活動する。そして地上生活の過程の中で、この諸力の一部が造形および成長の活動から自由になり、思考力となるが、それは通常の意識にとっては影のような思考世界を作り出す諸力である。
人間の通常の思考力が、精妙化した造形力であり成長力であることを知るのは極めて重要である。人間の有機体の造形と成長の中で顕れるのは、ある霊的なものである。この霊的なものが、その後の生涯において霊的な思考力として現れる。(・・・)
イマジネーション的、霊的な観照においては、この可塑性のある(彫塑的な)力は、一方ではエーテル的・霊的なものとして、他方では思考の魂的内容として現れる。
(・・・)
イマジネーション認識によって人間の二番目の本性を知り、そして無の意識の中に霊的内容が満ちてくることによって三番目の本性を知ることになる。このように成立する認識を、アントロポゾフィーはインスピレーション認識と呼ぶ。(…)そしてインスピレーションによって参入できる世界を、アントロポゾフィーはアストラル界と呼んでいる。ここで叙述されているように、「エーテル界」について語るときは、それは宇宙から地球に向かう作用を意味している。しかし「アストラル界」について語るときは、インスピレーション意識によって観察できるように、宇宙の周辺からの作用から、特定の霊存在たちへと移行することになる。地上の物質が地球に由来する諸力の中に顕れるように、この霊存在たちは宇宙の周辺からの作用の中に顕れる。夜空を感覚によって眺め、星や星座について語るように、宇宙の遙か彼方から働きかける、具体的な霊存在たちについて語るのである。「アストラル界」という表現は、それに由来する。人間は三番目の本性をこのアストラル界の中に担っており、それはアストラル体である。
このアストラル体の中にも、地上の物質性が流れ込む必要がある。それによって、この物質性は物質的本性からさらに疎遠になる。人間は、植物界とエーテル体を共有しているように、動物界とアストラル体を共有している。
人間を動物界の上に持ち上げている本来の人間本性は、インスピレーションよりもさらに高次の認識方法によって認識される。アントロポゾフィーはそれをイントゥイションと呼ぶ。インスピレーションにおいては、霊的存在たちの世界が顕れる。イントゥイションにおいては、認識する人間とこの世界との関係がより近いものになる。人間は純粋に霊的なものを自分自身の内部で完全に意識化し、それによって霊的なものは身体性を通した体験とは何の関係もないということを、意識的な体験において直接経験する。(…)
こうして人間の四番目の構成要素を認めることができるが、それが本来の「自我」である。地球の物質性が「自我」の営みと本性に適合することによって、いかに物質本性からさらに疎遠になるかということが、再び分かるであろう。この物質性がここで取る本性は「自我機構」であり、この本性は地球物質の形式として、その地上的・物質的なあり方からはさしあたりもっとも疎遠である。
(P.22-27)
B)ルドルフ・シュタイナー『精神科学と医学』第5講(yucca訳/風のトポス・神秘学遊戯団)
植物的なものは、(…)人間の生体組織における働きとして存在しているものと、いわば対照をなしています。けれども植物そのものにおいても明白に三つの部分を区別することができます。この三つの部分の区別というのは、根として地中に向かって拡がっていくものを見る一方で、種、実、花のなかで伸びていくもの、上方へ向かうものを見るときに、とりわけ明確に皆さんの心に浮かんでくると思います。すでに外的な方向性と申しますか、そういうものにおいて、植物的なものと人間的なもののこのような違いをーーこの場合動物的なものは含めませんーー見ることができるのです。実際ここにおいてすでに、きわめて重要で意味深いものが存在しているのです。植物はその根を地中に沈め、その花を、すなわち生殖器官を上に伸ばしています。人間は宇宙のなかでのその姿勢に関してもこれと完全に反対になっています。つまり、人間はその頭部をいわば上に向かって根付かせ、その生殖器官を下方に向けていて、これは植物と全く逆です。したがって、皆さんが人間に関して、上に向かって根を張り、下に向かって花を、生殖器官を開花させている植物を、一つのイメージとして眼前に描くことも、あながち無意味なことではないのです。植物的なものは特殊な形式において、まさにこのように人間のなかに組み込まれているのです。さらに今度は人間と動物の違いを示す重要な指標となるのは、動物の場合、この(動物に)組み込まれた植物が、たいてい水平に横たわっていて、植物の方向と直角をなしているけれども、人間は、その宇宙のなかでの姿勢を、植物に対して完全に転回、と申しますか、百八十度転回させたのだということです。これは、そもそも人間と外界との関連を観察すれば見出すことのできる最も啓発的なことのひとつです。そして医学研究者の皆さんがこういうマクロコスモス的な事柄にもっと立ち入ってくだされば、たとえば細胞において作用している諸力についても、顕微鏡で観察するよりはもっと多くのことを見出せると思うのです。なぜなら、やはり細胞において作用している最も重要な諸力はーーその存在が植物であるか、動物であるか、人間であるかによって違いはありますがーー、マクロコスモス的なもののなかに観察され得るので、顕微鏡で観察しても実際のところほとんど得るところはないからです。人間の細胞をもっと良く研究できるのは、垂直に上昇したり下降したりするものと、釣り合いを保って横たわっているものとの間の相互作用を研究するときです。マクロコスモスにおいて研究するべきこういう諸力は、根本において、このマクロコスモス的な作用の写像に他なりません。
C)鈴木大拙『鈴木大拙 最終講義 禅八講』(角川選書522/平成25年4月25日)
「自己」とな何か。そして、どうしたらそれを掴めるか。いかにしたらそれを意識にのぼせることができるのか。「自己」意識はどうしたら達成できるのか。
注意すべきは、「自己」を古い概念と混同してはならないということである。魂は客観的に見出せるものと考えられていた、そして分析の結果、それが虚無であると分かった。「自己」は分析の対象にはならない。「自己」は知性によって扱われてはならない。それは知性がそこから出発する、ある根本的なものだからである。自己は思慮分別を条件づけるものだから、知性を超えている。「自己」を自己意識の意識にもたらすには、知性以上のものが要る。
通常の、ないしは相対的な意識においては、知覚があり、主観と客観があって、両者の間に関係が生じて、それを人は識知とか判断と解釈する。ところが、「自己」意識にあるのは識知以上の何かである。その知的な性格の外に行動意欲的要素があり、意思行為がある。「自己」意識とは意思なのである。
根本的意味において意思そのものであるから、「自己」意識は自らを意識する主観なるものを知らない。実は、「自己」が自らを意識するとき、自己意識が不可能なものであることを自ら知っている。こういう言い方は不条理で、まったくの自己撞着と響くかもしれない。しかし、「自己」が自らを意識するということは、本当は自己を意識しないことを意味する。なぜなら、「自己」意識とは、意識の対象とは別に意識する主体がある意識ではないからである。主観と客観とは、「自己」意識では一体である。「一体」というのも不正確で的外れである。ふつう「一」というとき、この「一」は「一」でないものと対立すると考えられている。肯定には常に否定が含意されている。「自己」では肯定と否定とが統合されていて、この統合は意思行為である。意思は知性に先立ち、知性は意思から出てくる。それゆえ、人が「自己」に到達できるのはーーすなわち「自己」がみずからを意識するようになるのは、思慮分別によるのではない。
「自己」は常にみずからを意識したがる。自己意識がないかぎり、「自己」は「自己」でない。しかし、この「自己」意識は、普通の意識の相対次元では起こりえない。なぜなら、普通の意識は合理化の結果であり、意識にのぼる自己がいかなるものであれ、それは抽象であって具体的な経験ではないからである。
(P.90-91)