
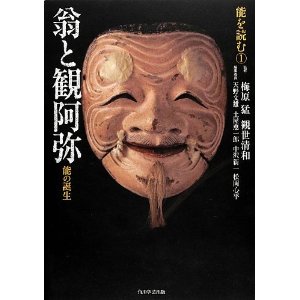
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.29
◎esquisse17
《「奥行き」を見ることと「離見の見」》
・私たちは演じているがそれに気づいていない
・「観る場所」であり「観る人」である「見所」
・仮面(ペルソナ)をつける「鏡の間」
・「あの世」と「この世」をむすぶ「橋掛り」
・「外=この世」からは見えない「無の暗闇」での視座としての「離見の見」
・私たちはシテ・ワキ・見所の多重の視座を生きる
・世界劇場に気づくこと気づかないこと
・明るい世界では闇の世界に気づきにくい
・アポロンとディオニュソスをともに生きる視座としての「離見の見」
 |
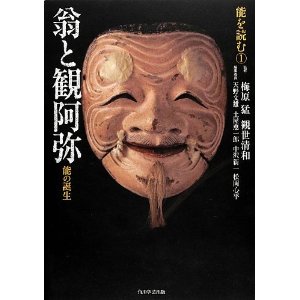 |
|---|
《note17》
◎私たちは演じている。そして、それに気づいていない。「奥行き」への探求は、演じていることに気づくことがまず重要な起点になる。前回、「世界劇場」をとりあげてみたが、今回は「能」における「離見の見」をガイドにして、今私たちが今いったいどこにいるのか、そしてそこで何を見ているのかについて考えてみたい。
◎ギリシア語の「劇場」の語源テアトロンは、「観る場所」を意味している。能では、観客及び観客席のことを「見所」という。では、見る場所である観客席、さらにいえば観る場所はどこで、そこから何を見ているといえるのだろうか。
◎能はもともと猿楽と呼ばれていたが、1881年(明治14年)能楽社 の設立を機に猿楽を能楽と改称された。猿の楽というわけで、物真似や滑稽芸などを演じていることからそう呼ばれていたのだろうが、もともとは古代、アジアの西域からシルクロード を経て伝来した「散楽(さんがく)」がルーツになっているという。大道芸的なその散楽について見てみるのもおもしろいが、テーマから外れるので省略。
◎能は、大きく現在能と夢幻能に分けられるが、現在能は生きている人間だけが登場し、夢幻能は現実世界の存在ではない死者、霊存在が主人公(シテ)として登場し、そこにワキとして旅の僧などが登場し、その夢にシテが現れるというような形をとっている。「あの世」から「この世」あるいは夢にでてきて、あの世に帰っていく。
◎現在の能舞台の原型ができたのは室町時代のことで、現在のスタイルで演じるようになったのは明治時代からだというが、基本は、能舞台空間において演者は「あの世」と「この世」を往還することに変わりはないだろう。シテは、「鏡の間」と呼ばれるところで面をつけ、「橋掛り」を通って方三間(ほうさんげん)の舞台に向かう。「橋掛り」が「あの世」と「この世」をむすんでいるのである。
◎舞台は観客席に向かって突き出ている。役者と観客が入れ子型〔凸凹〕になっていて、見所である私たちは、その能空間において「あの世」からやってくる存在の演技を見ているのだが、その私たちがいるのは、その異空間の外ではなく、見所である私たちは見所そのものとしてその異空間そのものにいるということができる。そして、ある意味では、ときに自らが霊存在のシテとなり、ときにシテに対するワキとなりながら、同時にそれを見ている見所という二重、三重の「観」を持ち得ることになるともいえる。
◎世阿弥は『花鏡』で、「離見(りけん)の見」という言葉を使っている。「離見」というのは、自分が演じている舞を、観客の目で自分を見るという「見所同見(けんじょどうけん)」という意味で使われているのだけれど、単に自分を客観視してお客様の気持ちになって演じなさいという理解だけでは面白くない。「内心ありと、よそに見えては悪かるべし……心をば、人に見ゆべからず」とあるように、「離見の見」は「外=この世」にではなく、「外=この世」からは見えない場所になければならない。それは、「無の暗闇〔「心行所滅之所」〕」であり、見所である私たちもそこに立ち会ってこその能、夢幻能なのではないかと思う。
◎観る人であると同時にその場所をともに「見所」というのはやはり興味深い。私たちは、観る場所そのものだということでもあるからだ。そして、「無の暗闇〔「心行所滅之所」〕」において「離見の見」となる。「見所」において、私たちは、「あの世」からやってきた「シテ」となり、それと対する「ワキ」となり、それを見ている「見所」という三重の視座そのものとなることができる。
◎「奥行き」を観るということは、観る場所そのものである自らの視座に気づくことからはじまる。「世界劇場」を、舞台の上の世界だけしかありえないと思っているとき、「奥行き」はまったく見えていない。見ようともしていない。自分が(「仮面」をつけて)どうやって舞台の上にやってきたのかも、舞台を観ている観客である自分の視線もまったく見えていない。照明のあたっている舞台の上だけが見えている。見えているものだけがはっきりと見えている。しかし、見えていないものにはまったく気づくことができない。そして、見えているもののなかの「奥」にあるかもしれない関係は闇のなかにあって見分けがつかない。
◎自分が「世界劇場」の役者として登場していると思っているときには、たとえその場所からは直接見えていないとしても、自分はなんらかのかたちでこの舞台にやってきたということに気づいている。台を観ている観客である自らの(離れたところからの)視線にも気づいている。そして、照明のあたっている舞台の「外」の見えない場所のことにも気づいている。
◎この能における「離見の見」は、この現実世界においても本来は成立しているはずである。しかし、通常、私たちはその「見」を持つことができないでいる。私たちは、自らが仮面を着けて「あの世」からやってきた「シテ」であり、それと知らず「シテ」に相対している「ワキ」であり、そしてそれを「見」ている視座そのものでもあることに気づくことができない。私たちは明るい照明のあたっている世界しか見えていない。橋掛りの向こうにあって仮面をつけていた「鏡の間」のことも、演じている方三間の舞台の向こうに「見」ている「見所」のことも。あまりに明るい世界からは闇の世界が見えないのだ。しかし、ときにその明るい世界を破ろうと闇の向こうからやってくるディオニュソス的存在がある。アポロンに対するディオニュソスといってもいいだろうか。そのアポロンとディオニュソスは相容れない。その相容れない絶対的「差異」を可能にするのも「離見の見」なのだろう。アポロンの視座とディオニュソスの視座。それは、個人においても、またそれを超えた世界構成そのものにおける生成と死滅の往還のダイナミズムともなっているといえるのだろう。
◇参考テキストからの引用
A)古東哲明『〈在る〉ことの不思議』勁草書房 (1992/10)
いうまでもなく、劇場の語源theatronは「観る場所」を意味する。では、どこからどこを観るのか。LOCUS(三次元空間)座標系でいえばむろん、観客席から舞台をみるのだが、問題は、上演現場に開かれる演劇空間(Spielraum)に投げ込まれた見所(観客)が、topos(意味空間)座標系上のどこからどこを観るのか、ということである。
能では、おおく他界人〔死者・精霊・神霊・物狂い〕が主人公であり、その生死往還が筋書きとなる。その筋書きが序・破・急の階(きざはし)〔能特有の上昇気流〕をたどって進行する演劇的意味空間のなかで、役者のみならず見所の在所(テアトロン)もまた、この世とあの世を流離う。表面は静態的にみえる能舞台の内部には、人間精神にゆるされたおそらく最大の振幅運動が起動するのである。最初はこの世からあの世を観ている視座が、この世でもあの世でもない宙吊り状態を経由し、あの世からこの世を観る視座【闇の劇場】へ幻容、そしてふたたびこの世にもどるというのが、その振幅運動の概略である。その幻容しさすらう眼の起動を物理的に保証するのが「橋懸り」である。
橋懸りは周知のように、あの世からこの世へと渡された架け橋。その橋懸りを辿って登場する役者(シテ)は、冥府の住人。その他界からの侵入者が、しばしのあいだ、此界および見所〔此岸人〕と接触し鬩ぎあう場所が、方三間の厳しい「舞台」である。それはいわば他界の出店(フロント)でありあるいは逆にこの世の前哨基地(フロント)。その他界にして此界なるバルドゥ的舞台をはさんで、役者と観客が入れ子型〔凸凹〕に精神の交流(インタープレイ)をはじめるとき、不可視のtoposとしての能演劇空間が開演する。(P.290-291)
B)同上
鏡の間に入った役者(シテ)は、面(オモテ)をかける。それは、自分を面の中に吸いつけてその裏側へ同化させるような心地だという。面の裏は荒削り、木肌剥きだしか黒色塗装である。そのすべてを削ぎ落としたような<裏側の闇>にまずは役者は自分を廻し、黒の裏世界に身を沈める。面にくりぬかれた眼穴は、視野狭窄がおきるほど狭隘である〔だから舞台には目付け柱がある〕。そのため、外の<面世界>をことさら覗こうとする遠心的な眼球運動を要求される、と同時にそのリアクションとして逆むきに、<裏世界(やみ)>へ屈折する求心的な眼差しの運動もひきおこされる。オモテ(此界)とウラ(他界)とへ、たがいに背反する視線運動が同時に発露し、内にして外、此岸にして彼岸という奇妙な交錯視界が、役者の視覚レベルで培養される。
そこにさらに、固くぶ厚い装束が被せられる。拘束服のようなそれは、日常の自由な所作を奪う。ふだんならば変哲もない一挙手一投足が、ことさら内面から汲みだされるような身体感覚をはぐくむ。外へ手足を踏みだしながら、それが同時に内面へ下り立つことになるような、身体沈潜の情感を喚起するのである。そしてそのことが、外界へ向かえばむかうほど内側(「内心の堺」)へと沈凛する、能演劇独特の「冷えた心」をつむぎだす。こうして役者(シテ)の他界人。死びとへの変身がおのずから醸熟していく。(P.291-292)
C)同上
そのような舞台空間に立つ演者にふさわしい視座(テアトロン)をさして、世阿彌は「離見の見」という。見所を、<こちら>他界の側(闇の劇場)へ誘い入れ吸い込むまなざしと解釈したい。
(・・・)
離見の見(内心・無心・秘めた心)はとうぜん、外(肉眼位相のこの世)にみえてはならない。「内心ありと、よそに見えては悪かるべし……心をば、人に見ゆべからず」(花鏡)。能ある鷹は爪を隠す式の安直な説教ではない。見えるような内心はまだ、<この世>にあるということだ。外は見えるが、外からは見えない場所〔まさに仮面の裏側〕が、離見の見(内心・無心・秘めた心)の境位だからだ。さらに敷衍すれば、離見の見は、見所に見てもらうもの(有=見)ではなく、見所をそこへ呼び込む場所(無=器)だということである)(遊楽習道)。あるいは、離見の見という、無の暗闇〔「心行所滅之所」〕(遊楽習道)に開演する「闇の劇場」へ見所をいざない、見所にもおなじ視座を装填させることに、能の本義があるということである。(P.293-296)
D)ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(下)(河出文庫)
曖昧なものでしかありえず、また判明であるだけにいっそう曖昧である判明なもの、および混雑したものでしかありえない、明晰でー混雑したもの。判明かつ曖昧であるというのは、《理念(イデア)》に固有な事態である。ということはまさに、《理念(イデア)》は、実在的ではあるがアクチュアルではなく、差異化=微分化してはいるが異化=分化してはいず、十分ではあるが完璧ではないということだ。<判明でー曖昧なもの>とは、本来は哲学的な酩酊・めまいであり、要するにディオニュソス的な《理念(イデア)》である。したがって、ライプニッツは海の岸辺であるいは水車の間近で、まさにぎりぎりのところでディオニュソスを逸していたのである。そしておそらく、ディオニュソスの諸《理念(イデア)》を思考するためには、<明晰でー混雑した>思索者アポロンが必要になるだろう。しかし、自然の光〔理性〕を回復するために、ディオニュソスとアポロンが統一されるなどということはあるわけがないのだ。ディオニュソスとアポロンはむしろ、哲学的な言語活動において、かつ諸能力の発散的な行使のために、つまり文体に関して齟齬をきたすもののために、二つの暗号化された言語を合成するのである。(P.125-126)
E)『能を読む①翁と観阿弥/能の誕生』(角川学芸出版/平成25年1月25日)
私が『翁と河勝』で詳しく論じたように、この摩多羅神は、ニーチェがギリシア悲劇の精神を形成すると述べたディオニュソスの神にはなはだよく似ているような気がする。ディオニュソスの祭は男女が性器を象った作りものを手に持ち、酔っぱらいながら町を練り歩くという酒と性と熱狂と滑稽の祭である。摩多羅神の祭にもこの酒・性・熱狂・滑稽という四つの特徴がすべて含まれるように思われる。とすると、摩多羅神は円仁の浄土教、あるいは最澄の天台宗の招来の時より以前、聖徳太子の時代に招来されたのかもしれない。またネストリウス派のキリスト教の崇拝者であったと思われる秦河勝によって密かに招来されあ神であるかもしれない。この翁とサルタヒコの格好をした「王の舞」の王、および摩多羅神との関係にはまだ解けない謎が多くあるが、翁、とくに三番叟がそのようなものと深く関係しているとすれば、「翁」には貴人と国家の安全を祈るという理性的、アポロン的精神とともに、この世の秩序を破壊するディオニュソス的精神が含まれていたというべきであろう。(P.300)