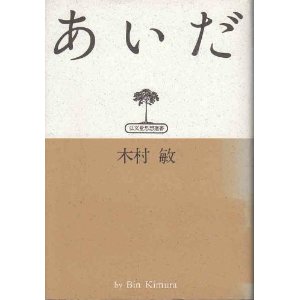


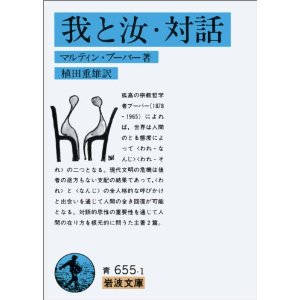

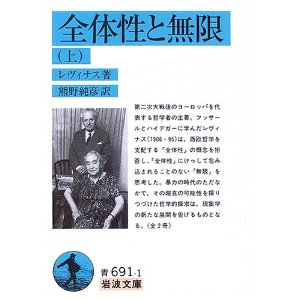
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.18
◎esquisse13
《我と汝・あいだ》
・木村敏の人間の心理的時間感覚と精神病理からの示唆
「祭りの前(アンテ・フェストゥム)」ー統合失調症的(分裂病的)
「祭りの後(ポスト・フェストゥム)」ー躁鬱病的
「祭りの最中(イントラ・フェストゥム)」ー癲癇的
・マルティン・ブーバーの二つの「根元語」:「我ー汝」「我ーそれ」
・交換不可能な絶対性をもった一回性のノエシスとしての「あいだ」
・自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る
・レヴィナス「主体の外へ」
・「私」と「あなた」が真に出会うのは「絶対的他性」の働きかけが受動的に応答しあう場所
(絶対的他性の視線の無限遠点とその交錯)
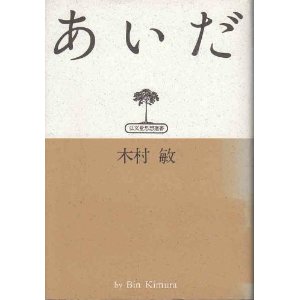 |
 |
 |
|---|---|---|
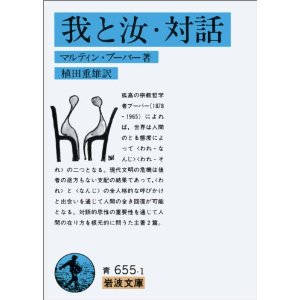 |
 |
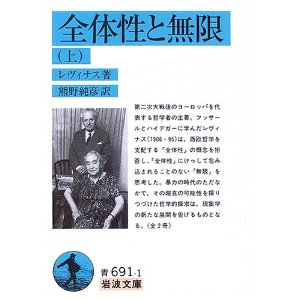 |
◇note13
◎エスキス8の補完として、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」ということの意味について、ちょっとややこしい感じにもなるのだけれど、「我ー汝」を考えるときには避けて通れないところなので、精神病理学者の木村敏の視点を使って少し。
◎木村敏は、人間の心理的時間感覚と精神病理を「祭りの前(アンテ・フェストゥム)」ー統合失調症的(分裂病的)、「祭りの後(ポスト・フェストゥム)」ー躁鬱病的、「祭りの最中(イントラ・フェストゥム)」ー癲癇的の三つに分類しているが、こうした時間感覚が形成されるにあたっては、幼児期の人間関係が深く影響している。つまり、自己と他者、我ー汝の関係としての「あいだ」である。
◎マルティン・ブーバーは、「我ー汝」、「我ーそれ」という「根元語」から人間が世界に対して取る態度が成立するとしたが、木村敏は我ー汝の「あいだ」の構造がそうした意識の二つのレヴェルに顕現していると見、それを根元であるとは見ない。「我ーそれ」の「それ」は相対的なノエマとしての「そこ」であり、それに対して「我ー汝」の「汝」の在りかとしての「ここ」「そこ」はノエマではなく交換不可能な絶対性をもった一回性のノエシスとしての「ここ」「そこ」である。重要なのは、「我ー汝」、「ここ」と「そこ」の「あいだ」の絶対性であり、さらにいえば「ここ」そのものもその「あいだ」に他ならないということである。つまり、「汝」は「絶対の他」「私の外にあるもの」として考えなければならず、しかもその「絶対の他」は「自己」でもある。そして、その「絶対の他」というのは、「もの」ではなく、ノエシス的な作用がそこに働いていると見なければならない。「あいだ」というのもふつう理解されるような空間的な場所ではなく、働きそのものとして理解されなければならない。そのことを西田幾多郎は「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」といったわけである。
◎ちなみに、「ノエマ」「ノエシス」というのは、フッサールの現象学において用いられる、ギリシャ語の見る=noeoに由来する言概念で、意識が対象を志向して対象を「ノエマ」として構成する作用のことを「ノエシス」と呼んでいるが、木村敏はそれを敷衍して、働きそのものである行為的な側面を「ノエシス」的な面、そのとき意識されているもののことを「ノエマ」的な面と呼んでいる。木村敏は、ある時点でノエシス・ノエマの対概念を、ラカンの影響も受けシニフィエ・シニフィアンの対概念に換えようとしたこともあったが、言語記号を認知するような主知主義的な立場に近い前者ではなく、あらためて自己自身を表現するという立場からノエシス・ノエマの対概念を使っている。言語以前、意識以前の「あいだ」の構造を見る必要があると考えているのだといえる。
◎「他者」というのは「他者と対峙する」とかいう言葉などで引き合いにだされることも多いが、面と向かった人を単に「他者」と見て、その人に対するコミュニケーションを円滑にするとかいう問題ではない。行動心理学的な側面をベースにコミュニケーション心理学を応用し自己実現をサポートするような開発セミナー的な手法も多いが、そこにはある意味では「我」も「汝」もいない。記号化された欲望同士、つまり「それ」と「それ」とが記号的な欲望のまわりを自己実現と称する「成功イメージ」のまわりをまわっているだけにすぎない。もちろん、世の中の多くはそれでまわっている。
◎ここでいう「我ー汝」は、「我」のなかに「絶対の他」を見ることで「我」は我自身となるのであり、そのことではじめて「絶対の他」である「汝」に対することが可能になるということである。そうした西田幾多郎の視点は、エマニュエル・レヴィナスの「他者」の視点に似てくる。レヴィナスは、他者との関係は相互的なものではないととらえている。「他者」は、私と「共にあること」(ハイデッガー)の中にも、「間主観性」(フッサール)の中にも現れない。可能なのは、相対する他者の背後から語り掛けてくる「絶対的他性」の言葉に応答できるだけだという。そして、主体の外へと超え出て行き、その外にある超越論的意識とでもいえるものを覚醒させる方向で思考を展開する。(とはいえ、ここらへんのレヴィナスの思考はなかなかつかみにくいのだけれど)
◎さて、私たちは、まず「他者」という「鏡」との「あいだ」で自己を形成する。しかも、ここに「私」がいて眼の前に「あなた」がいるというようなことからイメージされるようないってみれば牧歌的な関係性はほんらいありえない。私は「他者」によって「私」であると同時に、その「私」のなかに絶対的な他者性をもっている。「私は私であって私ではない」わけである。同じように、「あなた」もたんに「あなた」ではなく、私のなかの絶対的他者性を通じてしか、出会えない絶対的他者である。そしてそれらは、「ノエマ」的なあり方のなかである種固定化され、「それ」として相互に現れていることで、かろうじてコミュニケーション的なことが可能になっているだけであるにもかかわらず、私たちはそれをふつう複雑には考えない。ホラー映画風にいえば、私は鏡に映っていると思い込んでいる自分の顔=他者と話しているつもりでいながら、同じように「あなた」は鏡に映っている自分の顔=他者との間で、互いを「それ」と化しながら対話していると思っているわけである。
◎「私」と「あなた」が真に出会おうとするならば、互いに自らのなかに「絶対の他」を見、そこにノエシス的に働いている他者としての自己を見なければならない。つまり、私は私の絶対的他性の視線の無限遠点を見、あなたも同じくあなたの絶対的他性の視線の無限遠点を見、その交錯する「あいだ」において、いってみれば、互いが背中合わせになって相手のそうした視線の無限遠点と対話しなければならない。レヴィナス風にいえば、私とあなたは、互いに主体の外へと超え出て行き、背後にある「絶対的他性」の働きかけが受動的に応答しあう場所に生きなければならない。
◎おそらく、さまざまな精神病理が現れるのは、「それ」と「それ」同士の「もの」的な「あいだ」でエラーを起こした関係性だといえるのかもしれない。もちろん、多かれ少なかれ私たちは「我ー汝」関係の「あいだ」でそれなりの精神病理を抱えて生きているのだといえる。関係性の病なので、そうした病が表出した本人だけの病ではない。関係するあらゆる人と人の「あいだ」の病である。自分が自分でないように感じる、自分と相手との境目がわからなくなる、自分の中の世界だけのエクスタシー状態になってしまう、等等・・・。そうした精神病理は私たちにさまざまなことを示唆し続けてくれる。自己実現というときの「自己」にしても、本来はそれそのものが「絶対の他」でしかないのだから。
◇参考テキストからの引用
◎木村敏『あいだと時間の病理としての分裂病』(『分裂病と他者』筑摩書房 2007.8.10 所収)
A)分裂病は幼児期からの不幸な対人的出会いの歴史的帰結として、自己と他者の「あいだ」の場所において自己の自己性が成立困難になっている事態である、というのが私の一応到達した見解であった。
一方これと平行して、私は鬱病の基礎的事態を時間論的観点から考察し、これが「取り返しがつかない」という意味方向をおびた「未済のままの完了」という時間構造をもつことを述べたが、この時間的観点は、やがて鬱病者のポスト・フェストゥム(手遅れ、あとの祭)的時間構造に対する分裂病者のアンテ・フェストゥム(先走り、前夜祭)的時間構造という形で、分裂病者にも採り入れられることになった。
しかし、ここで問題となる「時間」は、従来の精神病理学において「時間体験の異常」という形で論じられた「時間」とは全く次元を異にするもの、いわば人間にとって「時間体験」なるものをそもそも可能にする根源的時間ともいうべきものがあって、それは一方で「自己」が自己として形成される以前の根源的な姿、つまりキルケゴールが「関係がそれ自身に関わる関係」と述べたような内的な関係もしくは内的な差異と同じ場所に属しているということが明らかになってきた。自己はもはや「自己同一性」の相においてではなく、「自己自身との内的差異」の相において理解すべきものと思われた。(P.35-36)
◎木村敏『あいだ』弘文堂 1988.11.20
B)自己と他者の「あいだ」(Zwischen))、我と汝の「関係」を、双方が互いに出会ってから初めて成立するコミュニケーションの交換としてでなく、そのようなコミュニケーションの可能性をそもそも基礎づけている領域として、つまり人間が人間として存在するという事実とともに最初から根源的に開かれてる領域として思索の中心に置いたのは、マルティン・ブーバーを始めとする対話哲学の人たちであった。(・・・)
ブーバーはその主著『我と汝』の冒頭に次のようなことを書いている。人間が世界に対してとる態度は、人間が語りうる根元語が二つであることに応じて二重である。根元語のうちのひとつは我ー汝であり、もうひとつは我ーそれである。《我それ自体というものは存在しない。存在するのは根元語・我ー汝における我と、根元語・我ーそれにおける我だけである。》人間は、それを対象物として知覚し、想像し、欲求し、感情の対象とし、思考する。《しかし我を語るとき人間は、何かを対象物として有したりはしていない。》彼はただ関係のなかに立つのみである。
しかし、我ー汝の関係と我ーそれの関係は、ブーバーの言うほど截然と分離しているのだろうか。むしろ、すべての「汝」は同時にいくらか「それ」であり、すべての「それ」は同時にいくらか「汝」である、というのがもっと本当らしくはないだろうか。(・・・)むしろブーバーが強調している「あいだ」の領域こそ、「汝」にいくらか「それ」性を与え「それ」にいくらか「汝」性を与えることによって、人間と世界との出会いを可能にし、人間が「関係のなかに立つ」ことを可能にするものではないのだろうか。ブーバーが言う「二つの根元語」とは、むしろ、「あいだ」の構造が意識のレヴェルにまで顕現した産物ではないのか。「根源語」がそこから派生してくる「根元」の、さらにその「根元」にこそ、われわれは言語以前、意識以前の「あいだ」の構造を見てとらなくてはならないのではなかろうか。(P.114-120)
C)ブーバーが「それ」と呼んだものの在りかは、相対的な「そこ」である。これに対してブーバーのいう「汝」の在りかは、架空の絶対的な「ここ」であり、想像上の絶対性を与えられた「そこ」である。
前者は「間接提示」によって構成されたノエマとしての「そこ」であり、これと相対的に対応する私の居場所としての「ここ」もノエマ的な「ここ」である。これに対して、後者の「ここ」と「そこ」はノエマではない。それはむしろ、ノエシス的作用そのものである。私のいまいる「ここ」が交換不可能な絶対性を持っているのは、それは私の経験全体の発生する場所だからであり、ノエシス作用の生じている場所だからである。私が一回きりの生を生きている場所だから、と言ってもいい。(・・・)
ヴァイツゼッカーの主体概念のことを思い出しておこう。「ここ」が絶対性を帯びているのは、それが主体の場所だからである。主体がその一回きりの生命を息ながら、生命の根拠との関わりを保っている場所だからである。しかもその主体は、ここで言えば「ここ」と「そこ」の出会いの原理である。主体の絶対性は、この出会いの原理の絶対性である。ということはつまり、「ここ」と「そこ」の「あいだ」の絶対性である。「そこ」が「ここ」固有の絶対性を分有することになるのは、「ここ」がもともと「あいだ」だったからにほかならない。生命の根拠との関わりの場所が、世界との出会いの場所だったからにほかならない。
「汝」の他者としての絶対性ということを強調したのは、西田幾多郎である。《私に対して汝と考えられるものは絶対と他と考えられるものでなければならない。物はなお我に於てあると考えることもできるが、汝は絶対に私から独立するもの、私の外にあるものでなければならない。》しかしこの「絶対の他」は私自身の自己と別のものではない。《自己が自己において自己を見ると考えられる時、自己が自己において絶対の他を見ると考えられるとともに、その絶対の他は即ち自己であるということを意味していなければならない》。(P.136-138)
D)「汝」は、私から「絶対の他」によって隔てられていることによって「汝」でありうる。しかしまさにそのことによって、私もまた「自己」としての私自身となる。この「絶対の他」は。そのまま「あいだ」と言い直してもよい。念を押すまでもないことだが、「私」と「汝」のほかに何か第三の実在として「絶対の他」というようなものが考えられるというのではない。「あいだ」といっても、それは決して二つのもののあいだの空間的な隔たりのことではない。(…)それは生命と直結した一種のノエシス的な作用であり、働きである。
西田とはまったく別の宗教的背景に立ち、西田とはまったく違ったーー多くの部分で互いに相容れないーー概念装置を用いながら、ある意味では非常に通底しあう問題を論じているのは、エマニュエル・レヴィナスである。レヴィナスの基本的な立場は、主体自己は単独者としてあくまでも他者から孤絶しており、ただ彼が面々相対する他者の背後から語り掛けてくる「絶対的他性」の言葉への応答を通じてのみ、他者と出会い、交流しあうことができるという認識である。彼はハイデッガーのいう「共にあること」の中にも、ましてフッサールの「間主観性」の中にも、真の他者の絶対的他性は見出されないという。彼らの見ている他者は、すべてを自己由来のものに見せてしまう「光」ーープラトン以来の西欧の認識論を支配している「光」ーーに照らし出された他者であり、同一者としての自己の内部から一歩も出ない他者であるに過ぎない。無限に他なるものとしての真の他者は、自己にとって絶対的な外部でなければならない。(・・・)
私と絶対的に異なるものとしての他者と出会わなければ、言い換えればすべてが自己の自己同一性のなかで演じられているならば、私はそれぞれの瞬間のあいだの他性を見出すこともできない。瞬間と瞬間とのあいだに他性が成立しなければ、時間も生成しない。私が時間をもち、歴史をもつことができるのは、他者の絶対的他性によってのみである。(・・・)
今の瞬間と次の瞬間とが、西田の好んで引く大燈国師の言葉に言うように《億劫分かれて須臾も離れず、尽日相対して刹那も対せず》という関係に成立つときにのみ、私が私であり汝が汝であるということが成り立つ。言い換えれば、次の一瞬が私にとって絶対的に未知であり不可知であることによって、未来という時間が可能になり、未来が未来として成立している限りにおいてのみ、私の目の前にいる他者は絶対的な他性を帯びることができるのである。(P.145)