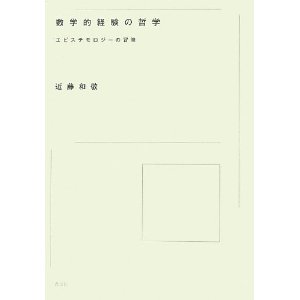
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.16
◎esquisse11
《なぜ数学があるのか〜数学的経験の可能性》
・「世界」の情報をコントロールするためには思考が不可欠である
・数学は問題と解を共有することができる形式・体系を有している
・数学は歴史に規定されているが、記号処理、概念処理における「過程としての真理」である
・見えないものを観るための数学と数学的経験
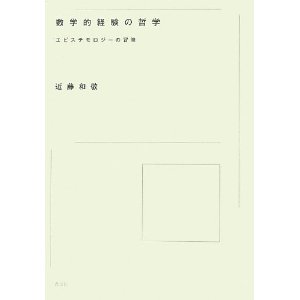 |
|---|
◇note11
◎前回の「エスキス10」のテーマは、「私たちがどのような世界観のもとに生きているのかを意識し検討すること」にむけてのものだったが、私たちは感覚(五感)によって「世界」からの情報を受け取っている。しかし、そうしたいった情報を受け取るだけでは「観る」ことにはならない。そのことをinterlude2でふれてみた。
◎世界からはさまざまな情報が届いていて、それをいわば「視覚情報」「聴覚情報」「嗅覚情報」「味覚情報」「触覚情報」等に分節して受け取ることでそれをもとに私たちは世界に対するあるイメージを形成しているのだけれど、それらのさまざまな情報を統合的にまとめあげるためには「考える」ということが不可欠である。そうしないと、データベースだけあってそれを使うOSやソフトウェアがない状態になってしまう。OS及びソフトウェアが感情中心や意志中心のものになる場合もあるけれど、それだと行き先が見えないでカオスのようになってしまうか、行く先だけあって自分がいまどこにいるかがわからなくなったりする。
◎そういう意味でいえば、考えることで、個々の情報を全体のなかに位置づけることが可能になる。見たことそのものではなく、見たことをさまざまな情報の全体のなかで判断することも可能になる。もちろん、その判断が正しいかそうでないかはわからないのだけれども、それなりの見取り図は描ける。わけのわからないことももちろんたくさんでてくるけれど、そのときでもわからないということがわかる。これはとても重要なことだ。わからないことさえわからなければどうすることもできない。問いのない答えを見つけるようなものだからだ。問うことができるということは、答えを見つけるための一歩手前だということもできるほどだ。
◎その意味でいえば、なぜ「数学」があるのか、なぜそれが必要なのかといえば、見取り図を描いて、その図を共有することができるからだ。そこには、とりあえず共有可能な問題とその問題が導き出すであろう解答の可能性がある。感情などに左右されない仕方で記号世界を共有することができる。
◎しなしながら、数学というと、いわゆる客観的で絶対に正しいというようなイメージもあるけれど、もちろんそんなことはない。数学はある意味で、思考を純粋にしたようなものだ。ある種の形式・体系に基づきながら、そこである程度厳密な仕方で記号的に真理かそうでないかを検討できる概念世界だといえるだろうか。つまり、基準をはっきりさせているので、それが正しいか間違っているかわかりやすいということ。だから、形式・体系のなかでは、つまりはその「世界」のなかでは厳密さをもっているが、その前提が拡がったり変わったりすると、その厳密さは失われてしまう。説明できないことになるか、範囲を限定した真理だということになる。もしくは、位置づけが変わってしまう。そのことを「歴史的に規定されている」ということもできる。
◎そうしたことをnote10に続いて、近藤和敬『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』をガイドとして考えてみたい。繰り返しになるが、この本では、数学が主役になっているのだけれど、あくまでもそれが格好の「見本」だからだ。「数学的経験」というのは、(かなり乱暴な言い方になってしまうけれど)ある種の形式・体系でとらえられた内容・概念を純粋思考する経験だということもできるだろうか。
◎なぜ格好の「見本」なのかといえば、数学の歴史は通常の生に関わる過程とくらべて形式・体系において変化しにくいために、通常私たちがきわめて人間的なものに束縛されやすいのとは対照的に、その「過程」が見やすいからである。たとえば、「0」という概念記号や「i」という虚数単位の記号などが生まれる前と後の数学の違いを考えてみてもわかる。同じ「1+1」でも、10進法と2進法とでは「解」は異なってしまう。それらは、歴史的文脈に依存していないとはいえないものの、記号処理、概念処理において、それぞれの体系以外の文脈を比較的考慮しないで扱うことができる。
◎私たちが常識的に見ている世界を「観る」(「観」の眼を得る)ためのひとつのツールとして、数学が有効である。私たちが通常の五感等ではとらえることのできない、純粋思考の世界をそこで展開させることが可能になる。古代ギリシアのアカデメイアにおいてその学園への入学資格が数学(幾何学)であったこともその意味から考えるとよくわかる。「見えないものを観る」必要があるのである。「見えないものを観る」ためには、五感を超える必要がある。
◇参考テキストからの引用
近藤和敬『数学的経験の哲学 エピステモロジーの冒険』青土社 (2013/3/23)
数学は、それがある意味で人間的なものに束縛されない極限的な記号的営みであるがゆえに、この脱文脈化の思考のために、不可能な思考へと向かう思考のために、特権的な「見本」となりうる。第一にそれは記号系を不可欠なものとするがゆえに、それが前提する「不定性」の介入を不可避なものとする。それはもちろん理想としては排除されるものとされるにもかかわらず、数学の問題を駆動する「懐疑の脈」においては、まさにその源泉として入り込むのであり、それが数学の歴史の多様性と豊かさを可能にしている。たとえばそれが関数という語であり、次元という語であり、数えるという語であるだろう。第二に、数学の営みは、厳密さという点を除けば、ほとんど自明な文脈をア・プリオリに指定しない。もちろん歴史的にそういった文脈が形成されるわけだが、その文脈も時に激しく揺さぶられ、疑われ、分岐し、多様化する。しかもその歴史的速度が、生物の進化現象などと比べて相対的に速いわりには、観察しやすい。第二の点にかかわるが、最後に、数学それ自体は、生の関心と直接のかかわりをもたない。それゆえ生という文脈を不可欠なものとして前提する必要がない。それゆえ、「否定神学」批判を経たあとの、ある種の構成主義的な実在論の立場にとって、数学は重要な「見本」を提示してくれると考えることができるのである。(P.392)