
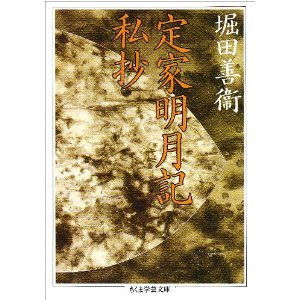
視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.5.7
◎esquisse-interlude4
《「ない」ことに気づくことからはじまる「奥行き」認識:「ウツ」と「ウツツ」の共鳴》
 |
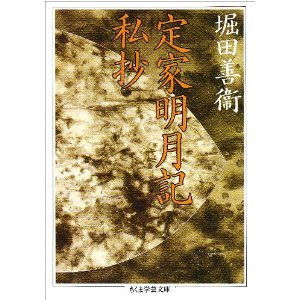 |
|---|
◇interlude4-note
◎「見わたせば 花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮」(新古今和歌集)という藤原定家の歌がある。西行の「秋の夕暮」を詠んだ 二首とともに「三夕(さんせき)の歌」といわれている有名な歌である。
◎この定家の歌は、「ない」ことを歌っている。「ない」ことで、むしろそこに「花」や「紅葉」が「ある」。「ウツ(空)」であるがゆえに、そこにより強く「ウツツ(現)」がクローズアップされてくる。しかも、「ウツ」か「ウツツ」かというような二元的な観点でなく、その関係性を共鳴させることができる。
◎佐伯 一麦の新刊『光の闇』を読んだ。聴覚、視覚、嗅覚、脚、声、記憶…と感覚の「欠損」をテーマとした短編の連作。ここにも「ない」ことが「ある」。聞こえないことが「ある」。見えないことが「ある」。脚のないことが「ある」。におわないことが「ある」。声のでないことがある。記憶のないことが「ある」。
◎ここでは、身体器官や身体感覚が「欠損」していることによって、それぞれの器官や感覚がむしろ照らし出されているのだけれど、それらは私たちの多くが通常有しているとされている、身体器官や身体感覚が「欠損」しているということが前提とされていて、そこから「ある」ということがクローズアップされている。しかも、「ない」か「ある」かではなく、それらが強く共鳴してくるなにかがある。
◎しかし、私たちが通常においては「ある」ことをまったく想定していない場合、それらが「欠損」しているいうことにさえ私たちは気付くことができない。なくてあたりまえ、どころか、「あるーない」という観念さえそこではもつことができない。つまり、問いをもつことさえできない。
◎もちろん、「ある」と「ない」のあいだには無限のグラデーションがあるように、「あるーない」と「あるーない」さえない認識状態とのあいだにも無限のグラデーションがあるだろう。「ある」にも、「たしかにある」から、「あるかもしれない」「可能性がある」「あるといっている人がいる」等々があるのだから。そして、同じテーマに対しても、ひとそれぞれで、確かに認識している人と、まったく認識できていない人とがいる。また、世界観によって、「あるーない」のあり方はまったく変わってくる。たとえば、唯物論的な世界観の場合と霊的世界観の場合では、「あるーない」の射程はまるで変わってくる。もちろん、そこまで対極的でない場合、たとえば関心のあるなしの場合でも、ずいぶんその射程が変わってくるのは明らかだろう。
◎私たちの認識問題としての「奥行き」のもっとも重要な問題は、ひょっとしたらそこにあるのかもしれない。「ある」けれどわからない、のと、「ある」わけはない、のとでは、まるでその問題のとらえ方が変わってくる。今は見え「ない」けれど、むしろその「ない」ことによって、「ある」ことをクローズアップさせることもできる。もちろん、ただただファンタジーのように「あるかもしれない」というのでは困る。少なくともこの「ファンタジー」には、虚の実があるはずだからである。今は見え「ない」のは、それが私のいる「実」からは「虚」となって見えなくされているということでなければならない。それであってはじめて、「奥行き」を「観る」ためのさまざまな道を検討することができる。「ない」ことを認識することで可能になる「ある」が逆対応的に照射あれてくる。「見わたせば 虚も奥行きもなかりけり」というときに、そこに虚の反転として現出してくるものを観なければならない。
◎今は、闇にいるとしても、みずからが闇にいるということを知ることで、その光の欠損が光に向かうためのアリアドネの糸となる。しかし、「光」のことをまったく知らない「闇」にいると、糸を辿るということを知らない。同じ「光の闇」でも、つまり、同じ地上生活を送っていても、それが「闇」かもしれないと気づけるか気づけないか。「奥行き」があることに気づくことができるかできないか。それが問題である。
◎私たちに「欠損」しているものは何だろうか。その「欠損」に気付くことが出発点となる。おそらく、その「気づき」さえ訪れれば、たとえ道は遠くとも、道はたしかに辿ることができる。しかし、欠損しているとさえ気付くことができない場合、道はない。私たちは問うことができてはじめて、進むことができるのだ。まさに、「僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る・・・この遠い道程のため」である。そのためには「ウツ」に気づき「ウツツ」とそれを共鳴させること。そこに「ワビ(侘び)」があり「サビ(寂)」があり、また「遊」を可能にする「風流」が世界の中にたしかに流れ込んできはしまいか。
《参考1/佐伯 一麦『光の闇』扶桑社 (2013/4/24)》
◎ずいぶん前から、欠損感覚を通して身体感覚を探ってみる小説を書いてみたいと思い続けていた。
身近に、聴覚や視覚をうしなった知人がいたこともある。また。自分自身がアスベスト禍に遭い、身体の内側に思いを寄せることが多くなったせいもあるかもしれない。
自分の身近に存在している、欠損感覚を抱えて生きている人たちへの聞き書きを進めているうちに、少しずつだが、その世界を察するようになり、それぞれに短編が相互に、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、記憶……が響き合って連関していることに気付かされることとなった。例えば、光が差さない闇という漢字が、門の外で音しか聞こえないという表意文字によって表されているというように。(P.210)
《参考2/松岡正剛の千夜千冊 0017夜》
堀田善衛『定家明月記私抄(正・続)』
http://1000ya.isis.ne.jp/0017.html
◎最初からリアルな「現」を立てて、それを空しく思っていくのでもなく、また最初からヴァーチャルな「空」を想定するのでもなく、いったんそのようなウツとウツツの関係そのものを「負」の状態にして、そのうえでその「負」の状態を強調するための景色を掲げる必要があった。そのうえで、ウツとウツツの両方の「関係」の相互性だけをいつまでも共鳴させるようにすることを試みたかったのである。
◎見渡せば花ももみぢもなかりけり浦のとまやの秋のゆふぐれ
ここは何もないように見える。見渡しても浜辺には何もない。浦の苫屋がひとつだけぽつんとあるような、寂しい秋の夕暮の光景である。
しかし定家は、その何もない寂しい光景を「花も紅葉もなかりけり」と詠んだ。実際にはそこに花があるわけでもないし、紅葉があるわけではないのだから「花も紅葉もなかりけり」というのは当然のだが、日本の歌にとっては、またその歌を見る者にとっては、言葉としての「花」や文字としての「紅葉」がそこに出るだけで、それは花や紅葉の色さえ見えることなのである。++++
定家はその花や紅葉の鮮やかな色と形を、言葉として文字としてヴァーチャルにつかって、一瞬にして浜辺に日本の歌の歴史の総体を咲かせ、そしてその直後に、たちまちそれらの色や形を、いやそれだけではなく花や紅葉にまつわる記憶の光景をさえたちまち消し去ってみせ、リアルな浦の苫屋の光景に戻してみせたのだ。残ったのは秋の夕暮だけ、そこには定家自身も消えている。それだけではなかった。そうすることで、何がリアルか何がヴァーチャルかは、少なくとも心の中では相対化してしまったのである。
このような試みをまっとうするのに、定家は「なかりけり」という一語をつかって「負」を現出できた。そしてまた、秋の夕暮だけに万事を万端まで残してみせた。
これが、ぼくが定家は特徴さえ消したいと思っているのではないかと見たことである。
◎すでによく知られているように、定家の歌、とくに「見渡せば」の歌は、武野紹鴎によって、千利休によって、さらに小堀遠州によって、茶の湯の心をあらわす最もぴったりしたものと最高の評価をうけた。このことを、よく考えてみる必要がある。
いま日本人の多くは日本の伝統文化をどうして未来につないでいこうかと検討をしている向きがあるようだが、何もそんなことに腐心することはない。紹鴎が、利休が、遠州が、定家の歌に戻ったことを凝視すればよい。
まず、歩むことである。そして見渡してみる。そこにはいろいろなものがあり、いろいろな出来事がある。けれども、そこには「ない」ものもある。われわれはいったい、この現実の世に何が「ない」と思っているのか。
侘び茶というものは、そこで本来なら唐物の道具や咲き乱れる萩がほしかったのに、いまはそれらがないことを侘び、手元にある一碗の茶碗と、一輪挿しの桔梗でなんとかお茶を入れるにすぎないのだということを表明した。
われわれもまた、同じことである。いろいろ欲しいと思う事態も、さまざま望む出来事も、あれこれ交わしたい人物もいる。しかし、たったいまのこのときには、手元にのこったもので工夫をすればよいのであろう。そして、そのときに「ない」から「ある」への創発がおこるのであろう。侘び茶というものもそうしたものだった。
ぼくには、定家の「好み」がそのように残されたと思われる。