
フェルナンド・ペソア『不穏の書、断章』


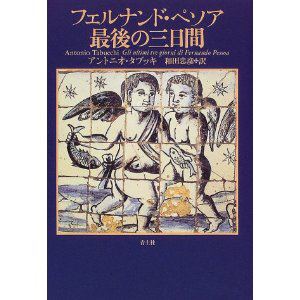
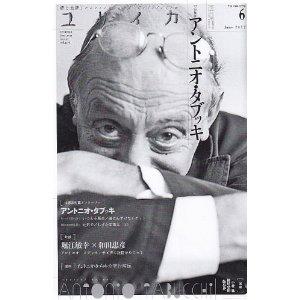
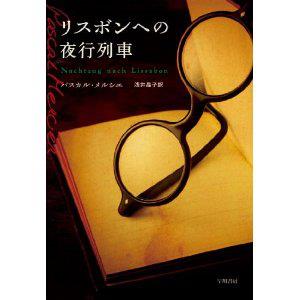
■フェルナンド・ペソア『不穏の書、断章』(澤田 直訳/平凡社ライブラリー2013.1.10)
ペソアを読むようになったのは、比較的最近のこと。
須賀敦子、タブッキ(『フェルナンド・ペソア最後の三日間』/
ユリイカ2012年6月号 特集=アントニオ・タブッキ)を経て、たどり着いた。
最初に読んだのは、現代思潮社の「ペソア詩集 (海外詩文庫)」。
たどり着いてみれば、ボルヘス、オクタビオ・パス、ロマン・ヤコブソン、
カルビーノからなんとドゥルーズまで、
この希有のポルトガル詩人、ペソアのことをさまざまに語っているのが目に入るようになった。
昨年翻訳されたスイスの作家パスカル メルシエの
『リスボンへの夜行列車』という哲学小説もまた、ペソアの言葉が背景に置かれている。
ペソアについて語るのは難しい。
少しばかり読むようになったぼくにも、いまだにペソアのことがよくわからない。
おそらくずっとわからないままだろう。ひょっとしたら訳者にも・・・。
わからないからこそ、ペソアのことが気にかかって仕方がなくなる。
けれど、このわからなさは、ふつうのわからなさとはまったく異なったわからなさだ。
まるで、ペソアを読んでいる自分が、いろんなペソアの分身になったかにようにさえ感じられ始める。
ペソアには、本人名義のほかに多くの異名
(ベルナルド・ソアレス、アルベルト・カエイロ、リカルド・レイス、アルヴァロ・カンボスなど)
で作品を書いているが、生前に出版されたのは本人名義の一冊の詩集と自費出版の英語訳詩集だけで、
死後、膨大な遺稿が整理され出版されたという。
ちなみに、この『不穏の書』は本人地もっとも近いともいえるベルナルド・ソアレス名義のもの。
ペソアは「詩と詩人」についてこう書いている。
「詩人はふりをするものだ そのふりは完璧すぎて
ほんとうに感じている 苦痛のふりまでしてしまう」。
「ふり」を完璧にすると、それそのものになっていまう。
しかしそうでなくては、詩人は「ふり」ができないのだ。
なぜペソアのことが気になるのか。
少しだけ腑に落ちたことがある。
それは、訳者の澤田直がペソアの『不穏の書』を
「バロック的な作品」であるといっているところである。
最近ぼくがバロック音楽を毎日紹介しているのもある意味でその流れなのかもしれない。
「『不穏の書』が具現するこのような複雑性、多面性、多孔性、
あるいは開放性はなにに由来するのだろうか。
ここでは暫定邸に、それがポルトガル芸術の根源的本質である
バロックに淵源を持つとだけ答えておこう。
『不穏の書』は、その生成、運動、不協和によって、すぐれてバロック的な作品だと言える。
ここに見られるのは、あらゆる物事の通過(トランジット)、異質なものとの絶えざる接触、
つねに別の者に、つまり自らの他者となることである。」
さて、いまだペソアをどのように紹介しようかわからずにいる。
仕方がないので、ボルヘスのことばを借りることにしたい。
「ペソア。あなたは、流派や、その教条やレトリックの虚しい形象や、
一国や一階級や一時台を代表せねばならなぬという執拗な義務感を、
造作なく捨てることができました。」
「あなたは自分のために書いたのであって、栄光のために書いたのではありませんでした。
私たちはあなたの詩篇を分かちあいましょう。どうか私をあなたの友だちであらせてください。」
ペソアの魔術にかかったぼくも、さまざまな権威や信条への依存を「造作なく捨て」て、
自分の自由のためになにがしかを書いておくことにしたいと思っている。
それはとくに発表するとか、知らしめたいとか、教えたいとかそういうこととははるかに遠い。
ぼくはぼくの「ふり」をしながら、ペソアが残したさまざまな「断片」のように語ることにしよう。
そして、そうすることで「ほんとうに感じている 苦痛のふりまで」してしまうほどに。